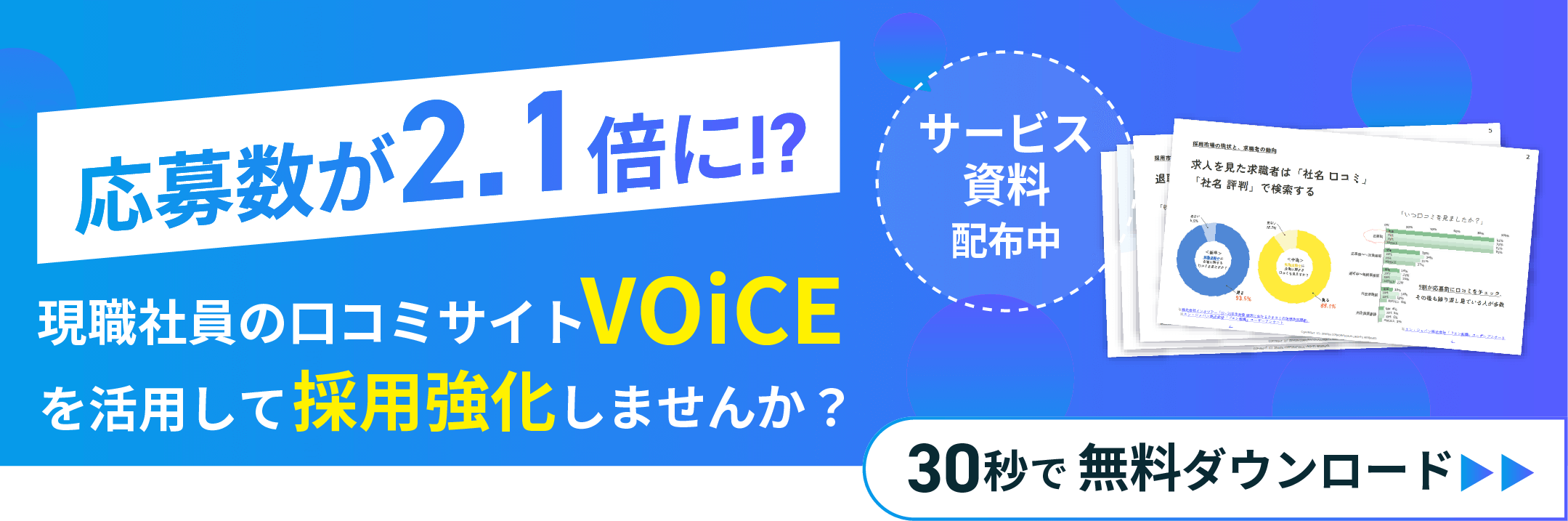なぜ“早期退職”を放置してはいけないのか?早期退職の原因と対策のための発信戦略
- 口コミ対策
- 採用ミスマッチ
- 離職防止
2025.09.07
採用活動に力を入れても、入社後すぐに退職者が出てしまう。
そのような経験をした経営者や人事責任者も多いでしょう。
「採用コストをかけてようやく採用した人材が数ヶ月で辞めてしまった」
「定着率が上がらず、毎年同じように採用活動を繰り返している」
このような状況は、組織の成長スピードを遅らせ、現場の負担も増大させる可能性があります。
特に中小企業や専門職では、採用1人あたりのコストが大きく、早期退職を繰り返せば人材戦略そのものが揺らぎかねません。
では、なぜ早期退職は繰り返されるのでしょうか。
その背景を探ると、表面的な待遇や労働時間の問題だけでなく「入社前と入社後のギャップ」という採用自体の構造的な問題が見えてきます。
本記事では、早期退職の原因を「情報の食い違い」という観点から整理し、VOiCE導入事例を交えながら、対策するための発信戦略の考え方をご紹介します。
第1章:早期退職の背景にある「入社前と後のギャップ」
求職者が抱く“理想と現実”のずれ
新しく採用した社員が早期退職する背景には「想像していた仕事と実際の仕事が違った」というギャップがあることも多いです。
求人票や採用ページで伝えられるのは、限られた情報です。
「成長できる環境」「風通しの良い社風」といった表現は前向きですが、具体的にどのような体験ができるかまでは伝わりづらいのです。
一方で、入社後の社員は日々の業務を通じて
- 想定以上の業務量や責任の重さ
- 勤務スタイルや休日の取り方の違い
- 社内の人間関係や価値観の相違
といった現実に直面します。
この差が「イメージと違った」という早期退職の引き金になる可能性があるのです。
ギャップがもたらす早期退職への影響
近年の求職者は、企業から提示される公式情報だけでなく、SNSや口コミサイト、個人ブログなども参考にしています。
特に若手世代は「実際に働く人の声」に信頼を置きやすい傾向があります。
そのため、事前に得られる情報が少ない、あるいは実態と乖離していると「この会社で長く働けるだろうか」と不安を抱きやすくなるのです。
こうした情報不足は、入社後に不一致を感じるリスクを高めます。
結果として、せっかくの採用活動が早期退職に結びついてしまう可能性が高くなるのです。
早期退職による企業への影響
早期退職がもたらす企業への影響は、採用コストや教育コストが活かしきれなくなるだけではありません。
現職社員のモチベーションにも影響します。
「また新人が早期退職した」という空気が広がれば、現場の士気が低下するおそれもあるのです。
さらに、求人市場において「早期退職が多い職場」という印象が広がると、次の採用活動に悪影響が及ぶことも。
つまり早期退職は、一度の損失にとどまらず、長期的な採用力の低下にもつながる可能性があるのです。
防止の鍵は“正しい情報提供”
こうした背景を考えると、早期退職を減らすためには、入社前の段階からリアルな情報を適切に発信することが大切です。
そのため、情報を発信するときは待遇や制度を強調するだけでなく、実際の社員の働き方や現場の雰囲気を見せる工夫をする必要があります。
このような「理想」と「現実」の差を少しでも縮めることが、定着率向上への第一歩といえるでしょう。

第2章:株式会社アクターリアリティー様のVOiCE導入事例 ― 「今」を伝える仕組みが定着率を高めた
事業紹介と採用への取り組み
株式会社アクターリアリティー様は、ソフトウェア開発(組込・制御、業務系)から、機械設計・電気電子設計といったハードウェア開発をメインに行っている企業です。メーカーとの直接取引で技術支援を提供してきました。2026年に創業20周年を迎えるにあたり、従業員数を400名規模へ拡大し、拠点数を13拠点に広げるという計画を進めています。
その実現のために、未経験の新卒層から経験豊富な中堅層まで幅広い人材を採用対象とし、主体的に取り組める人材との出会いを重視。同社のエンジニアは顧客からの評価も高く「担当を変えないでほしい」と指名を受けるケースもあるといった、人柄や姿勢が付加価値として認められている点が特徴です。
既存口コミサイトの課題
同社の採用活動において課題となっていたのが、既存の口コミサイトの影響でした。これらのサイトは転職希望者や退職者の投稿が中心であり、ネガティブな内容が集まりやすい傾向があります。また、古い口コミが長期間残るため、すでに改善された事柄であっても「現在も続いている問題」として求職者に受け取られてしまう可能性がありました。
変化のスピードが速い同社にとって、過去の情報が影響し、現状を正しく伝えにくい点が懸念だったのです。
VOiCE導入の決め手
こうした課題を解決する手段として選ばれたのが、現職社員の声を発信できるVOiCEです。既存の口コミサイトが退職者の意見を中心に掲載するのに対し、VOiCEは「今働いている社員の声」を発信できる仕組みである点が大きな特徴です。
特に注目されたのは「社員がなぜ働いているのか」「どのような魅力を感じているのか」を具体的に示せる点でした。求職者にとっては、企業のホームページに掲載された“理想的な姿”だけでなく、リアルな働き手の言葉も判断材料になります。加えて、ポジティブな声だけでなく現職社員が感じている課題も正直に発信できるため、入社前に双方が現実的な理解を持てるという点も導入の決め手となりました。
導入後に見えた効果
VOiCE導入後、面接現場には変化が現れました。応募者の中には「社員の声を読んで魅力を感じた」と動機を語る人や、事前に記事を読んだ上で「ここに記載のあった点について詳しく知りたい」と具体的な質問をする人も。
特にIT業界、中でもSESの働き方に不安を持つ人は多く、労働時間やフォロー体制に関する質問が目立ちます。VOiCEの情報を前提にしたコミュニケーションが行われることで、面接は「不安を軽減できる場」としても機能するようになりました。
結果として、入社前の理解度が高まり「想像と違った」という理由での早期退職は減少したとの声も。
導入を通じて得られた気づき
この取り組みを通じて同社が得た気づきは、採用広報において「社内の声を収集し、外部に届けるプロセス」が重要であるという点です。従来は外向きの発信を重視していたものの、社員の実感をもとに情報を整理することで、採用活動を実態に即したものに近づけることができました。
さらに、社員自身にとっても、自分がなぜこの会社で働いているのかを振り返る機会になったといいます。
同社は今後も拡大路線を進める中で、VOiCEを活用しながら「現在の姿」を継続的に発信し、自社の理念に共感する人材との出会いを強化していく考えです。
引用元:株式会社アクターリアリティー様導入事例(VOiCE公式サイト)https://www.shain-voice.com/case/aqtor
第3章:発信戦略としての「今を伝える方法」
採用広報における情報の見せ方
企業が採用広報を行う際、多くの場合は強みや魅力を中心に伝える傾向があります。もちろん企業の特徴を示すことは大切ですが、それだけでは「入社後のイメージ」とのずれが生じることも。仕事のやりがいや成長機会とあわせて、日々の業務の流れや組織の雰囲気といった具体的な側面もあらかじめ示しておくことで、候補者の理解が深まりやすくなります。
「働き方のリアル」をどう伝えるか
一方で、企業が自ら発信しようとすると、どうしても発信内容が一方通行になりがちです。社内の雰囲気や人間関係のように、外部から見えにくい情報は、候補者にとって不安材料になりやすい領域でもあります。ここで役立つのが、現場で働く社員自身の視点です。日常的に感じている小さな工夫ややり取りは、公式なメッセージ以上に候補者の参考になることがあります。
発信がもたらす定着への流れ
候補者が入社前に「この職場はこのような雰囲気で働いている」と具体的にイメージできると、入社後のギャップは小さくなります。その結果、早期退職につながる理由のひとつである「想定との違い」を減らすことが可能になります。また、情報発信は候補者だけでなく、現職社員にとっても「自分の経験が採用活動に役立っている」という実感につながり、組織への関与意識を高める側面もあります。
発信戦略の継続性
発信は一度で完結するものではなく、継続的に行うことで効果が見えやすくなります。季節ごとのイベントや制度の利用例、新しい取り組みなどを少しずつ紹介することで、企業の「今」が自然に伝わりやすくなります。情報を更新し続けることは、候補者に対しても誠実さや透明性を感じてもらいやすい要素となります。
第4章:発信を支える仕組みとしての「VOiCE」の特徴
VOiCEとは
VOiCEは、現職で働く社員によるリアルな声や評判を集めた口コミサイトです。一般的な口コミサイトと異なり、現職社員に社内アンケートを実施し、情報を発信する仕組みを持っています。そのため、外部からは見えにくい「実際の働き方」や「組織の雰囲気」を候補者に伝えやすいのが特徴です。
VOiCEの活用
採用広報に取り組む企業にとって、候補者との認識のずれを減らすことは大きな課題のひとつです。企業自身が伝える情報だけでは不十分に感じる場合や、候補者から「実際の働きやすさをもっと知りたい」という声が寄せられる場合もあります。VOiCEは、そうしたニーズに応えるための補完的なツールとして活用可能です。
他サービスとの違い
従来の口コミサイトは、投稿内容が匿名であるがゆえに、情報の信頼性や偏りに不安を抱く候補者もいました。VOiCEは「現職社員の声」に焦点を当てている点が特徴的で、発信内容の透明性を重視しています。これにより、候補者は片寄った情報に左右されにくくなる可能性があります。
活用によって期待できる効果
VOiCEを通じて現職社員が発信する情報は、候補者にとって「入社後のイメージを具体的に描く」手がかりとなります。企業にとっては、入社前の理解を深めてもらうことで、結果的に早期退職の原因のひとつである「入社後のギャップ」を小さくできます。また、社員自身が声を発信することにより「自分の経験が採用活動に役立っている」という感覚を得やすくなり、社内のエンゲージメント向上にもつながる側面があります。
発信戦略の一部としての位置づけ
VOiCEは単独で採用課題を解決するものではなく、あくまで企業の広報活動や採用戦略の一部として活用する位置づけにあります。他の取り組みと組み合わせることで、候補者に多角的な情報を提供する一助となります。継続的な情報更新を意識すれば、企業の「今」を伝えるための重要な補強要素となるでしょう。
第5章:まとめと今後の活用のヒント
早期退職の原因を減らすための情報発信の意義
採用活動においては、候補者の入社前理解を深めることが重要です。入社後のギャップは、早期退職の要因となることが多い傾向にあります。日常の働き方や組織の雰囲気など、現場の実態を具体的に伝えることは、候補者が入社後のイメージを持ちやすくなる手段のひとつです。
発信は一方的な情報提供ではなく、社員の声を活用することで、より現実に即した情報を届けられる可能性があります。候補者にとっても、企業の現状を理解した上で入社を判断できる環境は、入社後のミスマッチを減らす要素となるでしょう。
VOiCEを取り入れるポイント
VOiCEで現職社員の声を発信することで、入社前の理解を深める参考になります。活用する際には、次の点を意識すると情報の価値が高まります。
- 定期的に情報を更新し、現状を反映させる
- 採用活動の他施策と連携させて、多面的に情報提供する
こうした取り組みにより、候補者の理解度を高め、入社後の定着につなげやすくなることが期待できます。
今後の採用活動への活用
情報発信は一度行っただけで完結するものではありません。社内の変化や新たな取り組みを継続的に伝えることで、候補者に企業の「今」を伝えやすくなります。また、社員自身も自らの経験や考えを見直す機会となり、組織のエンゲージメント向上にもつながる可能性があります。
早期退職のリスクをなくすことは難しいですが、入社前の理解度を深めることで、候補者と企業の双方にとって納得感のある採用の仕組みを作れます。
VOiCEの活用を検討する
現職社員の声を活かした情報発信を検討される企業では、VOiCEの導入を選択肢のひとつとして考えられます。
公式サイトでは、導入事例やサービス内容の詳細を確認できるので、まずは自社の現状を整理した上で情報収集から始めてみると良いでしょう。