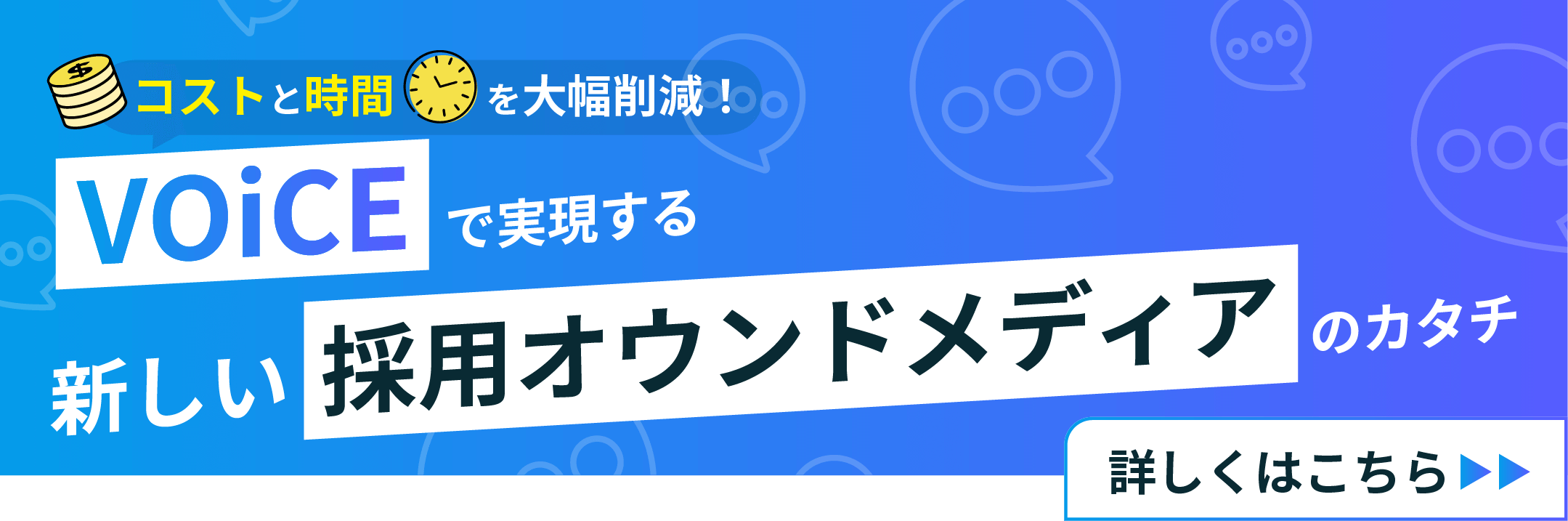採用ブランディングとは?
求職者に選ばれる企業になるための新常識
- 採用広報
- 採用強化
- 採用活動
2025.08.14
少子高齢化が進み、人材の獲得競争が激化する中、従来の「給与・待遇・福利厚生」だけをアピールする採用手法では、優秀な人材を惹きつけることが困難になっています。特に若年層やミレニアル世代、Z世代の求職者は「どのような人と働くのか」「どのような価値観を持つ企業か」「どのような働き方ができるか」といった、企業文化や共感性を重視する傾向が強まっています。
このような背景から、注目されているのが「採用ブランディング」という手法です。採用ブランディングとは、求職者に向けて自社の魅力を正しく伝えるための広報戦略であり、単なる求人広告とは一線を画します。本記事では、採用ブランディングの基本から、実践方法、そしてそれを強力にサポートするサービス「VOiCE」の活用方法までを詳しく解説します。
採用ブランディングとは何か?
採用ブランディング(Recruitment Branding)とは、自社の理念・文化・ビジョン・働き方・職場環境などを明確にし、求職者にとっての”魅力”として伝えるためのブランディング活動を指します。
採用ブランディングの目的
- ミスマッチの防止:企業側と求職者側の相互理解を深め、「こんなはずじゃなかった」という早期離職を防止します。
- 共感による応募促進:自社の価値観や文化に共感する人材からの応募を集めやすくなります。
- 採用コストの削減:ターゲット層に刺さるメッセージが伝わることで、無駄な広告費や面接の手間を削減できます。
- 企業価値の向上:社外のみならず社内にも良い影響を与え、社員のエンゲージメントや定着率を高めます。
求職者の視点の変化
現代の求職者は、給与や勤務地だけでなく「誰と働くか」「会社の価値観が自分と合っているか」「どのような働き方ができるか」といった内面的な要素を重視します。こうした視点に対応するには、企業の内面を伝える情報設計が不可欠です。
採用ブランディングが必要とされる背景
1. 働き方の多様化
テレワーク、副業解禁、フレックス制度など、働き方の選択肢が増えたことで、求職者の”企業選びの基準”が多様化しています。自社の制度や柔軟性を発信することは、選ばれる理由の一つになります。求職者は、自分らしい働き方ができる環境かどうかを見極めようとしています。
2. SNSと口コミの影響力
転職サイトや口コミサイト、SNSでの社員の声は、企業の「第二の広報」となっています。こうした声を積極的に活用し、ポジティブな企業イメージを形成することが採用ブランディングの要となります。転職会議やOpenWorkなどの口コミサイト上での評判が応募者の意思決定に直結することも珍しくありません。
3. 優秀な人材の獲得競争
エンジニア、マーケター、デザイナーなど、専門性の高い人材の争奪戦が続いています。他社と差別化するためには、給料以外の「働く意味」や「成長機会」を伝える工夫が求められます。また、多くの企業が似たような条件を提示している今「どこで誰と、どのように働くのか」が差別化の決め手になります。
4. 採用市場の”感情的判断”
データだけでなく、感情的な共感や直感も求職者の意思決定に強く影響しています。理屈ではなく「なんとなく良さそう」と感じさせる情緒的価値の訴求も必要です。

採用ブランディングの効果的な施策
1. 社員の声を活用したコンテンツづくり
求職者が知りたいのは、現場のリアルな声です。社員インタビューや座談会、社内イベントの紹介など、実際の働き手の視点から語られるコンテンツは共感を呼びやすくなります。特に新卒採用では、若手社員の一日密着記事や入社理由、社内での成長体験が人気です。
2. コーポレートサイト・採用サイトの強化
「会社案内」「ミッション・ビジョン・バリュー」「キャリアパス」などの情報を整理・可視化し、分かりやすく伝えることが重要です。さらに、動画や写真、ブログ形式の導入により臨場感を出すことが効果的です。近年ではスマートフォン対応の採用サイトも必須であり、UI/UXの最適化も重要です。
3. SNSやオウンドメディアの活用
InstagramやYouTubeなど、ビジュアルに強いSNSは、職場の雰囲気や社員の素顔を伝えるのに最適です。また、採用専門のオウンドメディアを活用することで、継続的な情報発信が可能になります。コンテンツマーケティングの観点からも、ブログやnoteを活用して、社員自らの発信を促すことが有効です。
4. イベント・インターン・説明会の設計
オフライン・オンライン問わず、求職者と接点を持つ場のデザインも採用ブランディングの一環です。「カルチャーマッチ」をテーマにした座談会や、職種横断のインターン企画なども評価されています。
VOiCEが提供する「リアルな職場の空気感」
採用ブランディングを実現する上で、有効なツールとなるのが、現職社員のリアルな声を可視化する口コミサイト「VOiCE」です。
VOiCEとは?
VOiCEは、企業の内面を、現職社員の言葉で伝えることに特化した口コミサービスです。求人広告や企業パンフレットでは表現しきれない、「空気感」や「人間関係」「価値観」といった、目に見えない魅力を発信できます。
VOiCEを使うメリット
- 共感を呼ぶ採用広報が可能:求職者にとって信頼できる一次情報となり、応募率の向上につながります。
- ミスマッチの防止:実際の職場の雰囲気を事前に伝えることで、入社後のギャップを減らす手助けになります。
- 社内理解の深化:社員自身が自社の価値を再認識する機会にもなり、社内の一体感やエンゲージメントが高まります。
- 定量データの可視化:社員の発言やキーワードを可視化し、どのような価値観が共通しているかを分析可能です。
実際の活用事例:共感が採用力を変える
あるITエンジニア派遣事業を展開する成長企業は、この数年間で社員数を80名台から900名以上へと拡大しています。(出典:VOiCE導入事例「第三の視点、VOiCEの“現職社員の声”が求職者の納得値を高め、正しい自社理解を叶える【株式会社ボールド】」https://www.shain-voice.com/case/bold)その過程で課題となったのが、口コミサイトなどに掲載される過去の情報による誤解です。すでに解消された制度や運用上の問題が、依然として求職者にネガティブな印象を与えていたため、現場の最新情報をどう正しく届けるかが大きなテーマとなっていました。
そこで活用されたのが、社員のリアルな声を発信するVOiCEの仕組みです。インタビュー形式で現職社員の働く様子や職場環境を紹介することで、企業の実態がダイレクトに伝わるようになり、求職者の理解と共感を得る効果が見られました。
採用面接の場では、以前よりも応募者からの質問の質が変化し、より深い理解を前提とした対話が可能に。企業側の説明負担が軽減されただけでなく、相互理解が進むことで採用後のミスマッチも減少しました。
さらに、入社を悩んでいた内定者に対し、現職社員の実体験を紹介した記事を提示したところ、企業文化への理解と安心感が生まれ、最終的には入社を決意するケースも見られました。
このように、現場の声を継続的に発信することで、単なる制度紹介では伝わりきらない「職場の空気感」や「人との関係性」が明確化され、候補者にとっての納得感を高める採用広報が実現されています。また、社員自身も改めて自社の魅力を認識するきっかけとなり、組織全体の一体感や定着率の向上にも寄与しています。
出典:VOiCE導入事例「第三の視点、VOiCEの“現職社員の声”が求職者の納得値を高め、正しい自社理解を叶える【株式会社ボールド】」https://www.shain-voice.com/case/bold (参照日:2025年7月13日)
採用ブランディングの成功に向けたステップ
- 自社の強みと価値観を整理する:企業のミッションやビジョン、これまでの実績、社内文化などを棚卸し、他社にはない独自の魅力を明確にすることが出発点です。社内外の評価や社員の声も参考に、言語化しておくことが後の発信の土台になります。
- 理想の候補者像を明確にする:スキルや経験だけでなく、価値観や働き方への考え方など、企業とフィットする人物像を具体的に描きます。ペルソナを作成することで、採用広報の方向性がブレずに伝えられます。
- 社員の声を収集・可視化する:現職社員へのインタビューやアンケートを通じて、生の声を集めます。ポジティブな意見だけでなく、改善点への意見も含めて整理することで、よりリアルな社内像が浮かび上がります。
- 採用サイト・SNS・VOiCEなどで発信する:集めた情報を、ターゲットに合わせたメディアやフォーマットで発信します。採用サイトやSNS、VOiCEといったツールを活用し、求職者が自然と触れられる導線を設計します。
- 定期的にデータを分析し、改善を重ねる:応募率、閲覧数、コンテンツごとの反応などをモニタリングし、改善サイクルを回します。数字だけでなく候補者の声や面接での反応も取り入れてブラッシュアップしましょう。
- 現場を巻き込んだ体制づくり:人事部門だけでなく、各部署の巻き込みが成果を左右します。社員が自ら広報に関与できるよう、参加のハードルを下げ、現場主導の発信を促す仕組みを設けましょう。
- 社員エンゲージメントを高めるインターナルブランディングの実施:社外に発信する前に、社員自身が自社の魅力に納得していることが重要です。社内報や社内イベント、理念共有のワークショップを通じて社員の意識を高め、外部への発信力を養います。
- 定量・定性の両面からの効果測定:応募者数や定着率といった数値面だけでなく、候補者の声・入社後の満足度調査などの定性データも活用し、戦略を改善していきます。
- 継続的な情報発信の仕組みづくり:採用ブランディングは一過性の取り組みではありません。年間計画を立て、コンテンツ制作スケジュール、SNS配信日程、社内取材の体制構築など、長期的な運用体制を整えましょう。
- 多様な人材の視点を取り入れる:ジェンダー、年齢、国籍、バックグラウンドの多様な社員の声を発信することで、多様性を尊重する企業文化を示せます。特に海外人材やシニア人材、障がい者雇用などに取り組む企業は、それを「価値」として伝える姿勢が必要です。
このように、採用ブランディングは「戦略」と「運用」の両軸があってこそ成果が見えてきます。
採用ブランディングの課題と乗り越え方
採用ブランディングは重要性が増す一方で、実際に取り組むとなるといくつかの壁に直面します。以下に代表的な課題とその対処法を紹介します。
1. 社内理解が得られない
採用ブランディングは人事部門だけで進められるものではありません。経営層の理解と現場部門の協力が不可欠です。社内向けの説明会や経営層インタビューなどを通じて、重要性を浸透させることが大切です。
2. 発信するネタが続かない
コンテンツの持続性に悩む企業も多く見られます。インタビュー対象を毎月固定する、チーム単位で社内広報委員を立てるなど、仕組み化と分業化がカギです。社内SNSやグループチャットでネタ出しを促進する方法も有効です。
3. “キレイすぎる”内容ばかりになってしまう
リアルな魅力を伝えるには、弱みや課題も包み隠さず見せる勇気が必要です。あえて課題を共有し、それに向き合う姿勢を発信することで、求職者の共感を得られるケースも増えています。
採用ブランディングと経営戦略の連動
採用ブランディングは、単に採用数を増やすための施策ではありません。中長期的には、企業の成長戦略と密接に関係しています。
- ブランドイメージの確立:採用でのブランド力は、顧客や取引先からの信頼にも直結します。
- カルチャー・フィットの促進:理念やビジョンへの共感を重視した採用は、組織文化の形成と維持に役立ちます。
- 人材ポートフォリオの最適化:経営計画に合わせて必要な人材像を定義し、それに合致した人材を採用するための基盤となります。
特に成長フェーズにある企業においては、「未来をともに創る仲間」をいかに引き寄せるかが、競争優位を左右する重要な鍵となるのです。
まとめ:本当に自社に合う人材に出会うために
優秀な人材ほど、企業の外面だけでなく「中身」を見ています。採用ブランディングは、単なるブームではなく、今後の採用活動のスタンダードになるといっても過言ではありません。
そして、それを支えるのが「VOiCE」です。現職社員のリアルな声を通じて、職場の空気感や価値観を可視化し、求職者の共感を呼ぶ情報発信を可能にします。
これからの採用は、企業と求職者の「共感と対話」が軸になります。「伝えたいこと」ではなく、「伝わること」を意識し、企業の個性や文化を魅力として打ち出す戦略が求められます。
本当に自社に合う人材に出会いたい──その願いを叶えるために、まずは採用ブランディングから始めてみませんか?