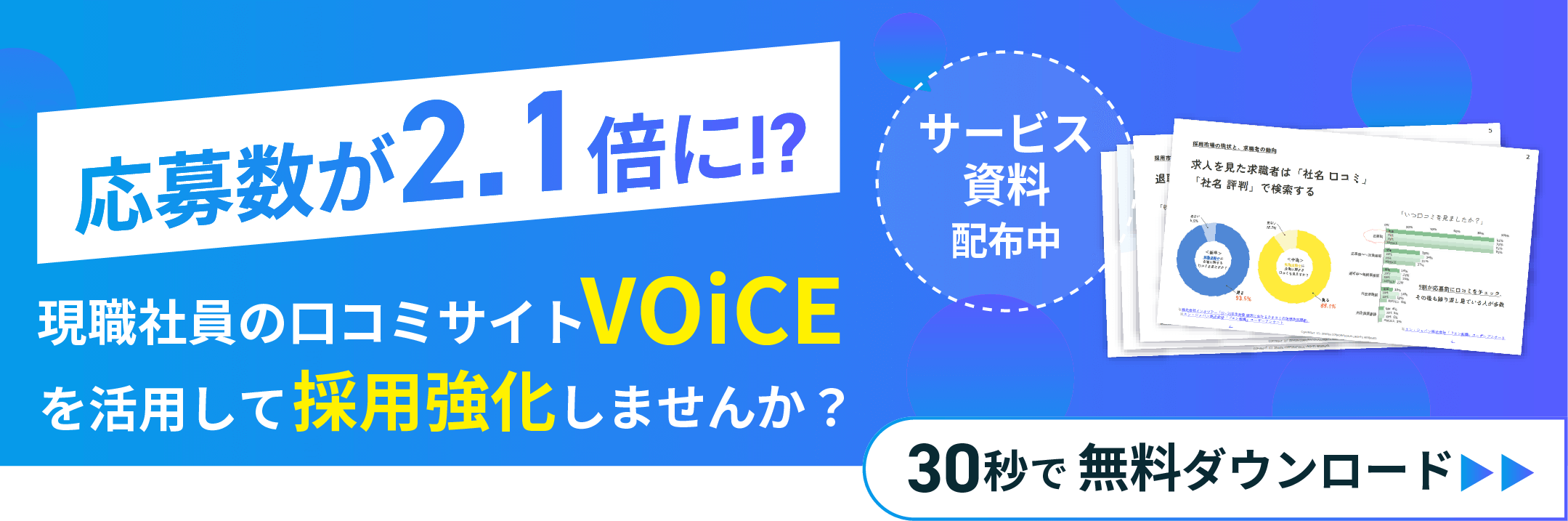主要な企業口コミサイト5つを比較|
求職者が本当に見ているサイトと企業側の対応策とは
- 会社の評判
- 口コミ対策
- 採用強化
2025.08.14
口コミサイトはたくさんあるけれど──企業が本当に知っておくべき視点とは?
インターネット上には、企業の「評判」や「働きやすさ」を伝えるさまざまな口コミサイトが存在します。特に近年は、求職者が企業選びの参考にこうしたサイトを閲覧することが一般化しつつあり、採用活動における“企業イメージ”の重要性は高まっています。
「給与水準は?」「残業は多い?」「社風は合いそうか?」
──そういった疑問に対して、企業公式の情報ではなく、“中の人”のリアルな声を求めて、口コミサイトを訪れるのが今の求職者の当たり前の行動です。
しかし、企業側の視点で見てみると「そもそもどの口コミサイトが見られているのか分からない」「ネガティブな書き込みばかりが残って困っている」という悩みも多く寄せられます。
本記事では、代表的な企業口コミサイトの比較や、企業が取るべき対応策、そして“見られる時代”から“見せる時代”へと移り変わる採用戦略の考え方を解説します。
また、最後には企業側からポジティブな情報を発信できる新しい口コミ戦略ツール「VOiCE」についてもご紹介します。
第1章:代表的な口コミサイトの比較とその特徴
企業に対する評価を収集・閲覧できる口コミサイトは数多く存在しますが、すべてのサイトが同じ性質を持っているわけではありません。
ここでは、求職者からの閲覧数が多く、採用活動における影響力が大きい代表的な口コミサイトを5つピックアップし、それぞれの特徴を解説します。
1. 転職会議|転職希望者の“転職軸”に訴える情報が豊富
特徴:
- 国内でも大規模な企業口コミ掲載数を誇る
- 口コミ閲覧には自らの口コミ投稿が必要(情報の信頼度が比較的高い)
- 年収・残業・福利厚生・社風など幅広い項目で評価
採用担当者にとっての注目点:
「転職を本気で検討している人」が多く利用しており、求人応募の直前にチェックされることも少なくありません。掲載内容が古いまま放置されていると、時代遅れなイメージを与える可能性があります。
2. OpenWork(旧Vorkers)|“働きがい”を重視する層に人気
特徴:
- 社員満足度を数値化したスコア評価
- レビュー対象は在籍経験のある社員や元社員
- 「働きがい」や「人間関係」などソフト面の評価が豊富
採用担当者にとっての注目点:
新卒・中途問わず「自分に合ったカルチャーか」を重視する候補者に多く読まれており、社風やリーダーシップに関する記述が採否を左右する場合も。中小企業も一定数掲載されており、無視できない存在です。
3. エンゲージ会社の評判(旧Lighthouse)|求職者との接点が広いポータル型
特徴:
- エン転職などの求人媒体と連携
- 求人情報と口コミをワンストップで閲覧できる
- 企業からの返信機能あり(ただし対応していない企業も多い)
採用担当者にとっての注目点:
「求人を見たついでに口コミも見る」という導線があるため、ライトな転職希望者や情報収集段階の層にも閲覧されやすい傾向があります。企業として口コミにコメント対応できる点は、印象改善に活かせます。
4. Indeed企業ページ|口コミと求人が統合された“入り口サイト”
特徴:
- 求人検索エンジン「Indeed」の中に口コミタブが存在
- 採用情報と併せて自社ページを構築できる
- 無料での運用も可能だが、広告配信により優先表示される
採用担当者にとっての注目点:
「求人情報を探すために訪れたユーザーが企業イメージを確認する場」になっているため、口コミの内容や量が企業ページ全体の印象を左右します。運用によっては戦略的に活用可能。
5. Googleマップの口コミ|実は盲点になりがちな“外部の評価”
特徴:
- オフィス所在地のGoogleビジネスプロフィール上で評価・コメントが可能
- 面接や職場体験に来た人が投稿するケースも
- 企業が返信できる
採用担当者にとっての注目点:
飲食店や病院に限らず、企業アカウントに対しても口コミがついていることがあり、知らぬ間にネガティブな印象がついてしまっているケースも。放置せず、定期的にチェックと対応を。
総評:見られているサイトは1つではない
多くの人事担当者が、特定のサイトだけを気にしてしまいがちですが、求職者は複数サイトを横断的に見て判断しているケースが多いです。
特にネガティブな内容が複数のプラットフォームに分散していると「これは事実なのかも」と信憑性を高めてしまうこともあるため、企業としては包括的なモニタリングと対応が求められます。

第2章:採用サイト改善のための3つの視点
──「口コミ」と「自社発信」のバランスを見直すタイミング
企業口コミサイトの存在感が高まる中、自社の採用活動を再設計する上で重要になるのが「採用サイト」との連動性です。
多くの企業がコーポレートサイト内に採用情報ページを設けていますが、それだけで“企業の魅力”は伝わるでしょうか?
答えはNOです。
今、求職者が重視するのは「言っていること」と「実際の声」が一致しているかどうか。
ここでは、企業が採用ブランディングを見直す際に意識すべき3つの視点をご紹介します。
1. 受け身の「情報掲載」から、選ばれるための「情報設計」へ
よく見られる課題は、「採用情報ページ=募集要項の羅列」にとどまってしまっているケースです。
確かに、職種・勤務地・給与などの要件は重要ですが、それだけでは企業としての魅力は伝わりません。
求職者が知りたいのは:
- 実際にどのような人が働いているのか
- どのような価値観・カルチャーを大事にしているのか
- 入社後にどのようなキャリアが描けるのか
こうした情報は口コミサイトの中では自然と語られており、それと同じ熱量で採用サイトにも反映させることで、ミスマッチを防ぎ、「想像通りの会社だった」と言われるようになります。
2. 「一次情報」こそが差別化の決め手
自社の魅力を伝える手段として、社員インタビューや1日密着レポート、オフィス紹介動画などを取り入れている企業も増えています。
こうした取り組みは、まさに“口コミ的”な価値を企業側から創り出すアプローチといえるでしょう。
ポイントは、飾りすぎず“リアル”を見せること。
SNSの発信や採用ブログなども含め、一次情報(社内で自ら発信する情報)を積極的に展開している企業ほど、口コミサイトでの評価も高まりやすい傾向があります。
3. ネガティブな印象を恐れず、“その先の改善姿勢”を伝える
口コミサイトにネガティブな意見があると、つい見なかったことにしたくなるものです。
しかし、実は「不満点があったが、改善された」「上司の対応が変わった」など、“ポジティブな変化”が見えるコメントほど、閲覧者の信頼を集めます。
だからこそ、自社発信の中にも、「社員の声を元に制度を改善しました」「現場からの提案で新しい仕組みを導入しました」といった変化を積極的に伝えていくことが、企業の誠実な姿勢として受け止められるのです。
第3章:“見られる”時代から“見せる”時代へ──口コミ戦略の視点を変える
──ネガティブ対応ではなく、ポジティブをどう“設計”するか?
口コミというと、どうしても「ネガティブ対策」「炎上防止」といった“守り”のイメージが強いかもしれません。
しかし今、優秀な人材の獲得競争が激化する中で、「口コミの見られ方」ではなく、「口コミの見せ方」に着目する企業が増えつつあります。
言い換えると、“見られる”ことを前提とした受動的な姿勢から、“見せる”ための能動的な設計へ。
この視点の変化こそが、企業の採用ブランディングを大きく前進させる鍵となります。
1. なぜネガティブ対応だけでは不十分なのか?
これまでの口コミ対策は、以下のような対応が見られることも。
- 否定的な投稿への削除依頼や通報
- 弁護士や外部コンサルを通じた法的対応
- 社内共有を避け、“見ないようにする”文化
これらは「守り」として一定の効果はありますが、根本的なブランド価値の向上にはつながりにくいのが現実です。
それに加え、削除された口コミの「痕跡」すらもネット上では記憶され続けることがあり、消すことは難しいのです。
2. ポジティブな声は“自然には拡がらない”
実際の現場では、社員の多くが企業の魅力を感じながら働いていたとしても、ポジティブな声はなかなか外部に出ていきません。
なぜなら「満足している人」は特に何も言わず、「不満がある人」ほど書きたくなる傾向があるからです。
この“構造的な偏り”こそが、口コミサイトにネガティブな意見が集まりやすい背景であり、企業側がそれを前提とした情報戦略を取る必要があります。
3. ポジティブな口コミは“仕組み”でつくる
ここで重要になるのが、「ポジティブな口コミは設計し、意図的に発信できる」という視点です。
たとえば:
- 社員アンケートで満足度の高いコメントをピックアップ
- 若手社員や育児中の社員に「働きやすさ」に関するストーリーを発信してもらう
- 自社の採用ブログやオウンドメディアに“社内の良いエピソード”を載せる
これらは口コミサイトに頼らずとも、「口コミ的価値」を創り出せる取り組みであり、自然なかたちで企業の魅力を伝える力を持ちます。
4. “言われっぱなし”ではなく、“発信力”を持つ企業へ
重要なのは、企業として“発信する姿勢”を持っているかどうかです。
これからの時代、働き方や企業文化を発信する力は、採用における競争力となります。
人事がただ応募者を待つのではなく、経営と一体となって「どのような仲間を求めていて」「どのような未来を描いているのか」を伝えること。
その姿勢が口コミとのギャップを埋め、候補者の“共感”を呼び、採用の質と歩留まりを大きく改善する要因となるのです。
第4章:ポジティブな印象形成を支援する「VOiCE」の特徴とは
──口コミの“見せ方”をデザインする新たな選択肢
ここまで、口コミに対して「守り」ではなく「攻め」の姿勢で臨む重要性をお伝えしてきました。
そして今、その“攻めの口コミ戦略”を実現するための具体的なツールとして注目されているのが、企業向けポジティブ情報発信支援ツール「VOiCE」です。
従来の口コミサイトでは、企業は“評価される側”であり、意図的にポジティブな情報を発信することが難しい環境にありました。
一方VOiCEは、企業自らがポジティブな社員の声・実績・取り組みを集めて、戦略的に発信できる仕組みを提供しています。
VOiCEの主な特徴
1. 社員の“リアルな声”を引き出す独自アンケート設計
VOiCEでは、社員からヒアリングする質問設計そのものにノウハウがあります。
「職場でうれしかったことは?」「この会社に入ってよかったと思う瞬間は?」といった、エンゲージメントが見える質問を通して、ポジティブで温度感のある声を引き出します。
それをそのまま発信できるため、装飾された採用コピーよりもずっと高い説得力を持ちます。
2. 企業専用の口コミ掲載ページを構築
集めたポジティブな声は、VOiCE内で専用ページとして展開されます。
コメント・職種・年代などを掛け合わせることで、応募者にとって「自分と重ねられる情報」がそろい、共感性の高いコンテンツとなります。
さらに、このページは検索エンジンにも最適化されており、企業名+評判などのキーワード検索にも強く、第三者視点でのポジティブ情報が上位表示される効果も期待できます。
3. 課題を“見える化”し、改善につなげるレポート機能
ポジティブな声だけを集めて終わりではありません。
VOiCEでは、社員の声をスコアリング・分析し、エンゲージメントの高低・改善ポイントを数値で把握できます。
これにより、単なる情報発信にとどまらず、経営や人事施策へのフィードバックツールとしても活用できるのです。
第5章:まとめ──企業の“見られ方”は、自ら変えられる時代へ
──いま必要なのは、口コミに振り回されない“発信する姿勢”
これまで見てきたように、企業の口コミは「管理しきれない外部評価」ではなく、「戦略的に活かすべき資産」へと変わりつつあります。
口コミサイトが一般化した今、求職者にとって企業の“印象”は、求人票や採用ページではなく、第三者の声を通して決まることも珍しくありません。
一方で、企業ができることは確実にあります。
それは──「見られることを恐れず、見せる力を育てる」こと。
企業が今、始めるべき3つのアクション
- 自社が掲載されている口コミサイトをすべて洗い出す
まずは「どのサイトに、どのような声があるのか」を把握することからスタートしましょう。
意外なところでネガティブなコメントが目立っているケースも少なくありません。 - 採用サイトや求人原稿との整合性をチェックする
発信しているメッセージと、第三者が語る印象に大きなズレがないかを確認しましょう。
口コミは候補者との“第一接点”になり得ます。 - ポジティブな情報を意識的に“見せていく”仕組みを整える
VOiCEのようなツールを活用して、社員のリアルな声を“資産化”し、発信する仕組みを取り入れることで、企業の採用力は確実に変わっていきます。
誰かに語られる前に、自ら語る企業へ
これからの採用ブランディングにおいて強い企業とは、
「他人にどう語られるか」ではなく、「自分たちでどう語るか」を決められる企業です。
口コミは“避けるもの”ではなく、“活かすもの”。
ポジティブな声を可視化し、戦略的に届けることができれば、採用における情報格差を減らし、ミスマッチの少ない本質的な採用へとつながります。