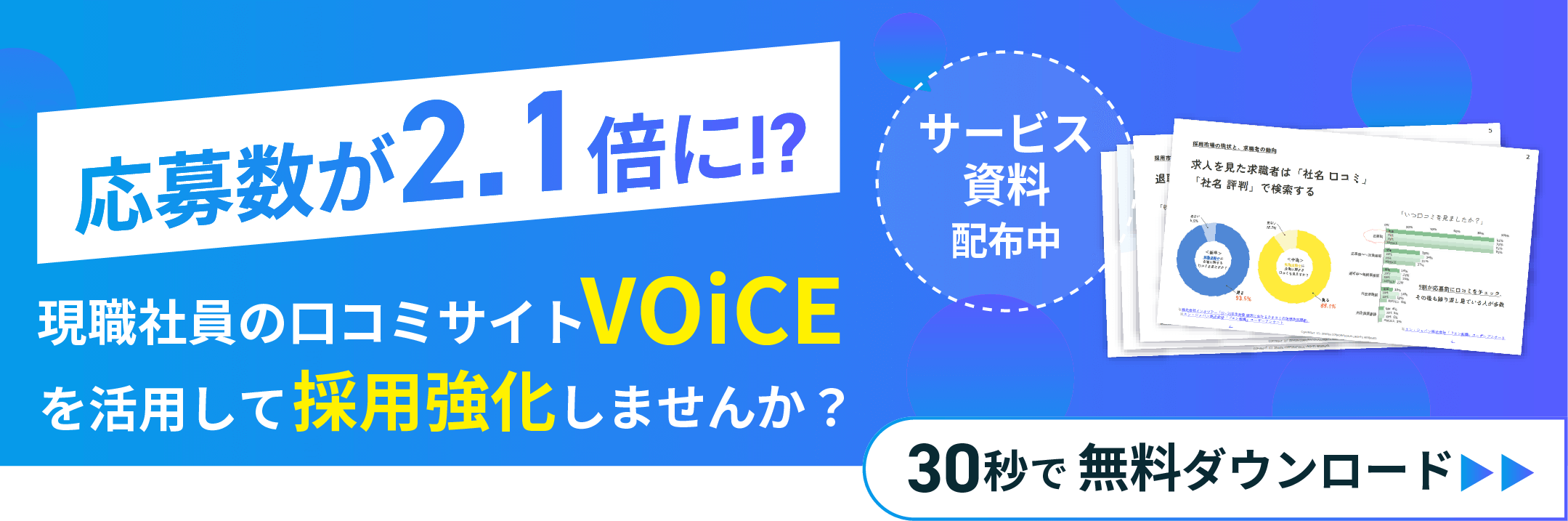悪評で人材を逃さない!
企業の信頼を高める口コミ対策と採用戦略
- 会社の評判
- 口コミ対策
- 採用強化
2025.08.14
かつての採用活動は、企業側が主導権を握る“選ぶ立場”のものでした。しかし現代では、候補者が企業を“選ぶ”時代です。求人情報や公式サイトだけでなく、口コミサイトやSNSを通じて企業の内情をリサーチし、応募の可否を判断する求職者が急増しています。
こうした背景の中、検索結果に現れる企業の情報は「採用広報の顔」ともいえる存在になりました。特に「○○株式会社 評判」「○○社 ブラック」など、企業名とセットでネガティブなワードが検索されるケースは珍しくありません。求職者にとってその結果は、「応募するかどうか」の重要な判断材料になります。
しかし、多くの企業が見落としがちなのは、“企業の顔”が第三者によって形作られているという現実です。匿名の投稿者が、時には退職者が、自社についての一方的な意見を投稿し、それがネット上に残ることがある──こうした構造に対する認識と対応が、採用活動の成否を分ける分岐点になっているのです。
本記事では、企業にとって頭の痛いテーマである否定的な口コミへの対応について、削除が難しい現実を踏まえた上で、いかにして新たな情報を発信し、企業としての印象を再構築していくか。その考え方と実践的な方法をご紹介します。
企業に広がるネガティブ情報の正体とは?──その多くは退職者の声
「うちの会社、なぜこんなにも悪く書かれているのか?」
多くの経営者や人事担当者が抱くこの疑問。その答えの多くは、口コミの“発信者”にあります。企業に対して否定的な投稿を行う人物の多くは、現職社員ではなく、すでに退職した元従業員の場合が多いです。
退職者がネガティブな情報を発信する背景には、複雑な心理が存在します。期待して入社したが理想とのギャップを感じた、上司や社風と合わなかった、キャリアが思うように築けなかった──そうした不満や後悔が、口コミという形で表に現れるのです。
加えて、投稿の多くが匿名で行われるため、内容の正確性や公平性が担保されにくいという側面もあります。事実に基づいた意見もあれば、感情に偏った一方的な表現も混在しています。にもかかわらず、口コミサイトの構造上、ネガティブな内容の方が「リアルな声」として注目されやすく、検索エンジンでも上位に表示されがちです。
また、口コミは時間とともに“積み重なる”性質があります。過去に書かれた投稿が、何年経っても削除されずに残り続けることで、企業のイメージは次第に否定的な方向へと傾いていきます。たとえ現在の職場環境が改善されていたとしても、古い情報が先に表示されてしまえば、求職者には正しく伝わりません。
ここで重要なのは、悪評の多くが「過去の一部の声」であるという認識です。そして、企業としての現在地や本来の価値が、求職者にきちんと届いていないという“伝達のズレ”が問題の本質なのです。
このような背景から、ただ嘆くだけではなく、誰が何の目的で発信しているのかを冷静に分析することが、まず最初の一歩です。そして、それを踏まえた上で企業が取るべき行動とは何か──次章では、否定的な情報を放置することで生まれる具体的なリスクについて詳しく解説します。
そのまま放置するとどうなる?悪評の蓄積が招く主な3つのリスク
否定的な口コミに気づいていながらも「事実と異なるから気にしなくていい」「どうせ応募者も分かってくれるだろう」と、対応を後回しにしていないでしょうか。
しかし、その“放置”こそが、企業にとって重大なリスクを招く要因になります。ここでは、悪評を無視し続けた場合に生じうる3つの代表的なリスクについて解説します。
① 優秀な人材の獲得チャンスを失う
近年、求職者は「企業の中身」を知ろうと、転職サイトだけでなく口コミサイトやSNSまで細かくチェックする傾向にあります。特にミドル層やハイキャリア層ほど、企業選びに慎重であり、検索結果の第一印象が意思決定に大きな影響を与えます。
たとえば、「社内の雰囲気が悪い」「マネジメントが機能していない」といった否定的な投稿が上位に表示されていれば、せっかく募集を出しても最初の応募すら見込めなくなることも。応募率が下がるだけでなく、期待していた層からの反応が得られず、採用コストばかりが増えるという悪循環に陥ります。
② 内定辞退・早期離職を招く
仮に悪評を見た上で応募し、選考が進んだとしても、面接の段階で「口コミに書かれていたことは本当ですか?」と質問されることは珍しくありません。そこで納得のいく説明ができなければ、内定後の辞退や、入社後すぐの退職にもつながりかねません。
特に、企業としてのイメージと実際の環境が乖離している場合、口コミが“真実”として機能してしまうこともあります。これは採用活動だけでなく、社内の定着率や信頼にも直結する深刻な問題です。
③ ブランドイメージの毀損と長期的な信用低下
採用に限らず、口コミサイトは社外ステークホルダー──たとえば取引先、投資家、将来のパートナー企業などにも閲覧されうる情報源です。
「社員を大切にしていない会社」
「経営層が現場を理解していない」
「ハラスメントが蔓延している」
こうした印象が検索結果に並んでいれば、いくら表向きにPRを頑張っても、信頼回復は困難です。企業ブランドとは、意図的に作るものではなく、“他者にどう見られているか”によって自然と形成されていくものだからです。
このように、ネガティブな情報を軽視することは、採用の効率低下だけでなく、企業全体の評判や信頼性にまで悪影響を及ぼす可能性を孕んでいます。
特に問題なのは、こうした情報が時間の経過とともに埋もれるどころか、むしろ検索結果の目立つ場所に居座り続けてしまう点です。企業としての現在の姿が正しく伝わらない状況が続けば、あらぬ誤解を生み、評価の回復がますます困難になります。
企業の実情と外部から見える印象との“ギャップ”をどう埋めるか。それが、次に考えるべき課題です。

否定的な情報はなぜ検索上位に出るのか?検索エンジンの仕組みを知る
多くの企業が戸惑うのは、「数ある情報の中で、なぜあのネガティブな口コミだけが目立って表示されてしまうのか?」という点です。
この現象の裏には、検索エンジンの仕組み──つまり、Googleなどが情報を評価・表示するルール(アルゴリズム)が大きく関係しています。
1. ユーザーの関心が集まりやすい“ネガティブ情報”の特性
人は本能的にリスクを避けたいという心理を持っており、ポジティブな情報よりもネガティブな情報に強く反応する傾向があります。口コミサイトの閲覧者も例外ではなく、「この会社、やばくないか?」「ブラックかも?」と感じさせる投稿ほどクリックされやすく、SNS等でシェアされやすくなります。
検索エンジンは、ユーザーの行動をもとに表示順位を決定するため、クリック数や閲覧時間が長いページは「価値が高い」と判断され、結果的に上位表示されやすくなるのです。
2. 継続的にアクセスがある“口コミ系ドメイン”の強さ
もうひとつの理由は、口コミサイトそのものが非常にSEOに強い構造になっている点です。
たとえば「転職会議」「OpenWork」「エンゲージ会社の評判」などのプラットフォームは、企業名を含んだページを網羅しており、しかも毎日のように投稿や閲覧が行われています。
これらのサイトはドメイン全体の評価が高く、検索エンジンから“信頼性のある情報源”とみなされているため、少数の投稿でもページ単位で上位に表示されてしまうことがあります。結果として、企業名で検索した際に、自社がコントロールできない第三者の意見が真っ先に目に入る──という状況が生まれやすくなるのです。
3. ポジティブな情報がそもそも「存在しない」リスク
もうひとつ見落とされがちなのが、「ネガティブ情報が目立つ」のではなく、「ポジティブ情報が何もない」というケースです。
現場で活躍する社員の声、取り組んでいる制度や文化、社内の実際の雰囲気──そうしたリアルな情報が外部に発信されていないと、検索エンジンにとっては“比較できる情報がない状態”になります。
その結果、退職者の声が“企業の真実”として検索結果に固定化され、時間が経っても状況が変わらなくなってしまうのです。
否定的な投稿が上位に表示され続ける背景には、こうした複合的な要因が重なっています。
それでも、「情報の出し方」を少し工夫するだけで、外部からの見られ方は大きく変わります。企業として、今ある情報との向き合い方や、発信のあり方をどう見直していくかが、今後の採用戦略において重要なカギを握っているのです。
削除できない悪評にどう向き合うか?現実的な3つの対応策
多くの経営者や人事責任者が最初に考えるのは、「なんとかして口コミを削除できないか?」ということかもしれません。しかし実際のところ、第三者が運営する口コミサイトにおいて投稿を削除することは非常に難しく、法的な根拠がない限り対応してもらえないのが現実です。
それでは、企業としてはただ見て見ぬふりをするしかないのでしょうか?
削除が難しいからこそ、“見られ方”をコントロールするための前向きな対策が必要になります。ここでは、現実的かつ実行可能な3つの対応策をご紹介します。
1. 検索結果にポジティブな情報を増やす
悪評の影響力を弱めるためには、検索結果に多様な情報を掲載し、否定的な投稿だけが目立たない環境をつくることが重要です。
たとえば、社内の働き方改革や新制度の導入、社員インタビュー記事などを、オウンドメディアや外部メディアで発信することで、検索結果に“企業の現在地”が反映されやすくなります。
ネガティブな声を消すことはできなくとも、それ以外の声を積み重ねていくことで、全体の印象をバランスの取れたものへと導くことが可能です。
2. 社員のリアルな声を可視化する
多くの企業で見落とされがちなのが、「現職社員の声を可視化していない」ことによる情報不足です。
実際に働いている社員の感想や、部署横断で行われている取り組み、社内イベントの様子など、企業文化を反映したリアルなコンテンツは、求職者にとって信頼感のある情報源になります。
こうした“日常の延長線”にある情報を、写真やインタビュー形式で発信することで、外部からの印象が大きく変わります。口コミの内容と実際の雰囲気が異なることが伝われば、ネガティブ情報の説得力も相対的に薄れていきます。
3. 外部サービスを活用した印象改善の取り組み
情報発信のリソースが不足している、広報部門がない、ノウハウがない──こうした課題を抱える中小企業にとって有効なのが、専門サービスの活用です。
たとえば、VOiCEのようなサービスでは、現職社員のポジティブな声を丁寧に収集・編集し、検索結果に反映されやすい形で発信する仕組みが整っています。
単なる口コミ対策とは異なり、企業の強みや魅力を言葉として可視化し、第三者の評価として自然にインターネット上に広がっていく導線が設計されているため、長期的な信頼構築にもつながります。
これらの取り組みは、実行を重ねることで、“企業の見え方”そのものを少しずつ改善していくことが可能になります。
特に、日々の業務の中で社員が感じている働きがいや組織への信頼といった“ポジティブな実態”を、社外にも適切な形で伝えられれば、企業イメージに対する外部の印象は大きく変わっていきます。
こうした日常の積み重ねを、どう伝え、どう価値ある形で社会と共有していくか──その視点が、これからの採用広報には求められています。
VOiCEによる印象再構築の仕組みとは
これまで述べてきたように、否定的な情報の発信を止めることはできません。一方で、企業が主体的に発信するポジティブな情報が外部に届き、信頼につながる形で可視化されていれば、全体の印象は大きく変わっていきます。
社員の実際の声や社内の雰囲気を知るための情報として、現職社員のリアルな声に特化した口コミサイト「VOiCE」があります。
VOiCEは、退職者ではなく“今実際に働いている社員”の声を中心に掲載することで、企業の現在の姿をより正確に伝えられる仕組みを持っています。
一般的な口コミサイトとは異なり、単なる評価の集積ではなく、採用候補者や社外ステークホルダーに対して信頼性のある企業像を届けることを目的としたプラットフォームです。
現職社員の声こそ、もっとも信頼される情報源
求職者が企業を評価する際、気になるのは「実際の職場環境はどうなのか?」という点です。制度や理念よりも、そこで働く人たちの“ナマの声”に信頼を寄せる傾向があります。
VOiCEは、現場で働く社員に対して「働きがいを感じた瞬間」「入社前と後のギャップ」「チームの雰囲気や上司との関係性」など、内側からの目線で言葉を引き出します。これらの声は、求人票やコーポレートサイトでは伝えきれない、“体温のある情報”として、企業の魅力を補完してくれます。
コンテンツとして検索結果に届く構造設計
VOiCEのもうひとつの特長は、収集した社員の声を検索エンジンに適切に評価されやすい形で公開する仕組みが整っていることです。
単に声を集めるだけでなく、それを「届ける」ための導線まで一体で構築されているため、求職者が企業名を検索したときに、それらの声が目に触れる機会が自然と増えていきます。
こうして企業側からの発信が検索結果に並ぶことで、過去の否定的な投稿だけが目立つ状況を防ぎ、より現在に近い印象や、企業の“今”を知ってもらえる環境が整います。
一過性ではなく、積み重ね型の印象づくり
重要なのは、VOiCEが一度きりの施策ではなく、継続的に社員の声を発信していく設計になっている点です。新入社員や中堅社員、管理職など、多様な視点の声が増えていくことで、企業の全体像が立体的に伝わるようになり、偏った情報に影響されにくい検索環境が形成されていきます。
このようにして、否定的な情報だけが先行していた検索結果に対して、企業の実態に基づいた前向きな印象をじっくりと築いていくことが可能になるのです。
いまや採用活動は「応募者に見つけてもらうこと」から、「調べられたときにどう見えるか」へとシフトしています。VOiCEはその後者にアプローチする仕組みとして、単なる採用支援ではなく、企業価値そのものを整えていくパートナーとして機能します。
第7章:まとめ ── 印象を整えることは、採用力を高める第一歩
ネガティブな口コミは、企業の実態とは異なる印象を生み出し、採用活動に大きな影響を及ぼします。特に退職者による一方的な声が検索上位に表示され続けると、応募が減る・内定辞退が起きるといった悪循環に陥りかねません。
こうした課題に対しては、削除を求めるよりも、企業として「何を、どう見せるか」を整えることが有効です。現職社員のリアルな声を発信し、検索上の印象を刷新する取り組みが、信頼の入り口を築いてくれます。
VOiCEのようなサービスを活用することで、社内に眠っているポジティブな実態を社会に届ける導線が整い、長期的な採用ブランディングの強化にもつながります。
“知られていない良さ”を見える形に──その一歩が、企業の未来を変えていきます。