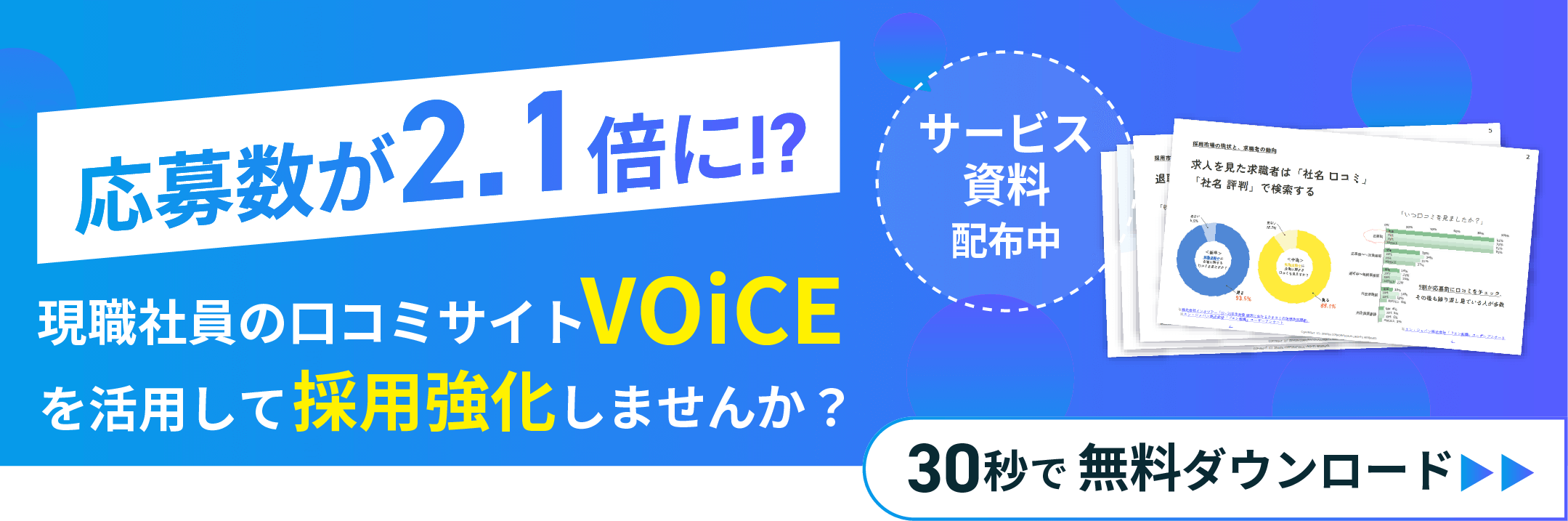その口コミ、放置していませんか?
採用に影響する“企業の評判”と向き合う方法
- 会社の評判
- 口コミ対策
- 採用強化
2025.08.04
はじめに:企業の「印象」は採用・取引に直結する時代へ
「最近、求人を出しても応募が少ない」「なぜか面接の辞退率が高い」「優秀な人材が最終面接で離脱してしまう」—こうした現象に心当たりのある人事責任者や経営者の方も多いのではないでしょうか。
実はこうした“採用の停滞”の背景には、企業の「見えないイメージ」が大きく関係しています。それは、いわゆる“企業口コミサイト”に掲載された情報。代表的な例でいえば、「転職会議」「OpenWork」「エンゲージ会社の評判」などが挙げられます。
これらのサイトには、現職・退職社員が匿名で企業の働き方や職場環境、経営陣への評価などを投稿できる仕組みが整っており、その透明性ゆえに、求職者の判断材料として広く活用されています。
一方で、企業側が意図しない形で「厳しい意見」や「過去のトラブル」が掲載されてしまうケースも珍しくありません。しかもそれらの内容は、Googleなどの検索結果に表示されやすく、時には会社名で検索しただけでネガティブな印象が目に飛び込んでくる状況も。
このような状況が続けば、単に採用の機会損失にとどまらず、取引先や新規顧客にまで影響が及ぶ可能性もあります。今や企業の「リアルな評判」が可視化され、誰でもアクセスできる時代。企業ブランディングとレピュテーションマネジメント(評判管理)は、もはや無関係ではいられません。
なぜ“評価サイトの声”が企業成長に影響するのか
企業の成長において、信頼は不可欠な資産です。そして近年、その“信頼の入口”が変化しています。
かつては「会社案内」や「IR情報」、あるいは代表者の言葉など、企業発信のオフィシャルな情報が主な信頼材料でした。しかし今、多くの人が真っ先に参考にするのは、「第三者が語る会社の実像」、つまり企業の評判や口コミなのです。
特に影響が顕著なのは、以下の2つのターゲット層です。
■求職者(中途・新卒ともに)
求職者の多くは、応募前の段階で企業の口コミをチェックしています。最近の調査では、約9割の求職者が口コミサイトを閲覧し、参考にしていると回答しています。

※エン・ジャパン株式会社「『エン転職』ユーザーアンケート」(https://partners.en-japan.com/special/190313)
職場環境、人間関係、残業や福利厚生、経営の透明性など、求人票だけでは見えない“リアルな声”が彼らの不安を和らげたり、逆に増幅させたりしているのです。
特にZ世代・ミレニアル世代の層にとって、ネット上の評判は「信用」の大部分を占めると言っても過言ではありません。ポジティブな評価が並ぶ企業はそれだけで選ばれやすく、逆にマイナスな情報が目立つ企業は、どれだけ待遇が良くても避けられる傾向にあります。
■ビジネス関係者(取引先・協業先)
企業間の取引においても、信頼性の判断材料として口コミサイトや検索結果が参照されるケースが増えています。
「この会社と取引しても大丈夫だろうか」「内部の混乱が取引に影響しないか」—こうした懸念を持たれれば、せっかくのビジネスチャンスも失われかねません。
実際に、営業担当が「御社、ちょっと評判が気になりますね…」と切り返された経験があるという経営者の声も、少なくありません。
このように、“ネット上の評価”は、採用と営業の両軸において企業の成長を左右する重大な要素となっているのです。
応募者・取引先が「企業の評判」をチェックする実態
インターネット検索が当たり前になった今、「会社のことを知りたい」と思った時にまず最初に行われる行動は、間違いなく“検索”です。求職者であれ、取引先であれ、その対象となる企業名をGoogleやYahoo!で検索し、目に入る情報をもとに判断を下すのが一般的な流れとなっています。
■実は見られている、検索結果の“リアルな声”
会社名を検索した際に表示される情報として、公式サイトや求人ページに加えて目立つのが、口コミサイトのページ等です。「転職会議」「OpenWork」「エンゲージ会社の評判」などのプラットフォームに投稿された社員の声が、検索結果の上位にランクインすることも珍しくありません。
しかも、それらのサイトの多くは「企業名+評判」「企業名+口コミ」といったキーワードでSEO対策が施されているため、会社名を入れて検索しただけで自然と目に触れてしまう構造になっています。
求職者の視点からすれば、そうした“実際に働いた人の声”は、企業選びの貴重な材料になりますし、逆にネガティブな情報が多く見られれば、「応募はやめておこう」という判断にもつながります。
■面接前の段階から企業の評判は見られている
求職者の多くは、企業に応募する前の段階から口コミサイトを確認しています。さらに、面接を受ける前にも、再度企業名を検索して評判をチェックすることが一般的になってきました。
特に20代〜30代の若手層は、企業のリアルな声を重視する傾向が強く、求人票や公式情報だけでは判断材料が不十分だと感じるケースも多くあります。
また、面接での印象が良かったとしても、後からネットでネガティブな評価を目にすれば、内定辞退や入社見送りの決断をすることもあります。つまり、採用の成否は面接時の対応だけでなく、ネット上の評判にも左右されているということです。

■取引先や業務提携先もチェックしている
実は、企業の評判を検索しているのは求職者だけではありません。新たな取引先候補として企業を調査する際にも、検索結果や口コミのチェックは欠かせないフローになっています。
経営層や購買部門は「会社名」で検索をかけ、公式サイトの情報と同時に、第三者がどのような評価をしているかを確認しています。
たとえば以下のような懸念が出ることがあります:
- 「経営層に対する不信感が多く書かれているが、信用して良いのか?」
- 「社員の定着率が悪そうだが、プロジェクトが途中で頓挫しないか?」
- 「トラブルが多いという情報があったが、うちも巻き込まれないか?」
企業間の信頼関係において、こうした“検索結果に映る印象”は無視できないリスクになり得ます。
ネガティブな声が与える採用活動へのインパクト
どれほど優れた採用戦略を練り、魅力的な求人票を作成しても、ネット上の評判が悪ければその努力は水泡に帰す可能性があります。
企業の採用活動において、「印象」という無形の要素が、応募数や内定承諾率、さらには従業員の定着率にまで深く関わっているのです。
■応募者数の減少とエントリー離脱
まず最初に直面するのが「応募者の減少」です。求人広告を見て一度は興味を持ったとしても、企業名を検索した際に目立つ位置にネガティブな口コミが表示されれば、応募を思いとどまる可能性は高まります。
たとえば、「パワハラが横行している」「残業が慢性的」「給与水準が低い」といった内容が上位に表示されていれば、「せっかく応募しても、時間の無駄になるのでは」と考えるのが自然です。求人票や採用ページにどれだけポジティブなメッセージを記載していても、検索結果に表示される“リアルな声”のインパクトの方が強くなってしまうのです。
また、口コミの影響は応募前だけにとどまりません。
実際にエントリーした後も、面接の前日や内定通知後に再度口コミを調べて「やっぱり辞退しよう」と判断されるケースが少なくありません。これは、採用コストがかかるだけでなく、面接官の稼働・スケジュール調整といった社内リソースも無駄になってしまうことを意味します。
■内定辞退や早期離職の増加
ネット上のネガティブな印象は、内定辞退率の上昇にも直結します。選考過程での好印象を維持できたとしても、最終的な判断段階で検索結果にネガティブな情報が並んでいれば、不安を感じて辞退という結論に至る求職者は少なくありません。
さらに問題なのは、そうした情報を見たうえで入社した場合も、「やっぱり悪い噂は本当だったのか」と不信感が芽生えやすく、結果として早期離職につながるリスクがある点です。
これは企業にとって、単なる「採用ミス」では済まされません。
離職にかかった時間的・金銭的コストだけでなく、職場のモチベーション低下や、社内の採用担当者へのプレッシャーにもつながってしまいます。
■社内にも波及する負の連鎖
「採用できない」「辞退される」「定着しない」という現象が続くと、社内にも少しずつ影響が及びます。現場の社員に過度な業務が集中したり、採用部門が焦ってミスマッチ採用を重ねてしまうことで、職場の雰囲気が悪化していくケースもあります。
こうした状況が続けば、再び社員の不満が高まり、結果としてまた口コミサイトにネガティブな評価が投稿されてしまうという“負のスパイラル”に陥る危険性もあります。
「悪い評判」が可視化される時代の対処法とは
インターネットの普及とともに、企業の評判はかつてないほど透明化されました。
今や一個人の口コミが、数千人、数万人の目に触れる時代。しかもそれは半永久的に検索エンジンに残り続けます。
こうした中で「評価を気にしすぎるのもどうか」と楽観視するのは危険です。一方で、過剰に反応し、評判の“削除”や“隠蔽”に走るのも、時代の流れに逆行する姿勢と見なされる可能性があります。では、企業としてどう向き合えばよいのでしょうか。
■“消す”ではなく“向き合う”という発想
まず前提として、企業にとって都合の悪い評判を「完全に消す」ことは、現実的には非常に困難です。口コミサイトは法的な観点からも“個人の主観的感想”として保護されているため、名誉毀損や虚偽でない限り、削除には高いハードルがあります。
つまり、「どうすれば削除できるか」を考えるよりも、「どう向き合い、印象を転換するか」という視点に立つことが、これからの評判管理における現実的なアプローチです。
■口コミは“組織の鏡”。まずは社内に目を向ける
ネガティブな投稿の中には、たとえ言い方が過激だったとしても、組織の課題を示唆しているケースがあります。
たとえば、
- 評価制度が不明確
- 経営層との距離がある
- 労働時間や残業に対する配慮が不足している
といった指摘は、企業にとって改善のヒントとなる“現場の声”でもあります。
口コミサイトを「攻撃」ととらえるのではなく、「内部改善のための材料」として受け止める姿勢が、長期的には企業価値の向上につながります。
もちろん、あまりに一方的で事実と異なる情報が書かれている場合は、運営元への申し立ても必要ですが、それと並行して「ポジティブな声を育てていく」ことが、健全な評判形成には不可欠です。
■“自然発生の良い声”を可視化していく
実際、企業の中にはポジティブな側面も数多くあるはずです。たとえば、
- 上司との距離が近く、相談しやすい風土
- 福利厚生が充実している
- 自由度が高く、若手にもチャンスがある
こうした前向きな体験は、現場の社員が自然に感じていることでもあります。ただし、それを“社外へ伝える仕組み”がなければ、永遠に表に出てくることはありません。
ネガティブな投稿は、満足していない人が強い感情で書くため可視化されやすく、逆にポジティブな感情は「わざわざ書かない」ために埋もれてしまいがちです。この構造が、ネット上の評判を「ネガティブに偏らせている」大きな原因でもあります。
だからこそ、良い声を社外に届けるための“能動的な仕組み”が必要なのです。
「削除」ではなく「上書き」という新しいアプローチ
企業にとって不本意な内容がネット上に掲載されたとき、まず最初に思い浮かぶのは「削除できないか」という対処法かもしれません。
しかし、第5章でも触れたように、現代においてネット上の口コミを完全に消去することは、法的にも技術的にも非常に難しく、リスクを伴うケースもあります。
加えて、“削除依頼”という行為そのものが、ネットユーザーから「隠蔽しようとしている」と受け取られ、かえって印象を悪化させる可能性すらあります。
そこで今、企業の間で注目されているのが「削除ではなく、上書きする」という新しい考え方です。
■「上書き」とは、印象の再構築を意味する
「上書き」とは、ネガティブな情報を無理に消し去るのではなく、それ以上に信頼性の高いポジティブな情報を発信・可視化することで、検索結果や企業イメージを“塗り替えていく”戦略です。
これは単なる広報活動ではなく、企業のリアルな魅力を、現場の声を通して社会に伝えていくという極めて戦略的なブランディング施策でもあります。
たとえば、「やりがいがない」という口コミがあった場合でも、現職社員が語る“実際のやりがい”が別の形で検索結果に表示されていれば、求職者は一方的な印象ではなく、複数の視点から判断することができます。
つまり、「マイナスをゼロに戻す」ことを目指すのではなく、「プラスを加えて全体のバランスを整える」という姿勢が、“上書き”という発想の本質なのです。
■重要なのは“誰が語るか”
このアプローチを成功させるうえで鍵を握るのが、「誰が語るか」という点です。
企業が自ら発信する情報(=公式メッセージ)は、どうしても“広告的”に見られがちです。一方、第三者である社員が「自分の言葉」で語った情報には、圧倒的な信頼性があります。
たとえば、
- 若手社員が語る「やりがいを感じた瞬間」
- 働くママが語る「制度の実態と支援の手厚さ」
- エンジニアが語る「開発現場の裁量と自由度」
こうした声がネット上に“整理された情報”として表示されていれば、企業に対する印象は大きく変わります。
検索ユーザーは、ネガティブな情報とポジティブな情報の「バランス」を見ています。一方的に“良いこと”だけを並べても響きませんが、現場のリアルな声があれば、企業の多面性が伝わり、信頼されやすくなるのです。
■“上書き”を意図的に設計するという視点
この「上書き」は、偶然に起こるものではありません。社内にあるポジティブな声を意図的に集め、正しく発信し、検索結果に表示される導線を設計することが求められます。
つまり、企業ブランディングや採用広報の延長線上にあるべき、“検索戦略を含んだ広報活動”という位置付けです。
このような「評判の設計」は、今後の採用活動や事業成長において欠かせない施策となるでしょう。
VOiCEを活用したポジティブな印象の発信とは
前章でご紹介した「削除ではなく、上書きする」というレピュテーション管理の新しい考え方。
それを実現する手段のひとつとして、注目されているのが「VOiCE」というサービスです。
これは、企業に対する印象を一方的に“消そう”とするのではなく、現場で働く社員の実感に基づいたポジティブな声を、Web上で“可視化”することで企業イメージをバランスよく伝えていく仕組みです。
■VOiCEとは何か?
VOiCEは、現職社員のリアルな声に特化した口コミサイトです。実際にその企業で働いている社員が、仕事のやりがいや職場環境、制度の活用状況などを、率直な視点で投稿できるプラットフォームとなっています。
一般的な口コミサイトでは、現職者・退職者を問わず、誰でも自由に投稿できるため、時に感情的・一方的な内容が掲載されることもありますが、VOiCEは“現職社員の実体験”に絞ることで、より企業の今の姿を伝えることに重きを置いています。
また、採用希望者や転職検討者にとっても、実際に働いている人の「生の声」を参照することで、より現実的な職場像をつかみやすくなるというメリットがあります。
■VOiCEの強みは、ただ口コミを掲載するだけではありません。
VOiCEの特徴は、単に社員の声を集めて掲載するだけにとどまりません。
企業名で検索された際に、VOiCE上のポジティブな口コミが検索結果に表示される設計となっており、企業名+評判 や 企業名+口コミ などの検索において、ネガティブな口コミ情報に埋もれず、もう一つの視点を持たせる役割を果たします。
「この会社に不安はあるけれど、実際に働いている社員はどう感じているのか?」という求職者の視点に対し、VOiCEは現職社員の前向きな視点や肯定的な体験を届けることで、企業に対する印象をバランスのとれたものに整えていきます。
これは、従来の一方的な情報に依存する口コミサイトとは異なり、“ポジティブな側面にも目を向けられる環境”をネット上に提供しているといえるでしょう。
■VOiCEの活用で得られる3つの効果
- 採用活動への好影響
求職者にとって、前向きな社員の声が目に入ることで、不安が軽減され、応募・面接に前向きになりやすくなります。 - ミスマッチや早期離職の予防
現職社員の等身大の声を通して実際の職場環境を理解した上で入社するため、入社後のギャップを防ぎやすくなります。 - 外部印象のバランス調整
企業名で検索された際に、ネガティブな評価と並んで、実際の現職者の肯定的な声も表示されることで、企業イメージが一面的に偏らず、より中立的な評価が可能になります。
まとめ:会社の未来を守るために今できること
これまでの章を通じて、企業のネット上の評判、特に口コミサイトにおける評価が、採用活動や取引関係に与える影響について詳しく見てきました。
口コミが採用の可否を左右し、企業成長のスピードにブレーキをかける時代において、経営層や人事責任者が“評判”という無形資産にどう向き合うかは、もはや事業戦略の一環といえるでしょう。
ネガティブな投稿は簡単には消せません。だからこそ、「印象を上書きする」という新しい選択肢を、今こそ本気で検討すべきタイミングなのです。
■“無関心”こそ最大のリスク
実際に「うちは口コミを気にするような会社ではない」と考えている企業ほど、応募数の減少や辞退率の増加、営業先での違和感といった“目に見えない機会損失”が起こっている可能性があります。
ネット上の情報は、企業が意図しなくても一人歩きします。そしてそれは、「未来の社員」や「未来の取引先」の意思決定に、知らず知らずのうちに影響を与えてしまいます。
採用がうまくいかない、営業先の反応が鈍い、応募者が途中で離脱する——そんな兆候を感じているなら、それは「企業の印象」に何らかの課題が生じているサインかもしれません。
■まずは「現職社員の声」を整えることから始める
評判は、外から操作するものではなく、内側から整えていくものです。
その第一歩として有効なのが、「今、実際に働いている社員の声」を言語化し、社会に伝えるという取り組みです。
これは単にイメージアップを図るということではなく、採用のミスマッチを防ぎ、エンゲージメントを高め、企業と求職者双方にとって納得感のある選択を増やすという、本質的な価値を生み出すアプローチです。
■VOiCEはその一歩を後押しする仕組み
現職社員の声を検索結果で可視化する仕組みとして、VOiCEはこれまで多くの企業の「印象転換」に貢献してきました。
匿名性を担保しつつも、現場で働く人のリアルな視点を社会に届けるVOiCEの取り組みは、いわば“ネット上における社風の翻訳機”ともいえる存在です。
- 「削除することができない情報をどう扱うか」
- 「口コミの不安をどう払拭し、安心につなげるか」
- 「誤解や偏見ではなく、実態を知ってもらうにはどうすべきか」
こうした課題に向き合う企業にとって、VOiCEは実践的かつ本質的な選択肢のひとつになるはずです。
■「印象のマネジメント」は経営戦略の一部へ
今後、レピュテーションマネジメント(評判管理)は「広報部門」だけの役割ではなく、「経営戦略」の中に組み込まれるべき領域となっていきます。
それは、採用市場での競争力確保のためだけでなく、企業の信頼性・継続性・市場価値を守るためにも必要不可欠な考え方です。
今からでも遅くはありません。まずは、自社が検索されたときにどんな情報が表示されているのか、現職社員の声はどう伝わっているのかを確認し、小さな改善から着手してみてください。