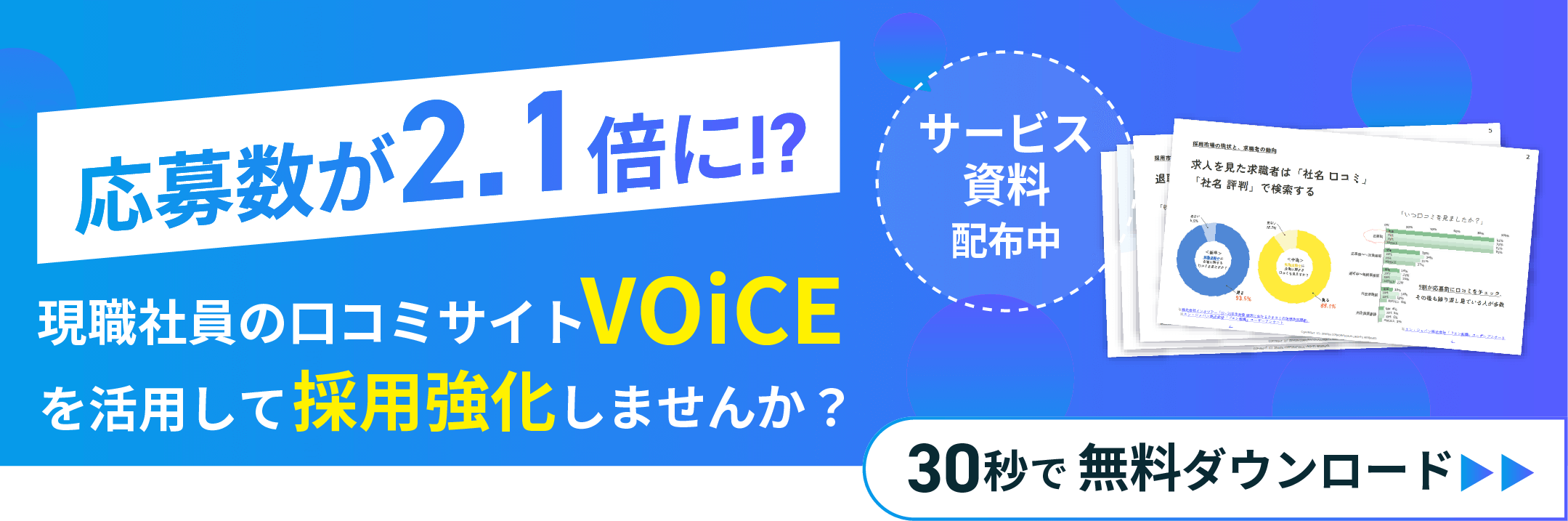「会社の評判が悪い」と気づいたとき、あなたはどう向き合うか
- 会社の評判
- 口コミ対策
- 採用ブランディング
2025.07.23
ある日、何気なく自社名を検索してみたときに目に入る言葉。
「〇〇社 ブラック」
「〇〇株式会社 やばい」
このような検索結果を目にして、驚いた経験がある方もいるでしょう。
近年「会社の口コミが悪い」「評判が低い」といった悩みを抱える企業は少なくありません。
採用活動においては、口コミサイトやSNS上の評価が応募数や内定承諾率に直結する時代です。
「なぜここまで会社のイメージが悪化したのか」「応募が減ったのは評判のせいではないか」と不安や疑問を感じている経営者や人事担当者も多いでしょう。
インターネットの普及によって、企業の内情は誰でも簡単に閲覧・共有できるようになりました。
一方で、事実よりも誇張された情報や、個人の主観的な意見が拡散し、企業の印象を大きく左右するケースも少なくありません。
では、なぜ会社の評判が悪くなるのか。
そして、その状況にどう向き合えばよいのか。
本記事では「会社の口コミが悪い」と気づいたときに見直すべき原因や背景を整理します。
さらに、企業の評判を改善へと導くための考え方と具体的な取り組みも解説します。
会社の評判や口コミはどう決まる?現代の「評価構造」を理解する
かつては、会社の評判を決めるのは企業の発信する情報──例えば広報部が作成するプレスリリースや、Webサイト上のメッセージでした。
しかし現在、企業の「評価」はそれだけでは決まりません。
実際に現場で働く社員や元社員、顧客の声が、SNSや口コミサイトを通じて拡散され、社会全体に“企業像”として共有されるようになっています。
つまり「会社の口コミが悪い」「評判が低い」といわれる背景には、こうした情報の流通構造の変化が大きく関係しているといえるのです。
「公式情報」よりも「リアルな声」が会社の評判に影響する時代
求職者や取引先が企業を調べるとき、最初に見るのはもはや会社案内やプレスリリースではなくなっている傾向にあります。
多くの人が「口コミサイト」「SNS」「Googleマップ」「X(旧Twitter)」などで、リアルな体験談を探します。
特に転職を検討する層にとって「現場のリアルな声」こそが信頼できる情報源になり得ます。
たとえ一部の口コミであっても、ネガティブな内容は印象として残りやすく、企業全体のイメージを左右してしまいます。
「会社の評判が悪い」といわれる背景にある情報の広がり方
インターネット上の情報は、一度投稿されると削除や訂正が難しく、長期間にわたって検索結果に残ります。
また、SNSでは個人の体験が拡散されやすく、企業に対する感情的な意見も短時間で広まる傾向があります。
このように、かつては企業内部で完結していた「評価形成」が、いまでは社外の多様な声によってつくられているのです。
だからこそ、企業に求められるのは「一方的な情報発信」ではなく、社員・顧客・求職者など、さまざまな立場の声をどう受け止め、どう改善に活かすかという姿勢です

会社の口コミや評判が悪くなる主な原因とは
「なぜ自社の評判が下がってしまったのか」──
そう感じたとき、目に見える課題だけで判断してしまうことがあるでしょう。
しかし実際には、評判を左右する要因はもっと複雑で、日々の企業活動や社内文化の中に潜んでいる場合もあります。
ここでは「会社の口コミが悪くなる」背景にある、いくつかの見えにくい原因を整理してみましょう。
時代の変化に合わない体制や働き方
変化の早い現代では、社員が「成長できる」「挑戦できる」と感じられる環境づくりが重視されます。
一方で、旧来の組織構造や意思決定の仕組みが残っていると「新しい取り組みがしにくい」「意見が通りにくい」と感じる社員が出てくることもあります。
そのような印象が社外に伝わると「古い体質の会社」「柔軟性に欠ける企業」といったイメージを持たれてしまう場合があります。
こうした認識の積み重ねが、口コミや評判の低下につながることもあるのです。
情報発信の少なさが招く誤解
「誠実に仕事をしていれば、きっと理解されるはず」
そうした姿勢はとても大切ですが、情報があふれる今の時代では、“伝えないこと”が思わぬ誤解を生むことも。
例えば、会社の取り組みや働く環境を外部に発信していないと、他者による口コミや断片的な情報だけが先に広まってしまうことがあります。
結果として「実際は努力しているのに、その姿が見えない」という状況が生まれます。
そして、会社の印象が実態よりも低く評価されてしまう場合もあるのです。
退職者の声が一方的に残る構造
口コミサイトの多くは、在職中よりも退職後に投稿されることが多い傾向が見られます。
そこには率直な意見や建設的な提案もありますが、時には退職時の感情が反映され、実際よりも厳しい印象のコメントが目立つこともあります。
そのような投稿が検索結果の上位に表示されると「会社の口コミが悪い」「評判が低い」と受け取られる原因になりかねません。
特に、企業側が発信をしていない場合は、そうした一部の声が第一の情報源になってしまうこともあります。
悪い評判や口コミを放置するリスクと影響
「会社の口コミが悪い」と気づいても「すぐに対処するのは大げさかもしれない」「そのうち落ち着くだろう」と様子を見てしまうケースは少なくありません。
しかし、インターネット上の情報は一度拡散されると長く残りやすく、対応を後回しにすることで、結果的に企業の印象に大きな影響を及ぼすおそれがあります。
ここでは、口コミを放置した場合に起こり得る主なリスクを整理してみましょう。
採用活動への影響──応募数や内定承諾率の低下
近年、求職者の多くは応募前に企業の口コミを確認している傾向が強まっています。
口コミサイトやSNSで「会社の評判が悪い」といった情報を目にすると、応募をためらったり、選考途中で辞退したりするきっかけになることがあります。
たとえ事実と異なる内容であっても、ネット上の印象は応募者の意思決定に大きく影響するため、採用の成果に直接関係してくる場合もあるのです。
社内のモチベーションや定着率への影響
口コミは社外だけでなく、社内の雰囲気にも影響を及ぼすおそれがあります。
自分の働く会社が「評判が悪い」といわれている状況は、社員にとって少なからずストレスや不安につながりかねません。
「自分たちの努力が正しく伝わっていない」と感じることで、働く意欲や誇りが損なわれることもあるでしょう。
その結果、離職やエンゲージメント低下など、組織面での課題が生じる可能性もあります。
顧客や取引先との信頼関係への影響
口コミサイトは求職者だけでなく、取引先や顧客も参考にすることがあります。
特に新規の商談やパートナーシップの検討段階では、「どのような会社なのか」を検索して確認することが一般的です。
その際に「評判が悪い」「対応に問題がある」といった口コミが目立つと、取引や契約を慎重に検討される場合があります。
こうした影響は直接的な売上減少にはつながらない場合でも、信頼構築の機会を逃す要因になり得ます。
悪い印象が固定化しやすい検索環境
ネット上の情報は、時間が経っても残り続ける傾向があります。
特に検索エンジンの結果にネガティブな内容が表示され続けると、新しい取り組みや改善を行っても、過去の印象が先行してしまうことがあります。
「昔の情報が今も残っている」だけで、企業イメージが更新されにくくなるのは大きなリスクといえるでしょう。
そのため、口コミや評判を“放置せず、定期的に確認する体制”を整えることが重要になります。
悪い口コミを見つけたときの対応方法
自社に関するネガティブな口コミを見つけた際、感情的に反応してしまうのは自然なことです。
しかし、対応の仕方によっては印象をさらに悪化させてしまうこともあります。
重要なのは「冷静に状況を整理し、誠実に向き合う姿勢」を持つことです。
(1)内容を冷静に確認する
まずは、書かれている内容が事実に基づいているのか、または誤解や一部の経験に偏ったものなのかを慎重に見極めましょう。
口コミをすぐに否定するのではなく「なぜそう感じられたのか」という視点を持つことで、社内の課題発見につながることもあります。
(2)社内で共有し会社の評判改善への糸口を探る
個人の意見として受け流すのではなく、関係部署と共有し、改善につなげられる点がないかを検討しましょう。
例えば「コミュニケーション不足」や「評価制度への不満」といった内容は、働きやすさ向上のヒントになることもあります。
(3)事実と異なる情報には丁寧に対応し会社の評判を守る
明らかに誤った情報が掲載されている場合は、口コミサイトの運営元に削除依頼を行うことも検討できます。
ただし、その際も感情的な表現や強い主張は避け、事実に基づいた冷静な説明を心がけることが大切です。
(4)ポジティブな情報発信でバランスを取る
悪い口コミだけが目立ってしまう場合は、社内の取り組みや社員の声、社会への貢献活動などを積極的に発信することで、企業の多面的な姿を伝えられます。
一方的な反論ではなく「実際の姿を知ってもらうため」の前向きな情報発信が、信頼回復につながる可能性があります。
会社の良い評判を築くために企業ができること
悪い口コミに気づき、適切に対応した後は、企業としての信頼を回復し、持続的に良い評判を築くことが大切です。
その鍵となるのは、現場で働く社員の声です。
求職者の多くは、企業から発信される情報よりも、実際に働いている人自身の体験や意見を信頼しやすい傾向にあります。
ポイントは、ただ良いところだけを強調するのではなく、等身大の声を伝えることです。
社員が感じている課題や改善の取り組みも含めて率直に共有することで、求職者や顧客からの信頼を取り戻すことにつながります。
具体的には、以下のような取り組みが有効です。
- 社員インタビューや座談会の実施
- 社内での改善活動やチャレンジ事例を紹介
- 社員のリアルな声を記事やSNSで発信
こうした施策を通じて、会社の姿を正しく伝えることが、口コミや評判の改善につながるでしょう。
VOiCEという選択肢 ― 社員の声を評判改善や採用に活かす
VOiCEは、現職社員の声を中心に企業の姿を可視化する口コミメディアです。
従来の口コミサイトとは異なり、企業と社員が協力して作り上げる、透明性のある情報共有の場として利用できます。
社員の声を通じて伝えられる情報
VOiCEを活用することで、社員の声から企業のさまざまな側面を伝えられます。
- 社風や働き方の特徴
- 成長環境やキャリア支援の取り組み
- マネジメントの姿勢
- 最近実施している改善活動や工夫
これにより、求職者や取引先などに、企業の“今の姿”を理解してもらいやすくなります。
社内改善のヒントとしても活用可能
VOiCEに掲載された社員の声は、社内の改善活動にも役立てられます。
社員の率直な意見をフィードバックとして受け取り、組織の課題を把握することで、改善のヒントにできます。
会社の評判改善だけでなく成長につなげる仕組み
単に「評判を伝える」場としてだけでなく、社員の声を採用活動や組織改善に活かすことで、企業の成長に役立つ可能性があります。
こうした双方向の活用が、VOiCEの特徴的な価値です。
まとめ:会社の口コミや評判が悪い状況を改善する第一歩
会社の口コミが悪い、評判が低いと感じたとき、多くの経営者や人事担当者は、まず防衛的な対応を考えがちです。
しかし、ただ状況を避けたり隠したりするだけでは、問題の解決にはつながりません。
大切なのは、ありのままの企業の姿を伝えること、そして社員の声に耳を傾けることです。
表面的な評価や一部のネガティブな口コミだけに目を奪われず、根本的な課題や改善の余地を把握することで、企業と社員、そして求職者との関係性を見直すきっかけになります。
口コミや評判の改善は、企業の成長のスタート地点でもあります。
社内のリアルな声を活かしながら、透明性のある情報発信を意識することで、信頼構築につながる第一歩を踏み出せます。
例えば、VOiCEのように社員の声を整理して可視化する仕組みを活用すれば、ネガティブな印象が広がる前に、自社の現状を正しく伝える取り組みを検討することができます。
会社の評価が低いと感じたときこそ、自社を見つめ直し、改善と信頼構築に向けた行動を始めるチャンスです。