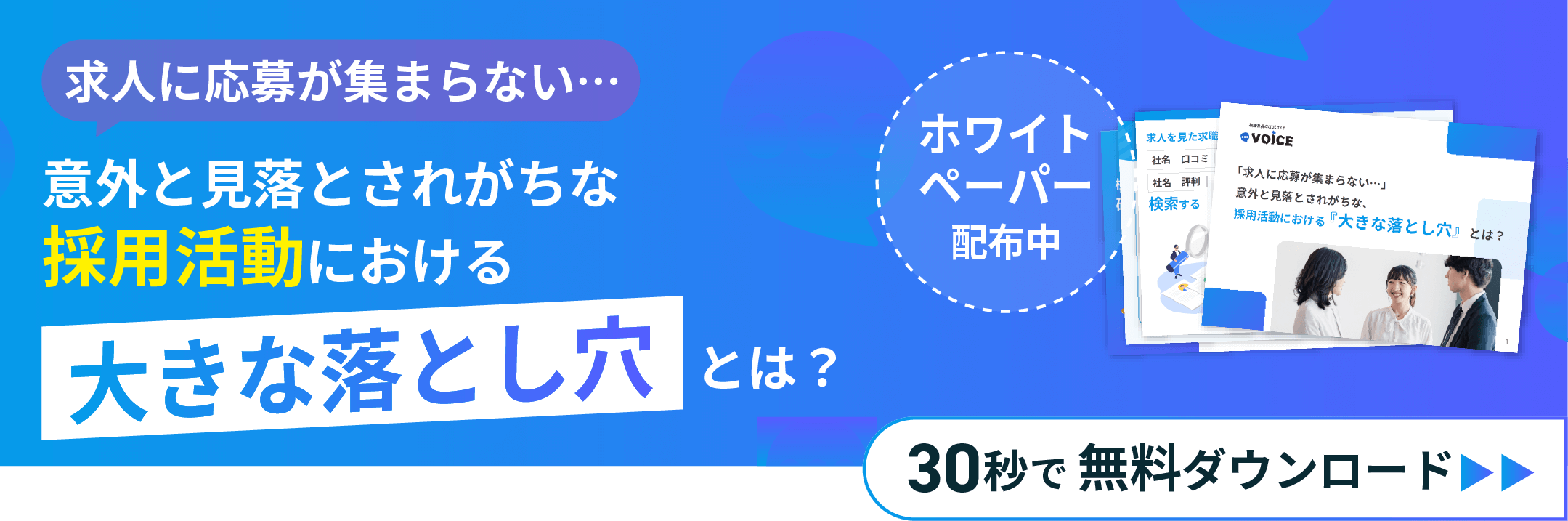人手不足だけじゃない?ドライバー採用が難しい理由と企業が今できる対策とは
- 採用強化
- 採用活動
- 採用課題
2025.10.16
物流や運送業界では、長年にわたり「人材確保の難しさ」が課題となっています。
特にトラックドライバーの採用は、応募が思うように集まらないケースや、面接後に辞退されるケースも。
背景には、人手不足という単純な理由だけでなく、働き方や待遇に対する考え方の変化、業界イメージ、若年層の就業意識など複数の要因が関係していると考えられます。
この記事では、ドライバー採用が難しい理由を整理し、企業が取り組むべき対策や改善のヒントをご紹介。
求職者に選ばれる企業になるために、どのような工夫が必要か。
これからの採用戦略を考える上で参考になる情報をまとめました。
第1章:ドライバー採用が難しい5つの理由
1. 高齢化と女性進出の少なさ
ドライバー職は、従業員の平均年齢が他の業種と比べて高く、高齢化が進んでいる傾向が見られます。
また、女性の就業率も低い傾向にあるのです。
出典:厚生労働省「統計からみるトラック運転者の仕事 トラック運転者はどんな人?」(https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/work)
これは長距離運行や夜間勤務が多いことなど、働き方の制約があることが背景のひとつにあると考えられます。
採用力向上につなげるためには、年齢や性別に関係なく働きやすい環境づくりを検討するのが大切といえるでしょう。
2. 働き方に対する価値観の変化
求職者の働き方に対する価値観が、大きく変化しつつあるのも理由のひとつといえます。
かつては「収入の安定」を第一に考える人が多かった一方、近年では「自分の時間」や「家族との時間」を優先する人が増えている傾向にあります。
そのため、求職者は勤務条件や休日日数、残業時間などに注目しているのです。
長距離輸送や深夜勤務が多いドライバー職は、生活リズムに工夫が必要な場合も。
求職者の働き方に対する価値観の変化により早く対応することで、応募者に選ばれやすくなる可能性も高まるでしょう。
3. 賃金や待遇への期待とギャップ
ドライバー職は運転技術に加えて、荷物の積み下ろしや時間厳守など多くの責任を伴います。
ところが、求職者の目から見ると仕事内容に対しての給与が十分であると感じられない場合も。
特に求人票では「給与の総額」や「各種手当」の内容が分かりにくく、待遇が低く見られてしまうことがあります。
また、他業界と比較されたときに「同じ体力仕事なら建設や製造の方が条件が良い」と判断されるケースも。
つまり、給与水準そのものだけでなく、情報の伝え方によって応募数が左右されるのです。
待遇に関する「誤解や不安」を軽減できれば、採用成功につながる可能性があります。
4. 業界イメージの課題
物流業界に対して「長時間労働」「過酷な仕事」というイメージが残っている求職者もいるでしょう。
実際には、働き方改革やデジタル化の推進によって改善が進んでいる企業もありますが、その変化を外部に対して伝えきれていないケースも。
例えば、車両設備の近代化やシフト制の導入などで負担軽減に取り組む企業も多いものの、求職者にはその情報が十分に伝わっていないのが現状です。
その結果、昔のイメージのまま応募を見送られるケースもあるのです。
また、SNSや口コミサイトの影響力が強まったことで、一部のネガティブな情報が拡散しやすい環境もあります。
「どの企業も同じ」と思われてしまう前に、自社の取り組みを正しく発信することが重要です。
5. 採用競争の激化
人材不足は物流業界だけの問題ではありません。
建設業や製造業、さらには倉庫業務や配送サービスでも、ドライバー資格を持つ人材が求められています。
そのため、同じ人材を巡って複数の業界が競合しているのです。
求人票の条件が似通っている場合、求職者は「より待遇が良い」「自分の希望に合う」と感じた企業を選びます。
自社の魅力を十分に伝えられないと、求職者が比較検討する際に選ばれにくくなることも。
さらに、ドライバー採用は地域性の影響も大きいのが特徴です。
勤務地の近さや通勤手段も応募意欲に直結するため、条件が少し合わないだけで候補から外れてしまうこともあります。
採用競争の中で「選ばれる理由」を示せるかどうかが、大きな分かれ目になっているといえるでしょう。

第2章:求職者は「リアルな声」を求めている
求人票だけでは伝わらない現場の情報
多くの企業は、求人媒体や自社サイトで勤務条件や給与、福利厚生などをアピールしています。
しかし、求人票に記載されるのはあくまで基本的な情報です。
「実際に働いたときの雰囲気」や「職場の人間関係」「休憩の取りやすさ」など、日常のリアルな部分までは伝わりにくいのが現実。
応募を検討している人ほど「リアルな声」に関心を持っています。
情報が不足していると、安心して応募に踏み切れないケースも多いのです。
SNSや口コミサイトで広がる社員のリアルな体験談
近年はSNSや口コミサイトの普及により、企業の評判が簡単に検索できるようになりました。
求職者は公式サイトよりも、現場で働く人の声を参考にする傾向があります。
特にドライバー採用においては「現職社員のリアルな体験談」が応募の決め手になることも。
給与額や休日数は同じでも「上司との関係が良い」「休みが取りやすい」などの声は、求職者にとって具体的で安心感のある情報といえます。
一方で、ネガティブな情報が目立つと、応募そのものを控えるケースもあります。
つまり、公式サイトや求人ページ以外でどのような情報を発信するかが、採用成功を大きく左右しているのです。
社員の声で「働きやすさ」を証明する重要性
企業が「働きやすい環境です」と発信しても、それだけでは信用してもらいにくいことも。
求職者が本当に知りたいのは「現場で働く人がどう感じているか」です。
例えば次のような情報は、求人票以上に応募意欲を高めることがあります。
- 入社の決め手になったポイント
- 実際の1日の流れや休憩の取り方
- 社内の雰囲気や上司・同僚との関係性
- 仕事を通じて感じるやりがい
これらは、求職者が「自分が働いた場合のイメージ」を具体的に描くのに役立ちます。
特にドライバー職のように内容がイメージしにくい仕事では、社員の声が大きな影響を持つのです。
比較される採用市場で選ばれる企業になるには
採用市場が厳しい中で、求職者は複数の企業を比較しながら応募を検討します。
給与や福利厚生が似ている場合、最後の決め手になるのは「安心感」や「信頼感」です。
「この会社なら長く働けそうだ」と思えるかどうかは、数字ではなく声や体験談から生まれます。
リアルな声を通じて、自社の魅力を具体的に伝えることが、採用競争を勝ち抜くための重要な要素なのです。
第3章:ドライバー採用力を高めるための具体策
1. 求人情報の伝え方を工夫して差別化する
ドライバー採用が難しいと感じる企業の多くは、求人票が他社と似通っている傾向があります。
給与や勤務時間、休日数といった基本条件はもちろん大切ですが、それだけでは応募者に選ばれにくいのが実情です。
例えば「社内の雰囲気」「社員同士のコミュニケーションの取りやすさ」「新しい車両や設備の導入」といった情報は、求職者にとって魅力的なポイントになり得ます。
求人媒体のフォーマットに沿うだけでなく、自社サイトや採用ページで写真や社員インタビューを交えて発信することで、差別化が可能になるでしょう。
2. 働き方改善への取り組みを発信する
ドライバー職は「長時間労働」というイメージがまだ残っていることも。
このイメージを改善するには、実際にどのような改善策を行っているかを伝えることが重要です。
例えば以下のような施策があります。
- 勤務シフトの見直しや短時間勤務制度の導入
- デジタコや運行管理システムを活用した効率化
- 積み下ろしの省力化やサポート体制の整備
- 有給休暇取得率や残業時間の削減実績を公開
こうした具体的な取り組みは、数字や実績とともに伝えることで説得力が増します。
「改善の努力をしている企業」という姿勢そのものが、求職者に安心感を与えるのです。
3. 採用チャネルを広げて若年層へアプローチ
従来の求人広告やハローワークだけでは、ターゲット層に十分にリーチできない場合があります。
SNSや動画配信を活用して会社の雰囲気を発信したり、転職イベントに参加して直接アピールしたりなど、複数の接点を持つことが効果的です。
特に若年層にアプローチするには、スマートフォンで情報収集する人が多いことを意識した採用活動が必要です。
短い動画で仕事内容を紹介したり、社員の一日をストーリー仕立てで伝えたりといった工夫は、他社との差別化につながります。
4. 応募から入社までのプロセスをスムーズにする
せっかく応募があっても、面接までに時間がかかると辞退につながることがあります。
応募から選考までのフローを簡潔にし、スピーディーに対応することで、応募者のモチベーションを維持できる可能性があります。
また、面接時には給与や勤務条件だけでなく「働きやすさ」や「社内の雰囲気」も丁寧に説明することが大切です。
入社前にギャップを減らすことで、早期離職を防ぎ、定着率向上の助けになります。
5. 社員の声を活用して安心感と信頼感を伝える
前章で触れたように、求職者はリアルな情報を求めています。
そのため、現場で働く社員のインタビューや体験談を発信することは、有効といえるでしょう。
「なぜこの会社を選んだのか」「実際に働いてみて感じたこと」などの生の声は、求人票以上に説得力があります。
さらに、入社後の成長エピソードやキャリアの歩みを紹介することで、長期的に働くイメージを持ってもらうことも可能です。
社員の声をオープンに発信する姿勢そのものが、企業の透明性や信頼性を高めます。
第4章:VOiCEの活用でドライバー採用力を向上
VOiCEとは?社員のリアルな声を届ける口コミサイト
VOiCEは、現職で働く社員による「リアルな声や評判」を集めた口コミサイトです。
従業員自身の体験談や感想が掲載されるため、企業が一方的に発信する情報とは異なり、求職者にとって参考になるポイントが多く含まれています。
「職場の雰囲気はどうか」「働きやすさは本当か」といった疑問に対して、実際の声を通じて理解を深められるのが特徴です。
求職者にとってのVOiCE活用メリット
求職者は求人票や公式サイトだけでは分からない情報を重視しています。
VOiCEでは、実際に働く人の意見を確認できるため、応募前に参考情報として安心感を持つ手助けになります。
例えば、以下のような点が参考になります。
- 入社を決めたきっかけ
- 一日の仕事の流れや休憩の取りやすさ
- 社内の雰囲気や人間関係の実際
- やりがいを感じる瞬間や改善してほしい点
これらの情報は、求職者が「自分が働いたらどうなるか」を具体的に想像する手助けとなります。
企業にとってのVOiCE活用メリット
企業にとっても、VOiCEは採用活動を補助する手段のひとつになります。
自社の魅力を社員の声を通して伝えることで、求人票では表現しきれない情報を求職者に届けられます。
また、社員が実際に感じていることを外部に発信することで、透明性のある企業として信頼感を高める効果も期待できます。
「応募数を増やしたい」「定着率を上げたい」と考える企業にとって、社員の声を活用することは有効な選択肢のひとつです。
他の採用施策との相乗効果で応募者を増やす
VOiCEは単独で活用するだけでなく、求人広告や自社採用サイトと組み合わせることで効果を高められます。
求人票で条件を提示し、VOiCEで社員のリアルな声を補完することで、応募者が安心してエントリーしやすくなります。
求職者は「条件」だけでなく「雰囲気やリアルな体験」を重視するため、両方をバランスよく伝えることが重要です。
その点でVOiCEは、採用活動を補完する存在として役立ちます。
ドライバー採用が難しい理由と対策のまとめ
ドライバー採用の難しさには、労働人口の減少や高齢化、働き方に対する価値観の変化、待遇への不安、業界イメージの課題など、さまざまな要因があります。
単に求人を出すだけでは、応募者に自社の魅力を十分に伝えられないことも多いでしょう。
応募者は給与や条件だけでなく、職場の雰囲気や実際に働く人の声を重視しています。
そのため、社員のリアルな声や具体的な働き方の情報を伝えることが、採用力を高めるためには重要です。
採用活動を改善する際は、求人情報の見直しや働き方の改善、情報発信の工夫を組み合わせることで、より多くの求職者に安心感を持って応募してもらえる環境を作れます。
採用行動への一歩
ドライバー採用の課題を整理し、現状の採用手法や情報発信を見直すことから始めましょう。
応募者が安心して選べる情報を提供することが、自社に合った人材と出会う第一歩です。
まずは「どの情報を、どのように伝えるか」を整理し、現場の声を活かした採用戦略をご検討ください。