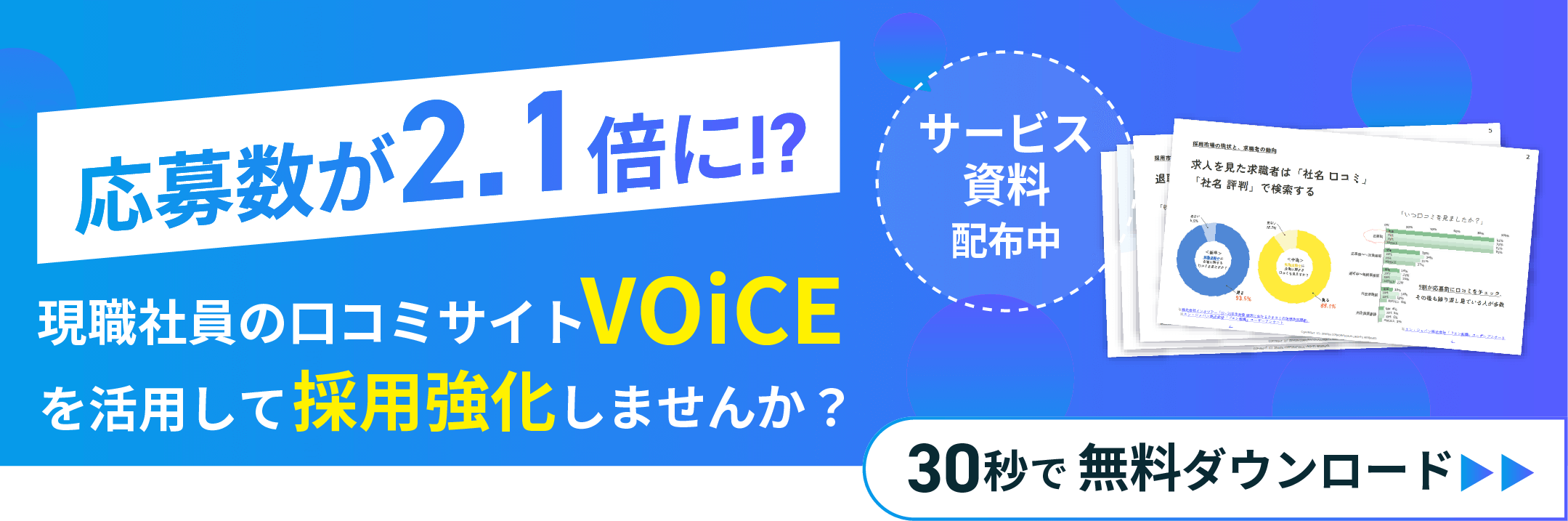「リアルを伝える」採用へ――“入社後ギャップ”を減らす採用ブランディングの新常識
- 口コミ対策
- 採用ミスマッチ
- 離職防止
2025.10.02
「入社後、想像と違った……」
そう感じさせてしまった時点で、採用活動が“片道切符の営業”に終わる可能性があります。
入社後ギャップが早期離職につながると、採用コストや教育投資が回収できず、企業の成長スピードにも影響します。
だからこそ、経営者や人事責任者に求められるのは「ギャップを減らす採用広報とブランディング」といえるでしょう。
この記事では、入社後ギャップを減らすための対策を整理しつつ、採用ブランディングの考え方と具体的な施策をご紹介します。
「定着率を高めたい」「採用の質を改善したい」と考える企業に向け、役立つヒントをまとめます。
第1章:入社後ギャップは「情報ギャップ」から「体験ギャップ」へ
入社後ギャップの変化
かつて「入社後ギャップ」と言えば、企業が十分に伝えなかったために起きる“情報不足”が原因でした。
「残業が多いと知らなかった」「給与体系が不透明だった」など、求人票や面接だけでは伝わらない情報が不満につながっていたのです。
しかし今は状況が変わっています。
求人サイトには詳細な条件が掲載され、企業の採用ページも多様なコンテンツを発信しています。
さらにSNSや口コミサイトが普及したことで、求職者は現場の声や働き方の実態を調べやすくなりました。
つまり、昔のように「情報が不足していたからギャップが生じた」という単純な構図ではなくなっているのです。
「体験ギャップ」とは
現在のギャップは、求職者が想像する「体験イメージ」と異なることから生まれる“体験ギャップ”です。
例えば、
- 「チームワーク重視」と聞いていたが、個人作業が思ったより多かった
- 「若手が活躍している」と紹介されていたが、裁量を持つのは一部に限られていた
- 「柔軟な働き方ができる」と期待していたのに、在宅勤務は実質的に難しかった
このように、企業が虚偽を伝えているわけではなくても「想像していた環境と違う」というズレが発生することがあります。
事前のイメージと体験が一致しないと、求職者の期待値は満たされず、入社後のモチベーション低下を招くおそれがあるのです。
体験ギャップが発生する背景
では、なぜ体験ギャップは起きるのでしょうか。背景には以下の要因があると考えられます。
採用広報の表現と現場の実態のずれ
採用担当者が「魅力的に伝えたい」という意識からポジティブな側面を強調しすぎると、現場とのギャップが生じやすくなります。
求職者の情報解釈のばらつき
同じ情報でも、受け取り方は人によって異なります。
「成長できる環境」と聞いて、自主性に任せる文化を想像する人もいれば、手厚い研修制度を期待する人もいます。
企業文化は数値化しにくい
働く上で大きな影響を与えるのは職場の空気感や人間関係ですが、これは求人票や説明会で伝えるのが難しい領域です。
このようないくつもの要因が重なり、体験ギャップは避けにくい構造になっているのです。
定着率への大きな影響
「思っていた環境と違った」という入社後ギャップは、仕事への意欲を下げ、早期退職の引き金になるケースもあります。
そのため、入社後ギャップは社員の定着率につながる課題といえるでしょう。
厚生労働省の統計によれば、新卒社員の3年以内の離職率は大卒で約30%※。
中途採用でも、早期での離職が一定数見られます。
特に若手世代は、違和感を抱いたときに早めに転職を選ぶ傾向が強いと見られています。
このような早期離職は、単に人材が抜けるだけでなく、以下のような企業への影響をもたらすおそれがあります。
- 採用コストや教育投資の回収が難しくなる
- 残された社員の負担が増え、職場の士気が下がる
- 組織の成長計画が遅れる
結果として、経営課題へとつながってしまうのです。
※出典:厚生労働省HP「新規学卒就職者の離職状況」(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html)
課題を放置できない理由
採用市場は年々競争が激化しています。
労働人口の減少により、求職者にとって選択肢が増え、企業は選ばれる立場になりました。
この状況で「入社後のギャップ」を放置してしまうと、せっかく採用した人材を失いやすくなり、組織の安定性を損ないかねません。
反対に、ギャップを減らせれば定着率を高められ、採用コストを有効に活用できる可能性があります。
そのため、経営者や人事担当者にとって「入社後ギャップ対策」は避けて通れないテーマといえるのです。

第2章:採用段階での期待値調整による入社後ギャップ対策
ギャップの根本は「期待と現実のずれ」
入社後ギャップの本質は、情報不足ではなく「期待値のミスマッチ」にあると考えられます。
この期待値は、求人票の文章や面接での言葉、さらには社員紹介記事など、あらゆる場面で形成されます。
たとえ情報自体が正しくても「受け手がどう想像するか」でズレが起きるのです。
採用時の期待値調整で入社後ギャップを防ぐ
そこで必要なのが「期待値調整」です。
期待値調整とは、求職者に対して「良い面」だけでなく「現実的な面」も伝え、あらかじめ理解してもらうこと。
例を挙げると、
- 「裁量が大きい」文化は、自分で動ける人には魅力的ですが、指示を待つタイプには厳しく映るかもしれません。
- 「スピード感のある環境」は、チャレンジを求める人に合いますが、安定志向の人には合わない場合があります。
こうした特徴を誇張せず、ありのまま伝えることが定着率向上に役立つ可能性があるのです。
求職者の「選択の質」を高める
期待値調整は、単に企業を守るためのものではありません。求職者にとってもメリットがあります。
入社前に現実を知ることで、自分に合う職場かどうかを判断しやすくなるためです。
その結果「入社してよかった」と感じる人材が増え、双方にとって満足度の高い採用になり得ます。
現代での採用活動は“単なる人材の補充”ではなく“いかに企業に合った人材と出会えるか”が問われる時代です。入社後ギャップを減らし、適材適所を実現することが、長期的な組織づくりの鍵となるでしょう。
実践できる入社後ギャップ対策の具体例
では、期待値の調整方法にはどのようなものがあるでしょうか。代表的な方法をいくつかご紹介します。
ネガティブ情報も適切に共有する
「忙しい時期は残業が発生する」「ルールがまだ整っていない部分がある」など、課題も隠さず伝えることが大切です。
働く社員の実際の声を届ける
求職者は企業側の言葉より、現場で働く社員の声に信頼を置きやすい傾向にあります。
実際に働く社員の目線で「1日のスケジュール」や「やりがいと大変さ」を発信することで、リアルな期待値を持ってもらいやすくなります。
入社前の体験機会をつくる
インターンや職場見学を通じて、実際の雰囲気を感じてもらうことも効果的です。
特に中途採用では、入社前に職場を体感できることで安心感が高まる可能性があります。
採用広報の言葉を精査する
「自由」「アットホーム」「裁量大」など曖昧な表現は、受け手によって解釈が異なりやすいものです。
数値や具体例を交えて伝えることで、ズレを減らせます。
入社後ギャップ対策を意識した採用戦略
期待値調整は「企業の弱みをさらす」ことではありません。
むしろ、正直に伝える姿勢は企業の信頼を高める可能性もあるのです。
近年は「入社前と違った」と感じた社員が自身のSNSで発信するケースもあり、透明性を欠いた採用は炎上リスクにもつながりかねません。
反対に「入社前から聞いていた通り」と思ってもらえれば、定着率だけでなくエンゲージメントの向上にも役立ちます。
採用市場で選ばれる企業になるためには、「期待値調整」を前提とした採用広報が大切といえるでしょう。
第3章:採用ブランディングで実践する入社後ギャップ対策のポイント
入社後ギャップ対策に欠かせない採用ブランディング
採用ブランディングとは、単に企業の魅力を発信するだけでなく「その会社らしさ」を外部に伝え、求職者の理解を深めるための取り組みです。
従来の採用活動は「条件や制度」を中心にした情報提供が主流でした。
しかし現在は、働き方や社風など“目に見えにくい部分”が重視される時代へと変化している傾向が見られます。
入社後ギャップを防ぐには、良い面も課題も含め「ありのままの姿」を伝えるブランディングが欠かせません。
ポイント①現職社員の声を中心にする
入社後のイメージに影響を与えやすいのは「一緒に働く社員のリアルな声」です。
経営層や採用担当者の言葉よりも、現場で働く社員の経験談のほうが求職者に響きやすい傾向があります。
具体的には、
- 社員インタビュー記事や動画を制作する
- 1日の働き方やキャリア事例を紹介する
- やりがいだけでなく、苦労した経験もあえて発信する
こうしたコンテンツは「このような人たちと働くのか」とイメージを具体化させ、体験ギャップを減らす効果が期待できます。
ポイント②カルチャーや価値観を明示する
入社後ギャップは「仕事内容」よりも「カルチャーの違い」で大きくなりやすいと考えられます。
例えば「スピードを最重視する文化」と「手順を丁寧に守る文化」では、求職者によって合うか合わないかが顕著に出やすいでしょう。
そのため、採用ブランディングでは「私たちの会社が大切にしていること」を明確に発信する必要があります。
- 意思決定のスピード
- 成果主義かプロセス重視か
- チームワークと個人裁量のバランス
これらを具体的に説明することで、入社前に価値観に対する認識が一致しているか確認しやすくなります。
ポイント③「良い面」と「リアルな課題」をバランスよく伝える
ブランディングというと「ポジティブな部分だけを発信するもの」と誤解されがち。
しかし、現実とのギャップを小さくするには、課題や大変な部分もきちんと共有する姿勢が重要です。
例えば、
- 急成長中なので、制度が追いついていない部分もある
- 繁忙期は残業が増えるが、その分チームで協力して乗り越えている
このように、課題を伝えながらも「どのように取り組んでいるか」を補足することで、ネガティブな印象を和らげられます。
ネガティブなことも誠実に伝える姿勢そのものが、企業への信頼につながりやすくなるのです。
採用ブランディングは「社内にも効く」
採用ブランディングの効果が期待できるのは、社外だけではありません。
社員の声や価値観を整理して発信するプロセスは、現職社員が考える「自分たちの会社らしさ」の再認識にもつながります。
その結果、
- 社員の帰属意識やエンゲージメントが高まる
- 新入社員の受け入れに一体感が生まれる
- 社内のコミュニケーション改善にもつながる
このような効果も期待できるのです。
つまり、採用ブランディングは「入社後ギャップ対策」であると同時に、組織全体を強くする取り組みといえるでしょう。
第4章:VOiCE活用で進める入社後ギャップ対策
VOiCEとは
VOiCEは、現職で働く社員の声を収集し、企業ごとのリアルな口コミをまとめたサービスです。
従来の求人情報や採用サイトでは見えにくかった「職場の雰囲気」「実際の働き方」といった生の情報を、求職者が確認できる仕組みを提供しています。
この特徴により、企業側も「自社がどのように見られているか」を把握し、採用広報や定着率改善に役立てられます。
入社後ギャップ対策に役立つポイント
信頼性の高い一次情報を提供できる
VOiCEでは現職社員の声が中心となるため、求職者がイメージを具体化しやすくなります。
企業の公式発信だけでは伝わりにくい部分を補い、期待値調整をサポートします。
ポジティブと課題の両面を見せられる
「やりがい」「成長実感」といった前向きな側面だけでなく「忙しい時期の大変さ」などリアルな声も掲載されます。
これにより、入社後のズレを減らし、定着につながる採用に役立てます。
データとして社内改善にも活用できる
社員の声を分析することで、組織の強みや改善点を把握しやすくなります。
採用ブランディングだけでなく、人事施策や職場環境改善にもつなげられる点が特徴です。
入社後ギャップ対策におけるVOiCEの活用法
採用広報での活用
自社サイトや採用ページにVOiCEの情報を組み込むことで、求職者が「外から見える情報」と「中で働く人の声」をセットで確認できます。
面接後の補足資料として
面接後に「社員の声も公開しています」と紹介することで、候補者からの信頼を得やすくなります。
候補者は、面接担当者の主観だけに依存しない客観的な情報を判断材料のひとつとして活用できます。
入社後フォローとして
内定者に事前に社員の声を見てもらうことで、入社前後のギャップを減らす効果も期待できます。
「聞いていた通りだ」と思えることで、早期離職の防止につながる可能性があります。
VOiCE導入による入社後ギャップ対策のメリット
VOiCEの導入は、入社後ギャップ対策を後押しするだけでなく、次のような副次的効果も生む可能性もあります。
- 採用時に透明性を示せることで、候補者からの信頼度を高まりやすくする
- 社員が自ら声を発信することで、エンゲージメントや帰属意識の向上に役立てる
- 採用活動だけでなく、社内の改善サイクルにも活用できる
「採用ブランディングの強化」と「定着率向上」の双方をサポートするサービスとして、VOiCEは採用の一助となります。
まとめ:入社後ギャップ対策で定着につなげる採用の実現へ
入社後のギャップは、企業と求職者の双方にとって大きな損失につながりかねません。求人票や面接から受けた期待値と現実のずれが積み重なれば、早期離職の原因となり、採用コストや教育投資が回収できないことも。
一方で、採用活動の段階から情報の透明性を高め、求職者が働く姿をリアルにイメージできる工夫を取り入れられれば、入社後のギャップは減らせる可能性もあります。
さらに、現職社員の声や具体的なキャリアパスの提示、カルチャーフィットを意識したコミュニケーションを行うことは、企業に対する信頼を高め、結果的に定着率向上や採用ブランディング強化にも役立ちます。
これからの採用では「数を集める」ことよりも「ミスマッチを防ぎ、長く活躍してもらう人材を迎えること」が重要です。入社後のギャップ対策をひとつずつ実行していくことで、企業の成長を支える安定した組織づくりが可能になるでしょう。