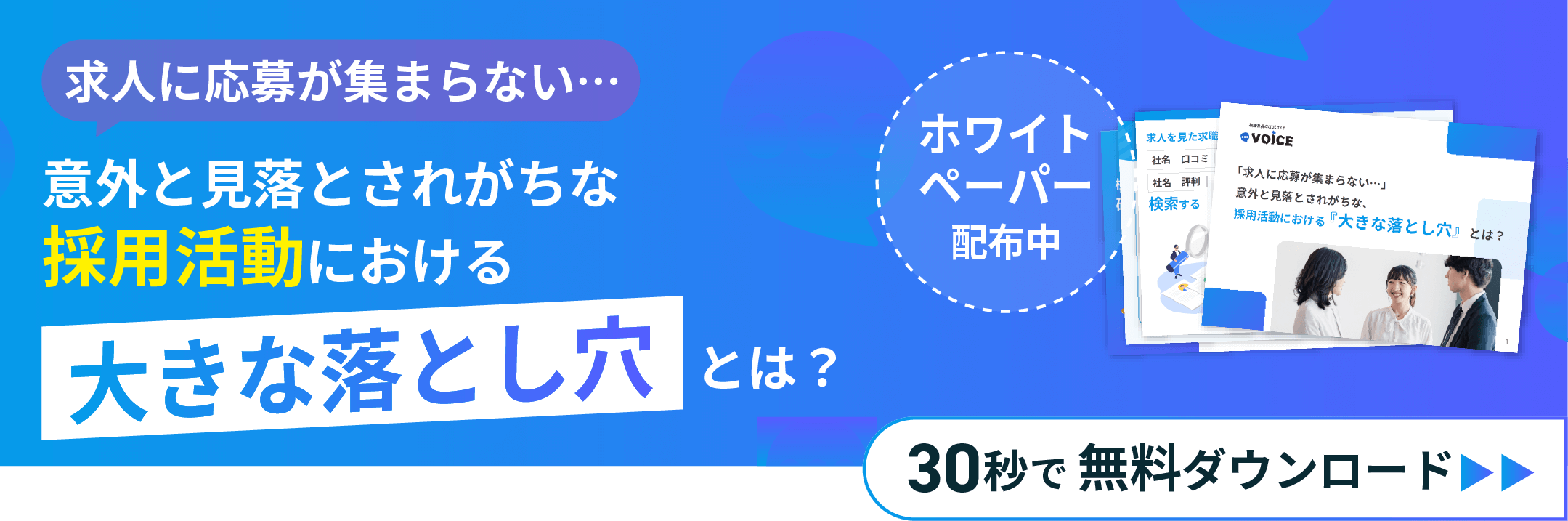なぜデザイナー採用は難しいのか?競争市場と求職者目線から考える採用成功のポイント
- 採用強化
- 採用活動
- 採用課題
2025.10.02
「ポートフォリオを見ても判断に迷う」「応募自体が少ない」「良い人材は大手やフリーランスに流れてしまう」——デザイナー採用に取り組む中で、このような悩みを抱える企業は少なくありません。特に中小企業やスタートアップでは、知名度や待遇面で大手企業と比較されやすく、優秀な人材を確保するのが難しいと感じているところも多いでしょう。
デザイナーは事業のブランディングやサービスの使いやすさ、ユーザーが得られる体験などを支える重要な職種です。しかし採用市場では需要に対して供給が追いつかず、採用が難航する傾向があります。この記事では「なぜデザイナー採用は難しいのか」という背景を整理しながら、企業が取り組むべき工夫や施策を考えていきます。
第1章:デザイナー採用が難しい5つの理由
デザイナー採用の難しさは、単に応募が集まりにくいという表面的な課題だけではありません。市場環境や働き方の変化、求職者の価値観など、いくつもの要因が絡み合っています。ここでは、企業が直面しやすい代表的な5つの理由を整理してみましょう。
1. デザイナーの人材が不足している
まず大きな理由は、デザイナーの数そのものが不足している点です。ITや広告、プロダクト開発など多くの業界でデザイン職の需要が高まっています。UI/UXデザインやWebデザインなど専門性が細分化される一方で、養成機関や教育環境は需要の伸びに追いついていません。その結果、求人に対して応募者の母数が少なく、採用競争が激しくなっています。
2. スキルやポートフォリオの評価が難しい
営業職や事務職とは違い、デザイナーのスキルは数値化しにくいという特徴も。ポートフォリオを提出しても、評価の判断が難しい場合があるのです。また、作品だけでは本人の再現性や実務での対応力が見えにくく、採用判断が難しくなりがちです。
3. フリーランスの増加で採用競争が激化
デザイナーの中にはフリーランスとして独立する人も多くいます。柔軟な働き方を求める人材は、企業に就職するよりも個人で案件を受けることを選ぶという傾向もあるのです。そのため、特に中小企業は「フリーランスという選択肢」とも競合しながら採用活動を進める必要があります。
4. 求職者の企業選びの基準が多様化している
給与や福利厚生だけでなく、デザイナーは「やりがい」「裁量」「企業としてのデザインに対する価値観」を重視する傾向があります。社内でデザインの価値がどの程度理解されているか、チーム体制はどうかといった点も重要です。こうした情報を求職者に見える形で整えていないと、魅力的な求人として映りにくく、応募が集まりにくい状況になります。
5. 大手企業との比較で差が出やすい
知名度や安定性が高い大手企業は、多くの求職者から選ばれやすい傾向があります。中小企業やスタートアップが採用を成功させるには、給与やブランド力以外の差別化が必要となるでしょう。しかし、差別化を十分に打ち出せていない場合、求職者に自社の魅力が十分に伝わらないことがあります。

第2章:求職者が見ている“採用情報の本質”
デザイナー採用において、企業が意識すべきなのは「応募者が本当に知りたい情報は何か」という視点です。求人票に給与や条件を載せるだけでは、デザイナーに刺さる情報になりにくいのが実情です。ここでは、求職者が重視するポイントを整理します。
1. デザイナーが知りたい仕事内容と裁量の範囲
デザイナーは自分のスキルがどのように活かされるのかを強く意識します。
「主にどのようなプロジェクトを担当するのか」「意思決定にどの程度関われるのか」といった仕事における具体的な情報が欠けていると、応募をためらう要因となりやすいです。そのため、採用活動の中で業務の具体像をイメージできるように情報を提示することが重要です。
2. チーム体制やデザイナーの社内での位置づけ
デザインを1人で任されるのか、エンジニアやマーケターと連携できるのか——。デザイナーにとって、社内で孤立せず働ける環境かどうかは重要な関心事のひとつです。
また、企業のホームページや求人情報だけでは、デザインの重要性やデザイナーの価値をどのように考えているのか読み取るのが難しいケースも。そうした場合、応募者は「成果が正しく評価されるか分からない」と不安に感じやすくなり、応募意欲の低下につながることもあります。
そのため、職種間の連携や評価体制をあらかじめ明示しておくことは、応募者に安心感を与える上で効果的といえるでしょう。
3. 成長機会やキャリアパスの有無
デザイナーはスキルアップを重視する傾向が強い職種です。研修制度や外部セミナーの参加支援、デザインツールの導入など、成長を支える仕組みがあるかどうかは応募判断に大きく影響します。キャリアの先に「アートディレクター」「リードUI/UXデザイナー」などの役割が描けるかどうかも注目されています。
4. 働きやすさや柔軟な働き方への対応
リモートワークやフレックス制度の有無も、多くのデザイナーが確認するポイントです。特にクリエイティブ職は集中環境を重視するため、働き方の柔軟性が応募意欲を左右する傾向も見られます。働きやすい環境や制度が整っている場合は、求人情報で具体的に伝えると効果的です。
5. 現職社員のリアルな声が与える安心感
求人票だけでは伝わらない要素として「現職社員の声」があります。働く人の体験談は、社風やカルチャーを知る上で大きな判断材料となるでしょう。特にデザイナーは「現場でどのようなプロジェクトが進んでいるのか」「チームの雰囲気はどうか」といった、実際に働く人の目線で見た具体的なイメージを知りたいと思っている方が多いです。
第3章:デザイナー採用を成功させるために企業がやるべき施策
デザイナー採用を難しくしている背景を踏まえると、単に求人広告を出すだけでは成果につながりにくいのが現実です。ここでは、中小企業やスタートアップが実践できる具体的な施策を整理します。
デザインの重要性を組織で共有する
デザイナーが働きやすい環境を整えるためには、まず経営層や他部署が「デザインの価値」を理解していることが欠かせません。「デザインは単なる装飾ではなく、事業戦略に直結する要素である」という共通認識を持っていると示すことが、応募を考えているデザイナーに安心感を与えます。採用前からこの認識を社内で共有し、求人情報にも反映できると効果的です。
自社ならではの魅力を言語化して発信する
大手企業と比較すると、ブランド力や給与面で差が生じやすい傾向にあるのは事実です。しかし、スタートアップや中小企業ならではの魅力もあります。例えば「裁量の大きさ」「意思決定のスピード」「多様な業務に挑戦できる環境」などです。こうした強みを具体的に言語化し、求人票や採用サイトで伝えることで、共感を持つ人材を引き寄せやすくなります。
ポートフォリオ評価の基準を整える
デザイナー採用では、ポートフォリオが大きな判断材料になります。企業側にデザインの専門家がいない場合は、評価基準を事前に定めておくことが有効です。例えば「ターゲットに合ったデザインか」「課題解決の意図が説明されているか」といった観点です。これにより、作品の見た目だけに左右されず、再現性のある人材を見極めやすくなります。
社員の声を活用して情報発信する
応募者は実際の職場環境を重視する傾向があります。そのため、現場で働く社員の声を公開することは効果的といえるでしょう。デザイナー自身や一緒に働くチームメンバーの体験談を発信することで、応募者が「ここで働く自分」を想像しやすくなります。こうした情報は、求人媒体だけでなく、自社サイトやオウンドメディアでも活用できます。
柔軟な働き方を検討する
優秀なデザイナーほど、自分に合った働き方を求める傾向があります。リモート勤務、フレックスタイム、副業との両立など、可能な範囲で制度を整えることで、応募の幅を広げられます。条件をすべて満たす必要はありませんが、柔軟性を示すだけでも応募意欲を高められる可能性があります。
第4章:デザイナー採用に役立つ「VOiCE」の特徴と活用方法
デザイナー採用を進める上で、多くの企業が課題と感じているのが「求職者に自社のリアルな魅力をどう伝えるか」という点でしょう。給与や条件だけでは差別化が難しいため、働く環境や文化を伝えることも有効です。そこで役立つのが、社員の声を集めて可視化できるサービス VOiCE です。
VOiCEとは
VOiCEは、現職で働く社員による体験談や意見を集めた口コミサイトです。応募者が気になる「実際の職場の雰囲気」や「働き方」「チームの関係性」などを、文字情報として確認できます。求人票だけでは伝えきれない部分を補うことで、求職者の不安を和らげるのに役立ちます。
デザイナー採用における強み
デザイナーは、具体的な仕事内容や評価の仕組みといったリアルな実情を知りたいと考えている傾向があります。そのため、現職社員のリアルな声は大きな判断材料のひとつとなるでしょう。VOiCEを活用すると「デザインに対する社内の理解度」「チームでの働きやすさ」といった情報を現場で働く社員の目線で伝えやすくなります。これにより、応募前にギャップを埋め、ミスマッチを減らす一助となります。
デザイナー採用におけるVOiCEの活用ポイント
VOiCEを効果的に使うには、単に情報を掲載するだけでなく、採用活動全体に組み込むことが大切です。
- 求人票にリンクを設置して、応募者がスムーズに社員の声を確認できるようにする
- 採用サイトやオウンドメディアにVOiCEの情報を引用し、自社の魅力を裏付ける材料にする
- 面接案内の際に応募者へVOiCEを紹介し、企業理解を深める参考とすることで質問しやすい雰囲気をつくる
こうした工夫によって、企業の透明性が高まり、応募者の信頼を得やすくなる可能性が高まります。
まとめ:デザイナー採用の難しさと企業が実践すべき対策
デザイナー採用が難しい背景には、人材不足やスキル評価の難しさ、フリーランスとの競合、そして求職者が重視する基準の多様化があります。特に中小企業やスタートアップは、大手企業と比べると知名度や条件で差が出やすいため、採用成功にはひと工夫が必要になるといえるでしょう。
採用を成功させるためには、組織としてデザインの価値を共有し、自社ならではの魅力を言語化して発信することが大切です。また、ポートフォリオの評価基準を整えたり、柔軟な働き方を検討したりすることも効果的といえます。さらに、求人票だけでは伝わらない「現職社員のリアルな声」を可視化することが、求職者に安心感を与える大きな要素となり得ます。
VOiCEは、現職社員の体験談を採用活動に組み込むサポートが可能なサービスです。企業側から透明性の高い情報を発信することは、応募者と信頼関係を築くだけでなく、採用後の定着率向上にもつながります。
VOiCEでデザイナー採用をサポート
デザイナー採用を難しく感じている企業こそ、まずは自社の魅力を「リアルな声」で伝える工夫が大切です。
VOiCEでは、実際に働く社員の体験談を収集・掲載できる仕組みを提供しています。求人票だけでは伝えきれない職場の雰囲気や働き方を、応募者に分かりやすく伝えられます。