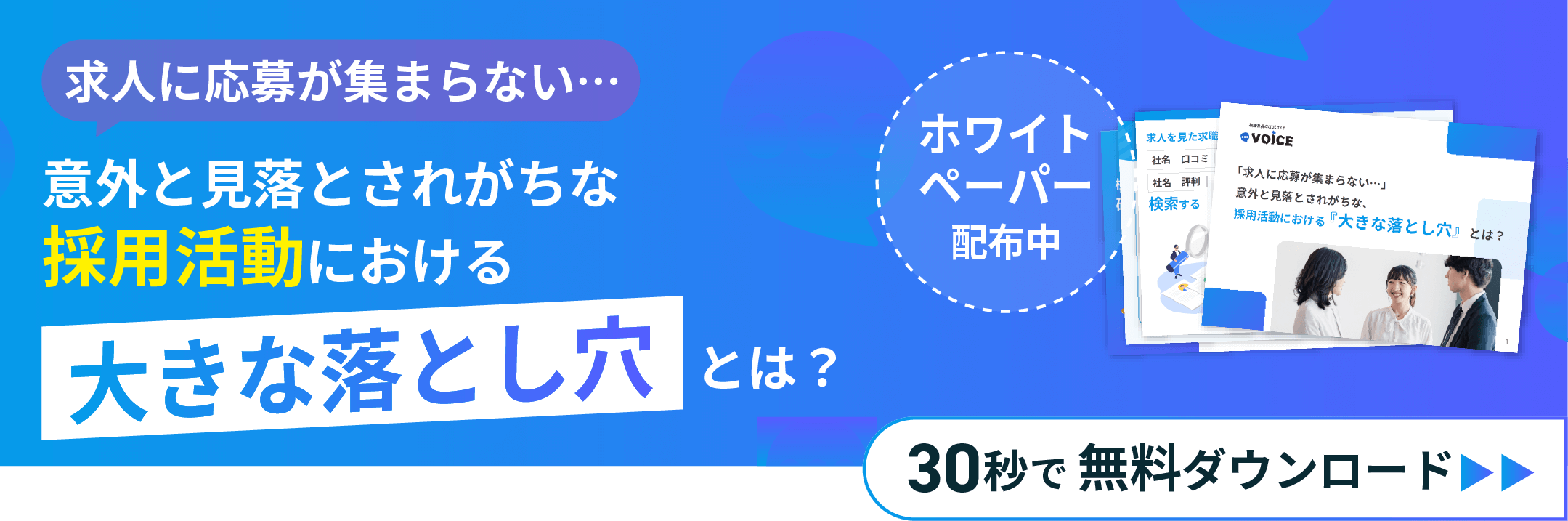施工管理の採用がうまくいかない理由とは?人材確保につながる現場発信のすすめ
- 採用強化
- 採用活動
- 採用課題
2025.09.24
建設業界の中でも、施工管理職採用の難しさに頭を抱える企業は多いでしょう。
「求人を出しても応募が少ない」「入社しても定着しない」という具体的な課題を感じている経営者や人事担当者もいます。
その背景には、少子高齢化による労働人口の減少や建設需要の拡大があるのです。国のインフラ整備や都市開発は進んでいますが、現場を支える人材は限られているため、採用競争は年々激しさが増しています。
さらに、施工管理という仕事は専門性が高く、長時間の現場対応や関係者との調整など、求職者にとってハードルが高いと感じられる側面も。そのため「施工管理の採用が難しい」という課題は、多くの企業で共通するものと考えられます。
この記事では、施工管理の採用が難しい理由を整理しながら、解決の糸口として「社員のリアルな声を活かした採用広報」に注目して解説。従来の求人票だけでは伝えきれない企業の魅力をどう発信するか、そのヒントをお伝えします。
第1章:施工管理の採用が難しい背景とは?
施工管理職の採用が難しいといわれる背景には、いくつかの要因が重なっています。ここでは主なポイントを整理します。
1. 労働人口の減少と若手不足
日本全体の労働人口は減少傾向にあり、建設業も若年層の志望者が少なくなっています。大学や専門学校で建築を学んだ人材は、必ずしも施工管理を志望するわけではなく、設計や不動産など他の職種を志すケースもあるのです。
2. 仕事内容のイメージが伝わりにくい
施工管理の仕事は「現場監督」と説明されることが多いですが、具体的にどのような業務を担うのかを正しく理解している求職者は少ないでしょう。安全管理、工程管理、品質確認、関係者との調整など、幅広い業務がある一方で、それを求人情報だけで正確に伝えるのは難しいのが実情です。
3. 勤務条件への懸念
施工管理は現場ごとに勤務時間や働き方が異なり、残業や休日出勤が発生することもあります。求職者は「ハードワークではないか」という不安を抱きやすく、応募をためらう要因のひとつとなってしまうこともあるのです。
4. 採用競争の激化
大手ゼネコンから地域工務店まで、施工管理の人材を求める企業は多岐にわたります。待遇や研修制度などで差別化が図られる中、求職者は選択肢を慎重に比較します。その結果、中小企業では応募が集まりにくい状況が生まれやすいです。
5. 定着率の課題
採用できても、早期離職につながるケースもあります。理由として「仕事内容が想像と違った」「現場の雰囲気になじめなかった」という声が挙げられる場合も。これらの理由は、採用時に十分な情報が伝わらず、ミスマッチが起きてしまうことが原因になっていると考えられます。
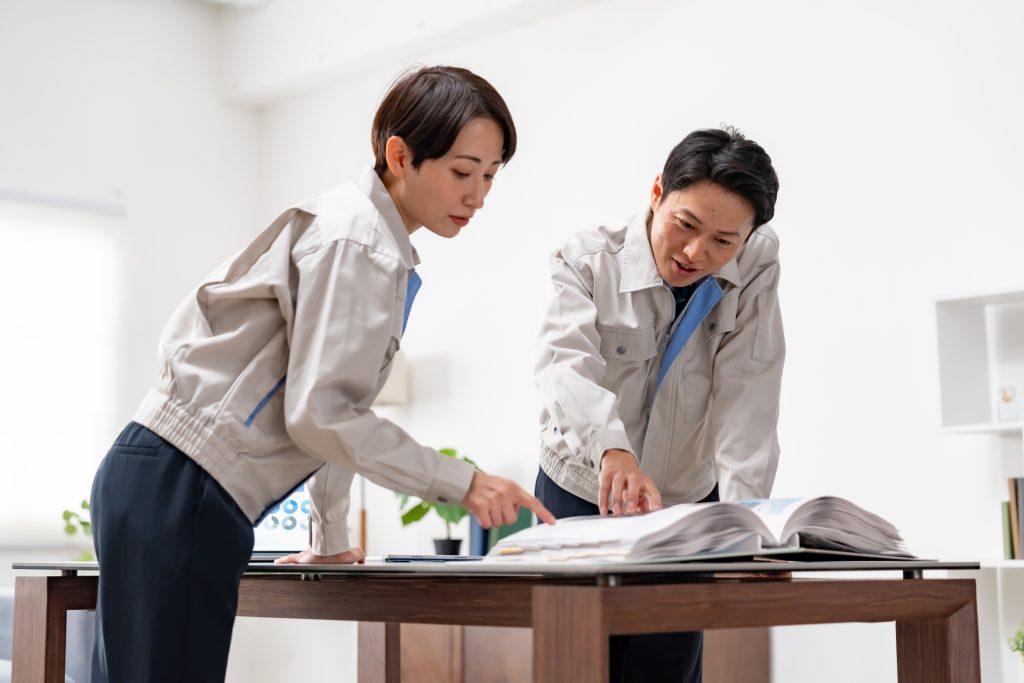
第2章:求職者が見るのは“企業の中のリアル”
施工管理の採用が難しい背景には、仕事内容や条件だけで求職者の知りたい情報を伝えきることが難しく、魅力が伝わりづらいという問題があります。求人票に書かれた給与や福利厚生はもちろん重要ですが、それだけでは応募意欲を高めるには不足している可能性もあるのです。
では、求職者はどのような情報を求めているのでしょうか。求職者が応募する際に知りたい情報についてそれぞれ解説します。
1. 現場の雰囲気や人間関係
施工管理の仕事は、多くの関係者と協力しながら進めます。そのため、働く環境や人間関係の安心感は、応募を決める大きな要因のひとつです。
「現場にどのような上司や先輩がいるのか」「チームの雰囲気はどうか」といったリアルな情報が、求職者にとって応募意欲を高めるポイントになるといえるでしょう。
2. キャリアパスと成長の実感
施工管理は専門的なスキルを積み上げていく職種です。入社後にどのように成長できるか、資格取得やキャリアアップの支援があるかといった点を、求職者は重視する傾向にあります。
求人票に『資格取得支援制度あり』と記載されていても、求職者が実際の内容や活用方法をイメージするのは難しい場合も。実際に社員がどのように資格を取り、どのようなキャリアを歩んでいるのかを示すことは、制度の理解を深める参考になります。
3. ワークライフバランスへの配慮
「施工管理の採用が難しい」といわれる要因のひとつに、求職者が労働時間への不安を感じているケースも。長く働き続けたいと考える求職者の多くは「どの程度の残業があるのか」「休日は確保できるのか」というリアルを知りたいと思っている傾向にあります。
実際に働く現職社員の声を通じて、働き方の工夫や会社の取り組みを発信すれば、安心感を持つ一助になります。
4. 求職者は“外の声”も参考にする
今の求職者は、求人票だけで判断せず、SNSや口コミサイトで企業の評判も確認します。公式サイトの情報だけでなく、現場で働く社員の声や体験談に信頼を寄せる傾向があるのです。
そのため、採用を成功させるためには、企業が発信する情報と現職社員のリアルな声をうまく組み合わせることが大切といえるでしょう。
「施工管理の採用が難しい」という課題を乗り越えるためには、数字や制度の説明だけでなく、求職者が本当に知りたい“日常のリアル”を伝えることが重要です。
次章では、その実現につながる「現場主導の広報」の考え方について解説します。
第3章:施工管理の採用に効く、“現場主導の広報”とは?
「施工管理の採用が難しい」と課題を感じている企業が増える中で、注目されているのが“現場主導の広報”です。これは、経営層や人事部が一方的に情報を発信するのではなく、実際に働く社員の声を積極的に届ける取り組みを指します。
なぜ現場の声が有効なのか
求職者は、制度や条件だけでなく「この会社で自分が働く姿」を想像したいと考える傾向が強まっています。そのとき役立つのが、現場で働く社員の具体的な体験談。
「入社のきっかけ」「成長を実感できた瞬間」「現場でのやりがい」など、現職社員のリアルな声は求人票だけでは伝わらない、その会社ならではの魅力を伝えやすいのです。
企業発信と社員発信のバランス
企業からのメッセージは、どうしても広報的になりやすく、求職者から見ると「宣伝色が強い」と受け止められることがあります。
一方、社員が自ら語る言葉には温度感があり、信頼性向上の助けになります。企業発信と社員発信をバランスよく組み合わせることで、情報の透明性も高まる可能性があるのです。
採用ブランディングへの効果
現場主導の広報は、単に応募を増やすためだけではなく、中長期的な採用ブランディングに役立つことも。
「この会社は社員が生き生きと働いている」「現場の雰囲気が伝わって安心できる」と求職者に感じてもらえれば、応募だけでなく定着率の改善にも結びつく可能性があります。
実現のための工夫
現場主導の広報を進めるには、以下のようないくつかの工夫が必要です。
- インタビュー記事の作成:社員に日常やキャリアについて話してもらい、記事化する。
- 動画での発信:現場の雰囲気を伝える短い動画を制作する。
- 口コミプラットフォームの活用:第三者視点で社員の声を集め、求職者に発信する。
こうした工夫を組み合わせることで「施工管理の採用が難しい」という課題を抱える企業でも、他社との差別化を図れる可能性があります。
次章では、現場の声を活用する取り組みを支援するサービスとして、口コミプラットフォーム「VOiCE」の特徴をご紹介します。
第4章:VOiCEの特徴|現職社員の声を活かした採用広報
施工管理の採用において「現場のリアルをどう発信するか」という課題を解決するために役立つのが、口コミプラットフォーム「VOiCE」です。
現職社員の声を届けられる
VOiCEは、現職で働く社員によるリアルな声や体験談を掲載できるサービスです。
企業の公式情報だけでは伝えきれない「現場の雰囲気」や「働く上での実感」を、求職者に自然な形で届けやすくします。
求職者の不安をやわらげる
「施工管理の採用が難しい」とされる理由のひとつは、仕事内容や働き方がイメージしづらい点にあります。
VOiCEを活用すると、社員の声を通して仕事の魅力やキャリアパスを示すことができ、応募前の不安を軽減する助けになると考えられます。
情報の信頼性を高める
求人票や会社説明資料はどうしても「企業目線の情報」になりやすいですが、VOiCEでは社員自身が語る言葉が中心になります。
そのため、求職者にとって信頼性が高く、応募意欲の向上につながる可能性が高まります。
応募から定着までを支援
VOiCEの導入は、応募数の増加だけでなく、入社後の定着率向上にも役立つ場合も。
事前に現場の雰囲気を知った上で応募する人が増えるため、ミスマッチを防ぎやすくなるのです。その結果、早期離職が課題となっている企業でも、効果的に活用できる場合があります。
ポジティブなサイクルを生み出しやすい取り組み
VOiCEは「活躍人材の声が、活躍人材を呼ぶ」というポジティブなサイクルを生み出しやすくする取り組みを行っています。
1. 現職社員に社内アンケート(らしさ診断)を実施
現職社員が自社についてどう感じているかを調査します。「仕事のやりがい」「人間関係」「評価制度」「活躍実感値」などを可視化し、自社の強みや課題を言語化します。
2. ポジティブな声を求職者に発信
アンケート結果を数値化し、VOiCEに掲載。検索で「社名 口コミ」「社名 評判」と調べた際に、現職社員のリアルな口コミとして表示されます。求人票では伝えにくい働きやすさや働きがいも、求職者に届けられます。
3. ネガティブな声を組織改善に活用
改善のヒントとなるネガティブな意見も拾い上げます。VOiCEなら、良い声は採用広報に、課題の声は組織改善に活用できるケースがあります。これにより、採用活動だけでなく人的資本経営の推進にもつながります。
第5章:まとめ|施工管理採用を成功に導くポイント
施工管理の採用が難しいと感じる背景
近年、多くの企業が「施工管理の採用が難しい」と感じています。求人を出しても応募が集まらない、内定を出しても辞退されてしまう。さらに、せっかく採用できても定着せず、早期離職につながってしまうケースも少なくありません。
こうした状況を打開するには、募集枠を広げたり待遇面を強化したりするだけでは不十分な場合も。その理由は、求職者の本当に知りたい情報が「現場のリアル」や「社員の働き方」だと考えられるからです。そのため、求人票や企業HPだけでは伝わりきらない情報を、どう求職者に届けるか考えるのが採用成功の分かれ道となるでしょう。
現職社員の声が施工管理採用のカギ
特に施工管理職は、業務内容がイメージしづらく「自分に合うか分からない」と思われることもある職種です。そのため、実際に働く社員の声を発信することは、求職者に安心感を与え、入社後のミスマッチを防ぐ効果が期待できます。
第4章でご紹介した 「VOiCE」 は、こうした「現職社員のリアルな体験談」を整理し、採用広報に活かせる仕組みを提供しています。施工管理職の採用においても、現職社員の声を可視化することで、求職者が自分の働く姿を具体的にイメージしやすくなり、結果的に応募の質や定着率改善を促す一助になります。
次のステップへ
今すぐ取り組めること
- 自社で「施工管理の採用が難しい」と感じている理由を整理する
- 求職者が知りたい現場の情報を、社員インタビューなどで収集する
- 必要に応じて外部サービスを活用し、効率的に発信の仕組みを整える
採用市場の競争が厳しさを増す今だからこそ、透明性と信頼性のある情報発信が、施工管理職採用を成功させる大きなカギとなります。