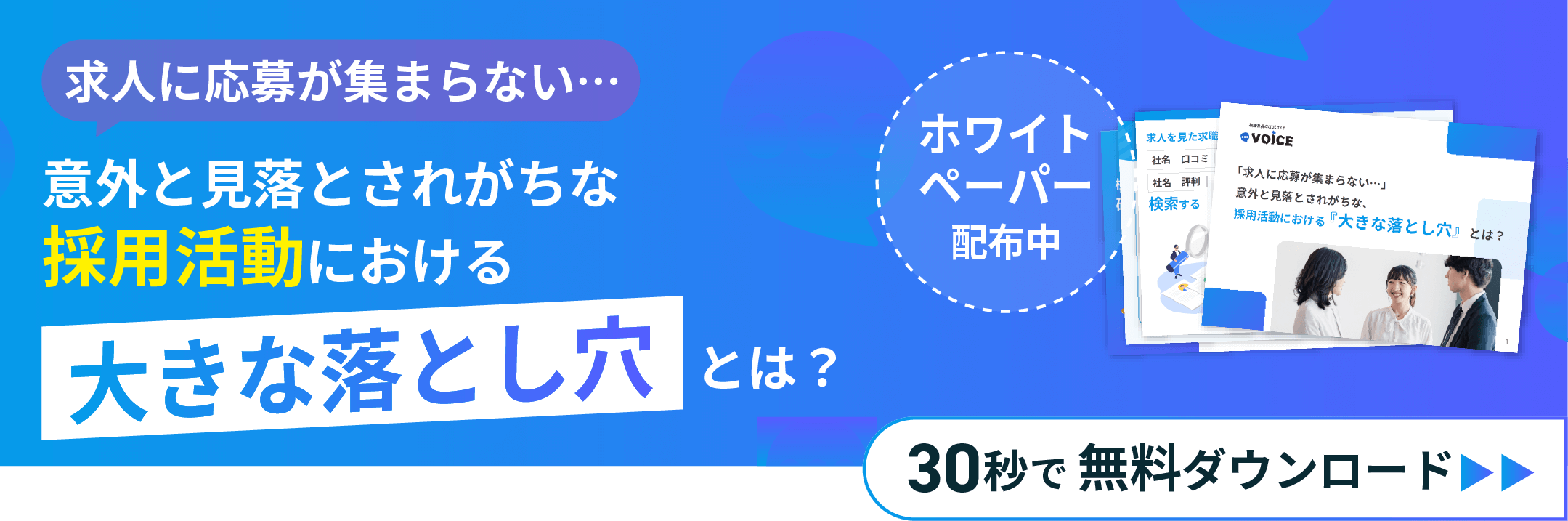整備士の採用が難しい本当の理由とは?応募を増やす採用広報の工夫
- 採用強化
- 採用活動
- 採用課題
2025.09.12
自動車業界を支える整備士は、欠かせない専門職です。ところが、近年は整備士の採用が難しいと感じる企業も増えています。求人を出しても応募が集まらない、内定を出しても辞退される——。こうした課題は経営者や人事担当者にとっても共通の悩みといえるでしょう。
採用が難しい背景には、業界の人材不足に加え、求職者の意識の変化もあります。単に待遇や条件を示すだけでは、応募につながりにくくなっているのです。では、整備士採用を成功させるために必要な視点とは何でしょうか。本記事では背景を整理しつつ、自社の採用広報を見直すためのヒントをご紹介します。
第1章:整備士の採用が難しくなっている3つの背景
整備士の採用が難しいといわれる理由は、ひとつではありません。業界全体の変化と求職者側の意識の変化が複合的に影響していると考えられます。
ここでは大きく3つの背景に分けて整理してみましょう。
1. 整備士人口の減少と資格取得者の減少
まず大きな背景としてあるのが、整備士や整備士を志す若者の人数が減少傾向にあるという点です。
その背景のひとつには「車離れ」と呼ばれる価値観の変化があります。都市部では車を持たないライフスタイルの方も増え、地方でもカーシェアの利用が広がりました。その結果、車に対して強い関心を持つ若者が少なくなり、整備士という職業に目を向ける人も減っている傾向にあるのです。
加えて、整備士になるには国家資格が必要です。資格取得のためには専門学校や実務経験が必要で、ハードルが高いと感じる人も多いです。そのため資格保有者が増えにくい状況が続き、採用市場に出てくる候補者も限られていると考えられます。
2. 労働環境のイメージと定着率
整備士は高度な専門知識を要する職業であり、自動車の安全を守るという社会的な役割も担っています。その一方で、体力的な負担も伴うため、就職希望者の中には「長時間労働が多いのでは」「キャリアアップが難しいのでは」と不安を抱く人も。
また、せっかく入社しても職場の雰囲気や人間関係が合わないこともあり、早期に離職してしまうケースもあります。整備士は経験を積むことも大切な仕事のため、定着率という課題も採用のハードルを高めている要因のひとつといえるでしょう。
3. 求職者の仕事選びの基準が変わりつつある
従来は「給与」「勤務地」「安定性」といった条件面が就職・転職の主な判断材料になっていました。
それに加えて、近年では「職場の雰囲気が自分に合うか」「社員同士の関係性はどうか」「キャリア形成の機会があるか」といった要素を重視する人が増えつつあります。中でも若い世代は、職場での働きやすさや将来性を気にする傾向が強まっているのです。
また、SNSや口コミサイトで職場の実態を調べてから応募する人も増えています。そのため求人票で条件を示すだけでは実情が伝わりにくく、反対に実際に働く社員の声や日常の雰囲気が「ここでなら頑張れそう」と思わせる決め手になることも多いと考えられます。
背景を踏まえた課題認識
整理すると、整備士の採用が難しいとされる背景には、
- 資格取得者が増えにくく、候補者が限られている
- 労働環境に対するイメージや不安が応募や定着に影響しやすい
- 求職者の基準が多様化し、条件提示だけでは不十分になっている
といった要因が重なっているとみられます。
だからこそ求人票の改善だけでなく、企業の魅力や実際の働きやすさをどう伝えるかが、これからの採用活動において重要になっていくでしょう。

第2章:求職者が“選ぶ時代”に変化した採用市場
整備士の採用が難しいと感じられる背景には、採用市場そのものの変化も大きく関係しています。以前は「企業が求職者を選ぶ」と考えられがちでしたが、今では「求職者が企業を選ぶ」時代に移りつつあるといわれています。
求職者が企業に関する情報を収集しやすくなっている
かつては企業が提示する求人票や会社案内が、求職者にとっての主な情報源でした。しかし現在は、インターネットやSNSの普及により、求職者が事前に多くの情報を得られるようになっています。
例えば口コミサイトや社員の発信から、職場の雰囲気や働きやすさを知りやすくなりました。そのため企業の説明だけではなく、外部から見た評価や社員自身の言葉が大きな判断材料となりやすいのです。
採用市場の「売り手優位」化
整備士の数が減少傾向にある中で、求人ニーズは高い状態が続いています。結果として、資格や経験を持つ整備士は複数の企業から声がかかることも珍しくありません。
求職者にとっては複数の選択肢があるため、自分に合った会社を比較検討できる状況にあります。つまり、条件や待遇だけでなく「ここで働きたい」と思わせる魅力が伝わらなければ、選ばれにくい時代になっていると考えられます。
働き方の価値観が多様化
近年は、働き方に対する価値観が大きく変化しています。安定や給与水準はもちろんですが、それ以上に「プライベートとの両立」「成長の機会」「安心して働ける職場関係」といったポイントを大切にする人が増えている傾向にあります。
特に若い世代ほど「自分に合った環境かどうか」を重視する傾向が強く、仕事内容よりも職場文化や雰囲気で応募を決める方も。企業はその視点を理解し、自社がどのような環境を提供できるのかを丁寧に示すことが重要です。
採用広報に求められる工夫
このような変化の中で、企業ができる工夫は「伝え方」を見直すことです。求人票に条件を並べるだけではなく、実際に働いている社員のリアルな声を届けることが求職者の安心感につながりやすくなります。
また、公式サイトやオウンドメディアを活用し、社員の働き方やキャリアパスを紹介することも効果的といえるでしょう。求職者が「自分の未来をイメージできる情報」を発信できれば、応募のきっかけにつながる可能性が高まります。
採用市場は、企業が求職者を選ぶ時代から、求職者が自分に合う職場を選ぶ時代へと変化しています。その中で整備士の採用を進めるためには、条件提示だけではなく「どのような職場で、どのような人と働けるのか」を具体的に伝える姿勢が重要です。
第3章:「社員の声」で採用力を強化するという発想
整備士の採用が難しいとされる背景には、求職者がさまざまな情報を見て企業を比較検討していることが挙げられます。そのため、企業が一方的に魅力を語るだけでは十分に伝わらない場合も。ここで注目されるのが「現場で働く社員の声」を活用した採用広報です。
社員の声が持つ説得力
求人票や会社案内に書かれている内容は、どうしても企業側の視点になりがちです。もちろん必要な情報ではありますが、求職者からは「本当のところはどうなのだろう」と疑問を持たれることもあります。
その点、現場で働く社員の声はリアルな体験に基づいているため、信頼性が高いと受け取られやすくなる場合も。実際に働いている人の言葉から「雰囲気」や「やりがい」が伝わることで、求職者は自分の将来を重ねやすくなります。
働きやすさや安心感を伝えやすい
整備士の仕事は専門性が高く、技術習得には時間がかかります。そのため求職者にとっては「成長できる環境があるか」「人間関係は良好か」といった要素が気になるポイントです。
こうした点は求人票だけでは伝えにくいもの。しかし、社員自身が「先輩が丁寧に指導してくれる」「困ったときに相談しやすい雰囲気がある」と語ることで、安心感を持ってもらいやすくなります。数字や条件では表しにくい“職場の空気感”を伝える手段として、社員の声は効果的といえるでしょう。
企業文化の共有につながる
社員の声を発信することは、単に求職者に安心してもらうだけでなく、自社が大切にしている価値観や文化を外部に示すことにもつながります。
例えば「技術の向上を重視している」「チームで協力することを大切にしている」といった言葉は、企業の姿勢を求職者に伝える大きな手がかりになるでしょう。これにより、自社の考え方に共感する人材と出会える可能性が高まります。結果として入社後の定着率向上に役立つ場合もあるのです。
社員にとってのメリットもある
さらに、社員の声を発信することは現職社員にとってもプラスの影響があります。自分の意見や経験が採用活動に活かされることで「会社に貢献している」という実感を得られることもあります。これは現職社員のモチベーションやエンゲージメント向上にも寄与する可能性があるのです。
第4章:現職社員の声を届けられるVOiCEの特徴
ここまで整備士の採用が難しい背景や、社員の声を活用する意義について触れてきました。実際に「社員の声をどう伝えるか」という場面で役立つのが、口コミプラットフォーム VOiCE です。
VOiCEは、現職で働く社員によるリアルな声や評判を集めたサービス。求職者にとって参考にしやすい現職社員のリアルな声を発信できる点が特徴です。ここではその具体的なポイントを整理します。
1. 現職社員のリアルな体験を発信できる
VOiCEでは、実際に働く社員が日常の業務や会社の雰囲気について発信できます。公式サイトや求人票では伝えにくい「働きやすさ」「人間関係」「成長機会」といった情報も、社員の体験談を通じて伝えられるのが大きな特徴です。
整備士を志す人にとって「先輩がどのような経験をしてきたのか」「技術をどう習得しているのか」といった情報は関心が高い部分です。そうした声を届けられることで、求職者が職場で働くイメージを描きやすくなります。
2. 透明性を高め、信頼につなげやすくする
採用活動では「会社が発信する情報」と「社員が語る情報」に差があると、不安を与えてしまうことがあります。VOiCEを活用すれば、第三者的な立場から社員の声を発信できるため、情報の透明性を高めやすいと考えられます。
透明性が高まることで「この会社は信頼できそう」と感じてもらえる可能性があり、応募への後押しになることも期待できます。
3. 応募前の不安軽減に役立つ
整備士を目指す人の中には「職場になじめるだろうか」「技術をきちんと学べるのか」といった不安を抱く方も多いでしょう。VOiCEに掲載された社員の声を読むことで、そうした不安を和らげる手助けになる場合があります。
応募前に安心感を得られれば、応募意欲の向上も期待できます。
4. 自社の強みを自然に発信できる
VOiCEで発信できる現職社員の声は、飾らない言葉で語られるものです。そのため企業が一方的に打ち出すよりも自然な形で、自社の魅力を伝えられます。
「教育体制がしっかりしている」「チームワークが良い」といった強みは、社員の実感を通じて伝えられることで、応募の検討に役立つ場合があります。
まとめ:整備士採用の難しさを踏まえた継続的な改善の重要性
自動車業界における整備士の採用は、慢性的な人材不足や資格要件の高さ、現場と求職者のイメージギャップなど、他業種にはない独自の課題があります。求人広告を出すだけでは応募が集まりにくく、せっかく採用しても早期離職につながるケースもあるでしょう。
しかし、情報発信の工夫や、社員のリアルな声を取り入れた取り組み、育成環境の整備などによって、少しずつ改善できる可能性があります。
整備士の採用で成果を上げるためには、一度きりの施策で解決を目指すのではなく、課題を定期的に見直し、自社の状況に合わせて施策をアップデートしていく姿勢が大切です。市場の変化や求職者の価値観に柔軟に対応しながら「働きたい」と思ってもらえる環境を整えることが、結果として採用力と定着率の向上につながることが期待できるでしょう。
VOiCEを採用広報に活かしてみませんか?
整備士採用を進める上で大切なのは「現場のリアル」を伝えることです。求職者は給与や待遇だけでなく、働く雰囲気や先輩社員の声を重視する傾向が強まっています。
その一助となるのが、社員による声を発信できる口コミサービス 「VOiCE」 です。
現職社員のリアルな言葉を求職者に届けることで、職場の雰囲気や働き方をより具体的に伝えられます。
「応募を増やしたい」「定着につながる採用をしたい」と考える企業にとって、VOiCEは採用広報の工夫に役立つツールのひとつです。
整備士の採用を改善したいと考えている方は、ぜひVOiCEの詳細をご覧ください。