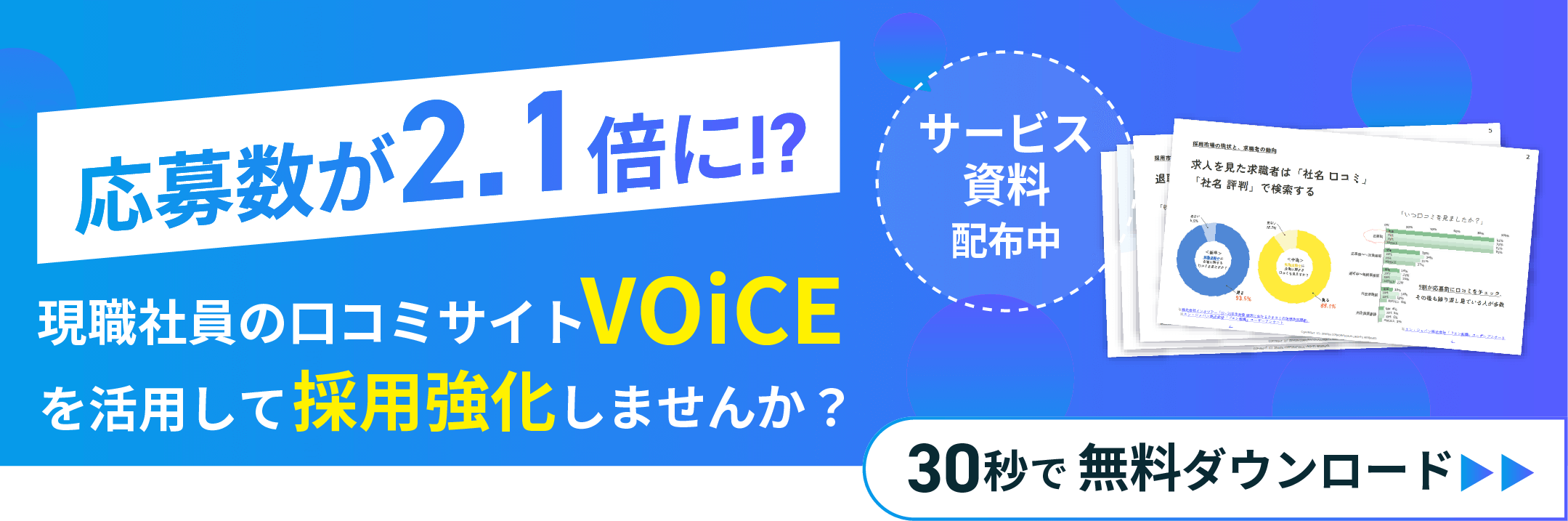“作られた感”が逆効果?
先輩の声を“リアル”に伝える採用広報のコツ
- 会社の評判
- 口コミ対策
- 採用活動
2025.09.12
採用活動において、応募者が特に注目するコンテンツのひとつが「先輩の声」です。
自社で働く社員の体験談やキャリアストーリーは、会社の雰囲気を伝えるひとつの手段。
しかし、形式的に整えすぎたインタビューや、企業目線で作られた記事は応募者に響きにくいものです。
むしろ「本当なのか?」と疑念を持たれる場合もあるかもしれません。
この記事では、応募者に刺さる「先輩の声」の作り方と、現場のリアルを活かした採用広報の工夫について解説します。
また、信頼性を高める方法のひとつとして、口コミサイト「VOiCE」の特徴もご紹介します。
第1章 なぜ「先輩の声」が採用において重要なのか?
応募者が知りたいのは「リアルな現場」
近年の求職者は、企業の発信する情報だけでなく、第三者の声を重視する傾向があります。
就職や転職は人生に関わる大きな選択であるため、応募者は「自分が入社して働く姿」を想像して決めたいと考えています。
そのときに参考になるのが「先輩の声」です。
働き方や人間関係、キャリア形成の実感が含まれた体験談は、求人票や会社概要では伝えきれない部分を補います。
企業ブランディングにも直結
先輩社員の声は、単に応募者の不安を減らすだけではありません。
社員の体験を共有することで「この会社は自分の成長を支えてくれるかもしれない」という期待感を高める効果が期待できます。
また、先輩の声を継続的に発信することで、企業の採用広報に一貫性が生まれます。
それは、応募数の増加だけでなく、企業ブランドそのものの強化にもつながるのです。
採用で重視される情報の信頼性と先輩の声
求職者は転職や就職を検討する際に、求人票や企業の公式情報だけでなく、社員のリアルな声を参考にするケースが多く見られます。
特に若手層や第二新卒は、仕事内容や人間関係に不安を抱きやすいため、実際に働いた人の声が意思決定を後押しする傾向も。
採用担当者にとって「先輩の声」は、求人広告や会社説明会と並ぶ重要な要素のひとつといえるでしょう。

第2章 よくある課題:採用サイトに掲載された“整いすぎた社員インタビュー”
形式的すぎる文章は応募者に響きにくい
多くの企業が採用サイトで社員インタビューを掲載しています。
「入社のきっかけ」や「やりがい」「将来のキャリア像」といった内容は定番といえるでしょう。
しかし、よくあるのがあまりにも整いすぎた文章です。
「入社してすぐに成長できました」「職場の雰囲気がとても良いです」といった表現ばかりが並ぶと、読み手は「本当にそうなのか?」と疑念を持ってしまいます。
応募者が知りたいのは、単にポジティブな面だけではありません。
現場で働く中での苦労や、そこをどう乗り越えてきたのかといったエピソードもまた、意思決定の参考になります。
一方的な企業目線になりやすい
採用広報で「先輩の声」を取り上げるとき、注意すべきは“発信の主体が企業寄りになってしまうこと”です。
広報担当者がインタビュー内容を取捨選択し、整えすぎると、どうしても企業に都合のよい内容だけが残ります。
結果として、応募者が「リアルさに欠ける」と感じ、かえって信頼性を損なってしまうこともあります。
採用サイトは公式情報である以上、ポジティブな側面が強調されやすいことは自然ですが、読み手の期待との間に生まれるギャップが課題でしょう。
“作られた感”が与える影響
求職者は近年、情報の信頼性に敏感になっている傾向が強まっています。
求職者の中には、SNSや口コミサイトの普及により、公式情報と現場の声を照らし合わせて判断する人も。
そのため、あまりに完成度の高いインタビュー記事は「宣伝用に作られたもの」と受け取られるリスクがあります。
応募者の不安を軽減するどころか「この会社は本音を見せていないのではないか」と逆効果になる恐れもあるのです。
応募者が知りたい「ちょっとしたリアル」
では、どのような内容が応募者にとって参考になるのでしょうか。
それは「等身大のエピソード」です。
例えば、
- 入社前は不安だったが、周囲のサポートで徐々に慣れた
- 失敗から学び、業務改善につなげた経験がある
- 先輩や上司の支えがモチベーションになった
こうした具体的な体験は、応募者にとって自分の将来像を描く材料になります。
また「大変なこともあるが、成長できる環境がある」というバランスの取れた内容であれば、かえって信頼感が高まる可能性があります。
採用広報における落とし穴
社員インタビューは効果的なコンテンツですが「整いすぎた内容」にしてしまうと逆効果になる可能性があります。
採用担当者は、ただ“良い部分を見せる”のではなく、“リアルな声をどう伝えるか”という視点を持つことが重要です。
次章では、こうした課題を解決するために欠かせない「作りもの感をなくす工夫」について解説します。
第3章 “作られた感”をなくすための工夫とは?
自然な言葉を引き出すインタビュー設計
「先輩の声」を掲載する際に重要なのは、答えを決めつけずに自然な言葉を引き出すことです。
あらかじめ質問項目を用意するのは有効ですが、形式的な問いかけばかりでは回答が似通ってしまいます。
例えば「仕事のやりがいは何ですか?」という質問に対して、多くの社員が「お客さまに感謝されたとき」と答えるかもしれません。
もちろんそれも事実ですが、応募者にとってはどこか抽象的に感じられるでしょう。
そこで「最近、達成感を得た具体的なエピソードは?」や「入社当初に大変だったことは?」といった質問を投げかけると、よりリアルな声が引き出せます。
言葉を整えすぎず、社員本人の表現を残すことも大切です。
ネガティブ要素を“前向きな学び”に変える
「リアルさ」を意識すると、どうしてもネガティブな内容が出てくることも。
例えば「残業が多くてつらかった」といったものです。
このような場合、事実を隠す必要はありません。
ただし、以下のように後の改善や学びにつなげて表現することで、読み手に安心感を与えられます。
- 「最初は業務量に戸惑ったが、チームで協力しながら乗り越えた」
- 「壁にぶつかったが、上司のサポートで解決できた」
応募者は“困難がまったくない会社”を求めているわけではなく、“挑戦を支える環境”を知りたいのです。
写真や動画を組み合わせて伝える
テキストだけでは「作られた感」が残ることもあります。
そこで有効なのが、写真や動画の活用です。
実際の職場風景や打ち合わせの様子を映すことで、文章以上に「等身大の雰囲気」が伝わります。
特に動画は、社員の表情や話し方から誠実さが伝わるため、応募者に親近感を与えやすいです。
ただし、ここでも演出過剰にならないことが大切。
過度に演技を強調した映像は、かえって信頼感を下げる可能性があります。
自社サイトと外部の情報を組み合わせる
採用サイトに掲載する「先輩の声」は公式情報であるため、どうしても内容が整理されがちです。
だからこそ、外部の口コミ情報と組み合わせて発信することが効果的。
口コミサイトでは、社員のリアルな声が自由に投稿されます。
公式サイトでは書きにくいリアルな部分が示されることで、応募者はバランスを取って判断できるのです。
自社サイトの情報と外部の情報を併用することで「企業が隠していない」という印象を与えられる点は大きなメリットになるでしょう。
“リアル”をどう設計するかが鍵
「先輩の声」は、単にインタビュー記事を掲載するだけでは十分ではありません。
自然な言葉を引き出し、ネガティブ要素も前向きに整理して、外部の情報もうまく取り入れることが重要です。
応募者は、“企業の整った姿”よりも、“現場のリアルを隠さず伝える姿勢”に信頼を感じやすいです。
その結果、入社後のギャップを減らし、定着率向上の効果も期待できます。
次章では、こうしたリアルな声を手軽に活用できるサービス「VOiCE」の特徴をご紹介します。
第4章 現職社員のリアルな声が見られるVOiCEの特徴
これまで解説してきたように「先輩の声」を活用する採用広報では“リアルさ”が重要です。
ただし、企業が自ら発信する情報には限界があります。
採用サイトは公式な場である以上、ネガティブな面をそのまま掲載するのは難しいものです。
一方で、応募者は「社員のリアルな声」を参考にしながら判断する傾向が強まっています。
そこで活用できるのが、現職社員の「今ここにいる理由」を届ける口コミサイト「VOiCE」です。
VOiCEとは
VOiCEは「現職で働く社員によるリアルな声や評判を集めた口コミサイト」です。
多くの口コミサイトでは、退職者の意見も含まれるため、どうしても過去の情報や、ネガティブな内容が目立ちやすい傾向があります。
それに対してVOiCEは、現職社員のみに限定して声を集めているため、応募者は「今まさにそこで働いている人の声」を参考にできるのです。
これは、求職者が過去の情報に左右されにくく、今の職場の様子を理解しやすくなることが期待できます。
採用担当者にとってのメリット
VOiCEは応募者だけでなく、採用担当者にとってもメリットがあります。
- 信頼性の高い情報を提供できる
現職社員の声に限定しているため、鮮度の高い情報を応募者に届けやすくなります。
また「企業が隠していない」という姿勢を示すことで、信頼感を高める効果が期待できます。 - 情報発信の工数を削減できる
自社で社員インタビューを制作するには時間とコストがかかるでしょう。
VOiCEに集まる声を活用すれば、既存の広報活動を補完しながら効率的に情報を発信できます。 - 入社後のギャップを防ぎやすい
現職社員による等身大の声が集まるため、応募者は入社後の働き方をより具体的にイメージしやすくなります。
その結果「思っていたのと違った」というギャップを減らし、定着率向上につながる可能性があります。
応募者が信頼できる情報のかたち
従来の採用サイトでは「作られた感」が出やすく、応募者の信頼を得にくいことも。
VOiCEのように現職社員の声に絞ることで、第三者性を保ちつつ、鮮度の高いリアルな情報を提供するのに役立ちます。
また、社員本人の言葉は、同世代の応募者にとって特に共感を呼びます。
「先輩の声」を公式サイトとVOiCEの両方で示すことで、応募者はより納得感を持って判断しやすくなるでしょう。
VOiCE活用で広がる採用広報の可能性
VOiCEは単なる口コミサイトではなく、現職社員の声を通じて企業と応募者をつなぐプラットフォーム です。
自社サイトでの発信と組み合わせることで、採用広報における「リアルさ」と「信頼性」を両立できます。
「先輩の声」を採用活動に効果的に取り入れたいと考える企業にとって、VOiCEは有効な選択肢のひとつといえるでしょう。
まとめ
「先輩の声」を採用活動に取り入れることは、応募者に安心感を与え、企業理解を深めてもらう上で有効です。
ただし、整いすぎた情報はかえって信頼を損ねる可能性があるため、リアルさを意識した工夫が重要。
その上で、外部の口コミサイト「VOiCE」を活用すれば、企業の公式情報だけでは伝えきれない現場の声を補完する手助けになります。
結果として、応募者は納得感を持って応募しやすくなり、企業側も入社後の定着率向上につなげられる可能性があるのです。
採用広報に「先輩の声」を効果的に取り入れたいと考えている企業の方は、ぜひVOiCEを活用してみてはいかがでしょうか。