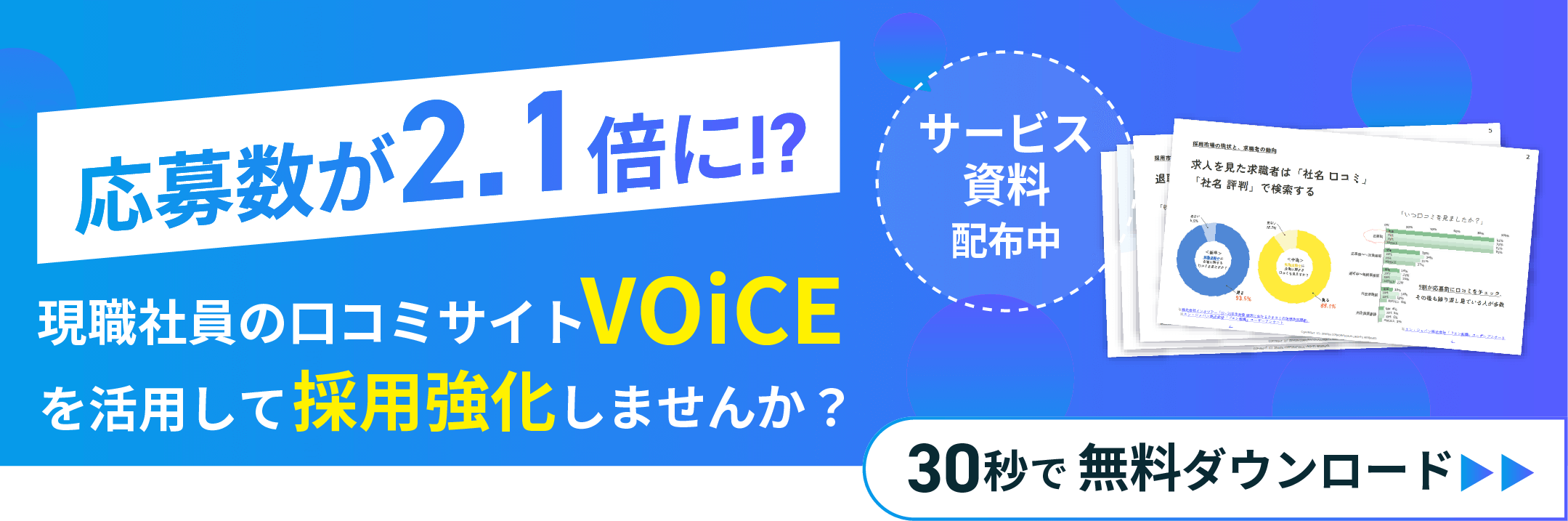社員の定着率を高めるには?
人事担当者が押さえるべき実践的なアプローチ
- 口コミ対策
- 採用ミスマッチ
- 離職防止
2025.09.12
社員の定着率は、企業の成長に直結する重要な課題です。
せっかく採用した人材が早期に退職してしまうと、採用にかけた時間や費用が十分に生かされないだけでなく、現場の生産性やチームのモチベーションにも影響します。
さらに、定着率の低下は採用における企業の信頼性にも影響があるのです。求職者は求人票だけでなく口コミやSNSを通じて企業の雰囲気を調べるようになっており、退職者が多い職場は慎重に見られる傾向があります。
本記事では「社員の定着率」という観点から、企業に及ぶ影響や定着率が上がらない原因を整理します。さらに、入社前後のギャップを埋めるための取り組みや、企業の魅力を正しく伝える方法についてもご紹介します。
第1章:定着率が低いとどうなる?企業に及ぼす4つの影響
社員の定着率が低い状態が続くと、企業にはさまざまな影響が及びます。ここでは代表的な4つの側面を解説します。
1. 採用コストの増大
人材を採用するには、求人媒体の掲載費用、説明会や面接にかかる人件費など多くのコストが発生します。
せっかく採用した人材が短期間で辞めてしまうと、投資したコストを回収できません。結果として、新たな採用活動を繰り返す必要が生じ、コストが増加します。
2. 現場の生産性低下
新しい社員が業務に慣れるまでには時間がかかります。定着率が低いと常に新人が入れ替わる状態となり、教育にかける負担が増えることも予測できるでしょう。
また、経験者が育つ前に退職してしまうことで、現場のノウハウが蓄積しづらくなり、チーム全体の生産性も下がる可能性があります。
3. 既存社員の負担増
退職者が出ると、その穴を埋めるために既存社員への業務負担が大きくなります。
結果として長時間労働が増え、さらに離職を招くという悪循環に陥るケースも少なくありません。こうした状況を防ぐために定着率を高めることは、働く人の安心感を守り、継続して働き続けてもらう意欲の向上にもつながります。
4. 企業イメージへの影響
求職者は求人票だけでなく、口コミサイトやSNSを通じて企業の雰囲気を調べています。定着率が低い企業は「働き続けるのが難しい職場」という印象を与えやすく、応募数が減る可能性があります。
採用広報を強化しても、現場の実態が伴っていないと信頼を築きにくくなるでしょう。定着率は外部への発信力にも直結する問題といえます。

第2章:社員の定着率が上がらない5つの主な要因
定着率を高めたいと考える企業は多いですが、現実には思うように成果が出ないことも少なくありません。
ここでは、社員が早期に離職してしまう主な要因を5つに整理して解説します。
1. 入社前後のギャップ
多くの企業で見られるのが「入社前に抱いたイメージ」と「実際の働き方」との違いです。
例えば、求人票には「チームワークを大切にする」と書かれていても、実際は「個人主義が強く助け合いが少ない」と感じてしまうケースがあります。
このような認識のずれが続くと「思っていた職場と違う」という違和感につながり、早期退職の大きな要因になります。
企業としては、ポジティブな情報だけを発信するのではなく、現実に近い働き方や社員の声を伝えることが大切です。入社前のギャップを減らすことが、結果的に定着率向上にもつながるでしょう。
2. キャリア形成の不透明さ
将来的にどのようなキャリアが描けるのかが見えにくいと、社員の長く働く意欲を低下させる要因になる可能性があります。
特に若手社員は「どのようなスキルが身につくのか」「次のステップに進めるのか」を重視する傾向が強いため、キャリアの道筋が不明確だと不安を抱きやすいのです。
評価制度や昇進のルールを明確にすることで、社員は将来像を描きやすくなります。キャリア支援の仕組みを整えることは、短期離職を防ぐ重要な要素のひとつといえるでしょう。
3. コミュニケーション不足
職場での人間関係や上司とのコミュニケーションが不足していると、社員は孤立感を抱きやすくなります。
相談できる相手がいないと小さな不安や不満が積み重なり、結果的に退職を検討する引き金になることも。
最近はリモートワークやハイブリッド勤務が増え、気軽な雑談の機会が減少している傾向にあります。こうした状況では、オンラインでの1on1や定期的なフォロー面談を設けるなど、意識的に接点をつくることが大切です。
4. 労働環境のミスマッチ
勤務時間や休日制度、給与水準などが社員の希望と合わない場合、定着は難しくなります。
特にライフスタイルの多様化が進む中で、柔軟な働き方や福利厚生の充実を重視する人材は増えています。
要望を満たすのが難しい場合は、労働環境の改善に取り組む姿勢を見せるだけでも社員の安心感につながるでしょう。制度を少しずつ改善することが、離職防止にもつながります。
5. 評価と承認の不足
「努力がきちんと認められていない」と感じると、社員のモチベーションは下がります。
成果を上げてもフィードバックがなかったり、評価が不透明であったりすると、仕事への意欲が薄れてしまうのです。
評価制度を整備するだけでなく、日常的に「ありがとう」や「助かった」といった言葉を伝えることも重要です。評価を受けた経験は、社員にとって働き続ける理由のひとつになります。
要因の重なりが離職を生む
これらの要因はひとつだけ生じるのではなく、複合的に影響し合うことが多いです。
例えば「入社前後のギャップ」と「キャリアの不透明さ」が重なると、社員は「この会社にいても成長できないのではないか」と感じやすくなります。
同様に「コミュニケーション不足」と「評価の欠如」が続くと、孤立感が強まり、モチベーション低下を招く可能性も。
企業としては、表面的な対策だけではなく、複数の要因を俯瞰して改善に取り組む必要があります。定着率を高めるには、職場環境と情報発信の両面からの見直しが大切です。
第3章:求職者は“職場のリアル”を口コミや検索で見ている
採用活動において、企業が発信する情報はこれまで以上にチェックされやすくなっています。
特に求職者は、求人票や公式サイトだけでは判断せず、口コミやSNSなど「第三者の声」を参考にする傾向が強まっているのです。
こうした情報収集行動は、採用後の社員の定着率にも密接に関わります。
求職者は企業の「リアル」を知りたい
従来の就職・転職活動では、企業が伝える強みや福利厚生が応募の判断材料でした。
しかし現在は「実際に働いている社員がどう感じているか」に関心を寄せる人が増えています。
求職者は公式情報とあわせて口コミを調べることで、入社後の働き方をできるだけ具体的に想像しようとしているのです。
例えば、残業時間や人間関係といった日常的な部分は求人票に細かく書かれにくいものです。
そのため「実際の声」に触れることで、安心感を得ようとする動きが広がっている傾向にあります。
検索行動に表れる“情報の取り方”
求職者の行動を見てみると、応募前に「企業名+口コミ」「企業名+評判」といった検索を行うケースが目立ちます。
また、転職系サイトやSNS、掲示板など複数の情報源を見比べる傾向も強まっています。
検索結果にポジティブな情報が並んでいれば安心感が高まりますが、ネガティブな体験談が目立つと不安を抱きやすくなるでしょう。
そのため、企業にとっては「どのような情報が外部から見られているか」を把握することが重要です。
情報ギャップが応募意欲に影響する
公式サイトでは魅力的なキャリア支援制度を紹介していても、口コミで「制度はあるが使いにくい」といった声が広がっていれば、求職者は不安を感じやすくなります。
一方で「面倒見の良い上司が多い」といったポジティブな声が外部に出ていれば、応募意欲は高まります。
つまり、情報に一貫性があるかどうかが応募者の判断につながるのです。
ここでのギャップが大きいと「入社後もミスマッチがあるのでは」と考えられやすく、結果的に定着率の低下にも影響する可能性があります。
求職者が口コミを重視する背景
なぜこれほどまでに口コミや評判が重視されるようになったのか。
その理由のひとつは、労働観の変化にあります。働く人は「長く安心して働けるか」「自分らしく成長できるか」といった視点を重視する傾向にあります。
その判断には、企業が発信する理想像よりも「現場の実態」に近い情報のほうが信頼されやすいのです。
また、SNSの普及により情報収集が容易になり、短時間で複数の体験談を比較できるようになったことも影響しています。
企業が意識すべきポイント
こうした状況を踏まえると、企業は「口コミが拡散されること」を前提に採用戦略を考える必要があります。
一方で、口コミは企業がコントロールできるものではありません。
だからこそ、社員の声を誠実に拾い上げ、発信の場を整えることが重要です。
求職者が目にする情報と実際の職場が一致していればいるほど、入社後のギャップは小さくなります。これは結果として、社員の定着率を高める効果も期待できるのです。
リアルな情報が定着率を左右する
求職者が応募を決める際には、企業の魅力そのものより「実際の働き方との一致感」が重視される傾向が強まっています。
職場のリアルが伝わる情報を整えることは、単なる採用広報ではなく、定着率改善のための基盤づくりといえるでしょう。
第4章:入社前にギャップを埋めることが大事
社員の定着率を高めるためには、入社後のサポートや制度整備も欠かせません。
しかし、それ以前に「入社前からの情報発信」でギャップを小さくしておくことが、効果的な取り組みのひとつといえます。
ギャップがもたらす離職リスク
多くの離職理由の中で「想像していた職場と違った」という声は珍しくありません。
仕事内容、職場の雰囲気、評価の仕組みなど、事前に知るのが難しい情報ほどミスマッチが起きやすいのです。
その結果、モチベーションが低下し、入社から数ヶ月で離職を選択してしまうことも。
企業が誠実に情報を伝えることで、こうしたリスクは減らせます。
入社前の段階で「この会社で働くイメージ」が具体的に描ければ、定着率は高まるでしょう。
リアルな情報提供の重要性
求人票や採用サイトでは、どうしてもメリットを中心に伝えがちです。
もちろん企業の魅力を発信することは大切ですが、過度に理想化された情報は後のギャップを大きくしてしまいます。
例えば「残業が少ない」と紹介しても、繁忙期には一定の残業が発生するのであれば、その点を明示しておくほうが安心につながります。
「制度はあるが利用しにくい」といった状況があるなら、改善に取り組んでいる姿勢を示すだけでも印象は変わります。
つまり、強みと同じくらい「ありのままの現状」を共有することが、結果的に信頼構築につながるのです。
社員の声を活用する
入社前の情報発信で特に有効なのが、現場で働く社員の声を紹介することです。
実際に働く人がどのように感じているかを知ることで、求職者は「自分がこの職場に入ったらどうなるか」をイメージしやすくなります。
具体例としては、社員インタビューや座談会記事、あるいは口コミを集めたプラットフォームを活用する方法も考えられるでしょう。
こうした取り組みは「会社が社員の声を大切にしている」という姿勢を示すことにもつながります。
採用担当者の役割
採用担当者は、単に応募者を集めるだけではなく、入社後を見据えて情報の一貫性を保つ役割も担います。
面接や説明会で伝える内容が、入社後の実態とかけ離れていると、不信感を生みやすくなるためです。
だからこそ、現場の社員と連携しながら「今の職場を正しく伝える」ことが重要です。
採用担当者が橋渡し役となり、企業の魅力と課題の両方を丁寧に発信していく姿勢が今後より求められるでしょう。
ギャップを埋めることが定着率を高める
入社前からリアルな情報を届け、期待と現実の差を小さくしておくことは、定着率向上に影響します。
「知っていた上で選んだ職場」であれば、入社後に困難があっても乗り越えやすくなるのです。
一方で、過度に良い面だけを強調してしまうと、小さな違和感が積み重なりやすく、結果的に離職につながりやすくなります。
つまり、採用の段階でいかにギャップを埋められるかが、社員定着の分岐点になるといえるでしょう。
第5章:社員の声を活かす――VOiCEの特徴
入社前のギャップを小さくするためには、企業自身の発信に加えて「現職社員の声」をどのように届けるかが重要です。
そこで活用できるサービスのひとつが VOiCE です。
VOiCEとは
VOiCEは、現職で働く社員によるリアルな声や評判を集めた口コミサイトです。
一般的な口コミサイトは、退職者や不満を持った人の意見が目立つ場合があります。
一方、VOiCEでは現職社員が実際に感じている働きがいや社内環境について、前向きな視点から情報を共有しています。
そのため、求職者は「今この会社で働いている人の声」に触れられ、入社前後のギャップを埋めやすくなります。
VOiCEの特徴
VOiCEには、以下のような特徴があります。
- 現職社員の声を反映
転職者や退職者ではなく、現場で働く人の意見を知れます。 - ポジティブな体験談を中心に掲載
働きやすさややりがいに関する実感がまとめられており、求職者が職場のイメージを具体的に理解しやすくなります。 - 企業の情報発信を補完
求人票や採用サイトで伝えきれないリアルな声を届けられるので、採用広報の一助として活用できます。
入社前の情報整理や職場理解に役立つ活用法
VOiCEに掲載された社員の声は、入社前に「働くイメージ」を持ってもらうための参考情報になります。
ギャップを減らすことで、入社後の定着を支える効果が期待できます。
また、社員自身が発信に関わることで「自分の声が会社に活かされている」という意識が芽生え、既存社員のエンゲージメント向上にもつながります。
これは結果的に、既存社員の定着にも良い影響を与えるのです。
まとめ
社員の定着率を高めるためには、制度改善やキャリア支援といった社内施策だけでなく、採用段階での情報発信が欠かせません。
特に「入社前後のギャップ」を小さくすることが、離職を防ぐ大きなポイントになります。
VOiCEは、現職社員の声を通じて職場のリアルを伝えられるサービスです。
求職者の不安を減らし、安心して入社を決めてもらうことで、定着率向上に役立つ可能性があります。
社員が長く安心して働ける職場をつくりたいと考える経営者・人事担当者の方は、ぜひ一度VOiCEをご検討ください。