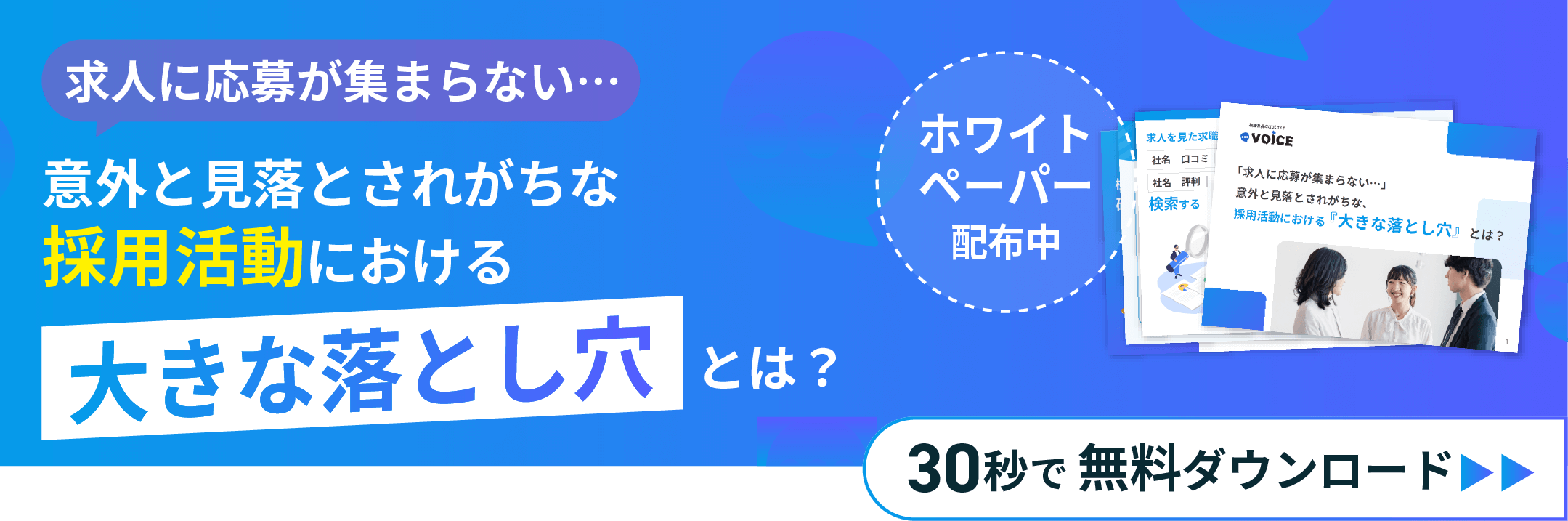新卒からの応募が来ない…なぜ?原因と今すぐ見直すべき採用広報のポイント
- 採用強化
- 採用活動
- 採用課題
2025.08.19
「新卒採用の募集を始めたのに応募が思うように集まらない」──こうした悩みを抱える企業は少なくありません。
近年は学生が企業を知る手段が増え、就職活動のスタイルも以前とは変わりつつあります。
そのため、企業が求人を出すだけでは、学生に見つけてもらうのが難しい状況になっているのです。
また、新卒が企業を選ぶ基準も多様化しています。
給与や勤務地といった条件面に加えて、働き方や成長の見通し、社風や人の雰囲気など、より具体的な情報を手がかりに比較検討する傾向があります。
こうした判断軸の変化に対し、従来型のアプローチだけでは魅力が伝わりにくいケースも見られます。
そこで本記事では「新卒の応募が来ない」と感じる背景を整理し、企業が見直しやすい採用広報のポイントをまとめました。
学生の視点に沿った情報発信を行うためのヒントとして、日々採用に向き合う経営者や人事担当者の方に役立つ内容をお届けします。
新卒応募が来ない理由:企業に共通する課題
1. 企業や求人が知られていない
新卒応募が伸びにくい理由のひとつに、学生との接点そのものが不足している点があります。
知名度だけでなく、情報発信のタイミングや媒体選びによっても学生に届きづらくなることがあります。
合同説明会への参加頻度が少ない、SNSでの発信が弱い、採用ページの更新が止まっている。
こうした状況では、そもそも企業の魅力に触れてもらう機会が十分に確保できず、認知段階でつまずきやすくなります。
このように、企業の魅力を伝える“場”や“導線”が整っていないことも、学生に気づいてもらえない要因のひとつです。
2. 求人情報が学生にとって“分かりにくい・魅力が伝わりづらい”
採用ページに必要な情報が掲載されていても、学生が知りたい順序で整理されていないと情報を理解しにくく、応募に結びつきにくくなります。
特に以下のような項目が曖昧だと、学生は不安を感じやすくなります。
- 具体的な仕事内容
- 入社後の成長ステップ・キャリアの流れ
- 教育・サポート体制
情報量が問題なのではなく「どのように伝えるか」が学生の理解度と応募意欲を左右するといえます。
3. 発信チャネルが限られており学生に届いていない
学生は就職ナビ、SNS、口コミ、動画、先輩の紹介など、複数のチャネルから企業情報を集めています。
しかし企業側の発信が採用ページやナビサイトに偏っていると、学生が普段触れる導線に情報が出ていない状態となり、結果として選択肢に入らないこともあります。
せっかく魅力があっても、発信経路が限定的だと“知ってもらう前に”機会損失が生まれやすくなるのです。
4. 求人票が抽象的で仕事内容やキャリアが具体化されていない
求人票が抽象的だと、学生は仕事内容を自分ごととして捉えにくくなります。
よくあるのは、
- 「成長できる環境です」
- 「幅広い業務を担当します」
- 「チームワークを大切にしています」
といった抽象度の高い言葉だけになってしまうケースです。
例えば、学生が知りたいのは「実際の1日の流れ」「入社後数年でどのように活躍できるのか」「求められる役割の具体像」など。
このような具体的なイメージを持てないままでは、学生側も応募判断が難しくなる場合があります。
5. 会社の雰囲気・働く人のリアルが伝わらず不安を感じやすい
学生は「どのような人が働いているのか」「職場の雰囲気は合いそうか」を重視する傾向にあります。
しかし多くの企業では、この“リアル”が十分に発信しきれておらず、安心材料が足りない状態になっているケースもあります。
また、社内の雰囲気や価値観、働く人の姿が見えないと、企業理解が浅いまま比較検討に進み、結果的に他社に流れてしまうこともあります。
学生が抱く“入社後の不安”を減らすためには、企業側が情報の透明性を高め、働く人の声や具体的な環境をきちんと提示することが求められるといえます。

新卒が企業を選ぶ基準は?応募につながるポイントを解説
1.仕事内容と成長イメージ
学生が企業を検討する上で、大きな関心を寄せるのが「入社後にどのような仕事をするのか」「どのように成長できるのか」という点です。
仕事内容の流れ、配属先のイメージ、任される業務の具体例が整理されていると「自分が働く姿」を想像しやすくなります。
また、近年はキャリアの展望への注目も高まっている傾向にあります。
- 研修期間はどれくらいか
- 何年後にどのような役割に挑戦できるのか
- キャリアステップにどのような選択肢があるのか
こうした情報があると、学生は将来像を描きやすくなり、応募の後押しにつながる可能性があります。
2. 職場の雰囲気・社員の人柄
仕事内容以上に「どのような人と働くのか」を重視する学生も増えています。
そのため、先輩社員の声、社内コミュニケーションの取り方、新人と先輩の関わり方などが分かると、入社後のイメージが具体的になります。
数字や制度だけでは伝わりにくいため、
- 社員インタビュー
- 日常の写真
- イベントの様子
など、人の雰囲気が伝わる情報が学生の安心感につながりやすくなります。
3. 働きやすさ・制度
給与や休日といった条件面に加えて、最近では 「働きやすさがどう実現されているか」 が重要視されている傾向も見られます。
学生が特に注目するのは、
- 有休取得率
- 平均残業時間
- 在宅勤務やフレックスの有無
- 研修・資格支援などの学びの機会
といった“環境面のリアル”です。
こうした働きやすさが見えることで「長く働ける職場かどうか」を判断しやすくなります。
4. 企業の理念・価値観
企業の価値観や社会への姿勢も、学生が比較検討する際の大切なポイントです。
例えば、環境への取り組み、地域との関わり、ダイバーシティ推進など、社会的な姿勢は学生にとって共感を生みやすい要素になります。
企業の理念やミッションが分かりやすく示されていれば、学生自身の価値観と重なる部分を見つけやすくなり、応募先として意識されやすくなります。
特に「リアルな情報」へのニーズが年々強まっている
これらの項目に共通するのは、“リアルで具体的な情報を求める学生が増えている”という点です。
制度や福利厚生の説明だけではなく、実際に働く人の声、日々の仕事の姿、現場の空気感。
こうした“等身大の情報”があるほど、学生は安心して企業を比較でき、応募意欲も高まりやすくなります。
応募が集まる企業の共通点は「情報の具体性」と「透明性」
学生の就職活動が多様化する中で、応募が集まる企業にはいくつかの共通点があります。
応募が集まる企業は、特別なPR施策ではなく、求職者が安心して応募できる「具体的で透明性のある」情報を丁寧に提示している傾向にあります。
抽象的なPRより“働く人の声”が判断材料になる
企業理念やミッション、魅力のまとめといった抽象的なPRだけでは、学生に伝わりにくいことがあります。
代わりに、実際に働く社員の声や体験談、日々の仕事のリアルなエピソードは、学生にとって参考になる情報のひとつです。
- 仕事のやりがい
- つまずきやすいポイント
- 働き方の工夫
- チームの雰囲気
こうした「その会社で働く姿が具体的に想像できる情報」は、企業選びの重要な判断材料となり得ます。
社風・日々の働き方・若手社員の実例などが重要
応募を後押しするのは、制度や待遇だけではありません。
学生が知りたいと感じているのは、
- 若手社員がどのようなキャリアを歩んでいるのか
- 毎日の働き方はどのようなものか
- 配属後にどのようなサポートを受けられるのか
- チームのコミュニケーションはどのような雰囲気か
といった、“社内の空気感”に近い情報です。
これは企業側から見ると伝えづらい側面かもしれませんが、学生にとっては「自分に合う職場か」を判断する上で重要なポイントといえます。
“安心して応募できるだけの材料”を提示している企業が強い
応募が集まりやすい企業には、共通して見られる傾向があります。
具体的には、学生が不安に思いやすい点を丁寧に説明し「この会社なら働くイメージが持てる」と感じてもらう工夫をしています。
さらに、企業・学生双方が同じ情報を見ながら期待値をすり合わせられる状態をつくることで、応募につながりやすくなるだけでなく、入社後のミスマッチも防ぎやすくなります。
したがって、近年は“リアルで具体的な情報”をどれだけ提供できるかが、採用成功の大きな鍵といえるでしょう。
新卒に伝わる採用広報の3ステップ
新卒の応募につながる採用広報は、特別な仕掛けが必要なわけではありません。
重要なのは、学生が知りたい情報を整理し、理解しやすく見せ、適切なチャネルを通じて届けることです。
ここでは、今すぐ見直せる3つのステップをご紹介します。
1. まず“学生が知りたい情報”を整理する
採用広報の第一歩は、企業側が伝えたいことではなく、学生が最初に不安に感じやすい項目から整理することです。
特に新卒は社会経験がないため「働くイメージ」が湧く情報ほど価値があるといえます。
- 仕事内容の具体例(1日の流れ、担当業務の詳細)
- キャリアステップの実例(入社1年〜3年のモデルケース)
- 研修・成長支援制度の実態(期間・内容・フォロー体制)
- 職場の雰囲気(チーム構成、コミュニケーションの特徴)
- 働き方・制度の使われ方の実例
これらは条件を並べるだけでは不十分で「自分がここで働くとどうなるか」を想像できる流れで整理することが鍵になります。
2. 情報の“見せ方”を工夫する
学生にとって重要なのは、情報そのものよりも、どのように見えるか・どれだけリアルかです。
文章だけでは伝わりにくい内容は、以下のような形で補強すると理解が深まりやすくなります。
効果的な見せ方の例
- 写真・動画:オフィスの様子、働く姿、社内イベント
- 社員インタビュー:若手が語る仕事のリアル、やりがいと苦労
- 1日のスケジュール:業務量や働くスタイルのイメージを可視化
- キャリア実例:年次ごとの成長ステップや挑戦の機会
- 働き方の実際:「残業時間の目安」「制度が使われているか」などの具体例
特に新卒が求めるのは「リアルで嘘のない情報」です。
そのため、等身大の若手社員の声を盛り込むと、応募を後押しする可能性があります。
3. 発信チャネルを複数化し“接点”を増やす
どれだけ良い情報をまとめても、学生に届かなければ効果は見込めません。
そのため、採用サイトだけに頼らず、複数チャネルを併用することで、学生との接点は広がります。
主な発信チャネル
- 採用サイト・コーポレートサイト
- SNS(Instagram、Xなど):日々の取り組み・社員紹介の発信
- スカウトサービス:個別接点で認知を広げる
- 口コミ・社員レビュー:第三者視点で信頼性を補強
- オンラインイベント・学内説明会
学生が日常的に触れる場にも情報が流れていることで「この企業、よく見かける」「雰囲気が分かる」という印象が自然に蓄積されていきます。
このように“接点を増やす”ことは、採用広報における再現性の高い施策のひとつです。
学生に伝わる採用広報と「VOiCE」の活用
学生に企業の魅力を伝えるためには、制度や条件の説明だけでなく、日々の働き方や職場の雰囲気といった“実際の体験に近い情報”も補足することが欠かせません。
そこで、情報の透明性を高める方法のひとつとして、現職社員の声を可視化できる「VOiCE」を採用広報に取り入れることも可能です。
社員の声を整理して“見える化”できる
VOiCEでは、働く人のリアルな声を収集・整理して掲載できます。
採用ページでは伝えきれない働き方・価値観・雰囲気などが言葉として残るため、学生が具体的にイメージしやすくなる補助となります。
社員発信ベースで企業文化を伝えやすい
企業が公式に発信する情報とは別に、VOiCEでは社員目線でどのような点に魅力を感じているのかを発信できます。
そのため「どのような人が働いているのか」「どのような空気感があるのか」を補足しやすくなります。
制度や数字だけでは伝わらない“温度感”の補強に役立つこともあります。
学生が気にしやすいポイントを補足できる
多くの学生が重視する「職場の雰囲気」「人間関係」「成長環境」などは、文字情報だけでは伝えにくい項目です。
複数の社員の声が集まることで、こうした点を比較・理解しやすくなることが期待できます。
採用ページの補完として活用しやすい
VOiCEは独立した口コミプラットフォームのため、採用サイト・会社説明会資料・SNSなど、既存の広報チャネルと組み合わせて利用されることもあります。
このように「公式情報+社員の声」という複数の視点がそろうことで、情報が立体的になり、学生が企業研究を進めやすくなる場合があります。
まとめ:応募が来ない原因の多くは“伝え方”にある
学生の応募判断は、情報の「量」だけでなく「伝わり方」にも大きく左右されます。制度や条件だけでは補いきれない部分があるからこそ、働く人の声や日々の雰囲気など、就活生が気にしやすいポイントを分かりやすく可視化する工夫が求められます。
そのひとつの方法として、社員の声や第三者的な視点を採用広報に取り入れるケースも増えています。
公式情報だけでは伝えづらい“働くイメージ”が補足されることで、学生が企業理解を深めやすくなる可能性があります。
結果として、情報の透明性が高まる採用広報は、応募数の増加だけでなく、学生とのミスマッチを防ぎ、より納得度の高いマッチングにつながることが期待できます。
採用広報は、大きな改革をしなくても、まずは「何を、どのように伝えるか」を見直すところから始められます。
社員の声の整理や、伝え方の工夫といった小さな取り組みが、将来の採用成果につながっていくでしょう。