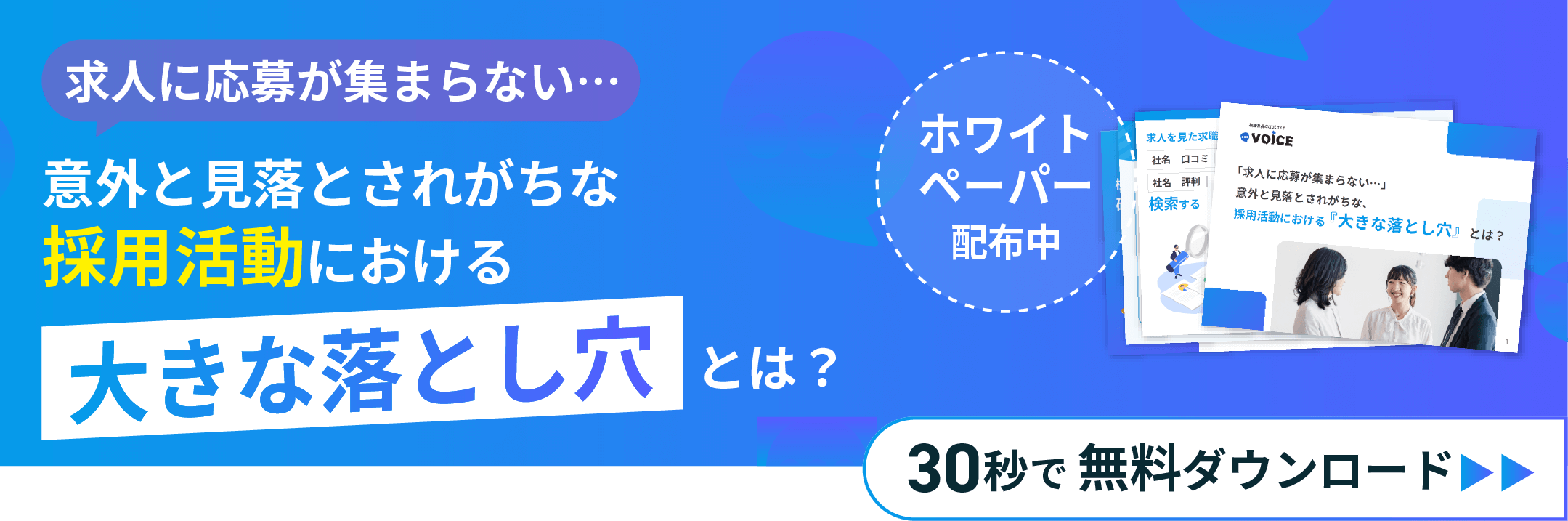第二新卒が早期離職しやすい理由とは?企業が取るべき対策を解説
- 採用強化
- 採用課題
- 離職防止
2025.08.17
即戦力として期待される第二新卒は、社会人経験を持ちながらもまだ若く、柔軟性や学習意欲が高いという特徴があります。そのため、企業にとって早期から一定の戦力として活躍が期待できる人材です。一方で、入社後すぐに離職してしまう「早期離職」のリスクも存在します。特に、仕事内容や職場環境が本人の期待と合わなかった場合、あるいはキャリアの方向性を模索している段階であった場合、早期離職につながりやすいのが現状です。
本記事では、第二新卒が早期離職しやすい背景を整理し、企業が取り組める具体的な対策を分かりやすく解説します。
第1章:第二新卒とは?特徴と早期離職の背景
第二新卒の定義と市場での位置づけ
「第二新卒」とは、一般的に新卒で入社してから数年以内に転職活動を行う若手社員を指します。明確な年数の定義は企業や調査によって異なりますが、概ね入社後3年以内の社員が対象となることが多いです。新卒と比べると社会人経験があるため、基本的なビジネスマナーや業務スキルを備えており、即戦力として採用されやすい傾向があります。
採用市場において第二新卒は、新卒と中途の中間に位置する層です。新卒の柔軟さと中途の実務経験の両方を兼ね備えているため、注目される傾向にあります。一方で、若手層であるためキャリアの方向性が定まっていない場合もあり、採用後に早期離職してしまうケースがあることも事実です。
第二新卒の特徴
第二新卒には、いくつかの共通した特徴があります。まず、学習意欲や柔軟性が高いこと。新卒での経験を通じて業務の基本を学んでおり、異なる職場環境や新しいスキルの習得にも比較的スムーズに適応しやすいです。また、社会人経験を持つことで、基本的なビジネスマナーや職場でのコミュニケーション能力を備えている場合が多く、入社後の研修や教育コストを抑えやすいメリットがあります。
一方で、キャリアの方向性や職場に対する価値観がまだ固まっていないため、理想と現実のギャップに敏感です。仕事内容や職場の雰囲気、人間関係が自身の期待と合わない場合、早期離職を検討するケースもあります。
第二新卒が早期離職しやすい理由
第二新卒が早期離職しやすい背景には、いくつかの要因があります。
(1)期待と現実のギャップ
第二新卒は入社時に、即戦力としての活躍を期待されることが多いです。しかし、実際の業務内容やチームでの役割に本人の想定とのギャップがある場合、モチベーションが下がりやすくなります。例えば、前職での経験と大きく異なる業務を任されたり、仕事の裁量が少なかったりする場合は、早期離職のリスクが高まることもあります。
(2)キャリアの方向性の模索
若手である第二新卒は、将来のキャリア像をまだ模索している段階。自己成長やキャリアアップの機会が少ないと感じると、より自分の希望に合った環境を求めて転職を考えやすくなります。特に、業務の幅や責任範囲が限定的であったり、評価制度が不透明であったりする場合、離職を検討することが多いです。
(3)職場環境や人間関係
職場の雰囲気や上司・同僚との相性も、早期離職に影響する大きな要素です。特に若手社員は、指導やサポートを受けながら成長することが期待されるため、メンターや先輩の存在が重要です。コミュニケーションが取りにくい環境やサポート体制が不十分な場合、孤立感を感じて離職に至ることがあります。
(4)待遇や働き方への不満
給与や勤務形態、福利厚生など待遇面での不満も早期離職の要因のひとつです。前職との比較や、他社の同年代社員との待遇差が明確になると、キャリアの選択肢として転職を検討する可能性が高まります。
第二新卒の採用で注意すべきポイント
企業が第二新卒を採用する際は、単に即戦力としての期待だけでなく、入社後の定着も意識することが重要です。入社前に仕事内容やキャリアパスを明確に伝え、企業文化や職場環境についても正確な情報を提供することで、入社後のギャップを減らせます。また、早期離職のリスクを理解した上で、入社後のフォロー体制を整えておくことが、定着率向上につながります。

第2章:企業ができる早期離職防止策
第二新卒は、柔軟性や学習意欲が高く即戦力になり得る一方で、キャリアや職場環境への期待が高く、入社後のギャップによって早期離職につながりやすい傾向があります。企業が第二新卒の定着率を上げるためには、採用段階から入社後のフォローまで、一貫した対策を講じることが重要です。具体的な取り組みを段階別に解説します。
採用段階でのミスマッチ防止
(1)仕事内容とキャリアパスを明確に伝える
第二新卒が早期離職する主な理由のひとつは、入社前の期待と実際の仕事内容とのギャップです。採用面接や説明会の段階で、業務内容や担当範囲、成長機会、キャリアパスを具体的に示すことが重要です。たとえば、「入社1年目はこの業務を担当し、2年目には〇〇のプロジェクトに関わる」といった具体例を示すことで、入社後のイメージが湧きやすくなります。
(2)面接・適性検査の工夫
第二新卒はまだキャリアの方向性を模索している場合が多いため、採用面接では価値観や志向性の把握が重要です。単にスキルや経験を確認するだけでなく、自己成長の意欲や職場での働き方の希望についても質問することが有効です。また、性格や思考の傾向を把握する適性検査を組み合わせることで、入社後のミスマッチを減らせます。
(3)企業文化や職場環境の情報提供
職場の雰囲気やチーム構成、上司のリーダーシップスタイルなど、数値化できない要素も第二新卒の定着に影響します。社員インタビューや社内イベントの様子を紹介するといった企業文化を具体的に伝える取り組みは、入社前の不安を和らげる効果があります。
入社後のフォロー・育成
(1)メンター制度やOJTの活用
入社後のサポート体制は、早期離職防止に直結します。先輩社員をメンターとして割り当て、業務だけでなく社内での人間関係やキャリアの悩みにも相談できる環境を整えることが重要です。また、OJTを通じて、実務を経験しながら成長できる仕組みを作ることも効果的です。
(2)定期的な面談とフィードバック
入社後、定期的に上司や人事担当との面談を設けることで、悩みや不安を早期に把握できます。面談では、業務の進捗だけでなく、キャリア目標や働き方への希望についても話し合うことが望ましいでしょう。適切なフィードバックを提供することで、自己成長を実感でき、モチベーションの維持につながります。
企業文化・職場環境の改善
(1)コミュニケーションの活性化
第二新卒はまだ社内でのコミュニティが十分に構築されていない場合が多く、孤立感を抱くことがあります。チームミーティングや1on1、社内イベントなど、コミュニケーションの場を増やすことで、職場への定着感を高めることが可能です。
(2)柔軟な働き方の導入
ライフスタイルや働き方の多様化に対応することも、早期離職を防ぐポイントです。リモートワークやフレックスタイム制、休暇制度の充実など、柔軟な働き方を提供することで、社員の満足度や定着率を向上できます。
(3)評価制度の透明化
評価や昇進の基準が不明確だと、成長実感が得られず、転職意欲が高まってしまうことも。定期的な評価とフィードバックを通じて、努力や成果が正当に評価される仕組みを整えることが重要です。
社内情報の可視化で入社前後のギャップを減らす
入社前に職場の実態を把握できる情報が少ないと、入社後のギャップが大きくなり、早期離職につながりやすくなります。現職社員の声や社内の雰囲気を伝える情報を積極的に発信することで、採用段階から定着を意識した対応が可能です。次に、現職社員のリアルな声を集めた口コミサイト「VOiCE」を活用した具体的な方法を紹介します。
第3章:VOiCEの活用で早期離職を防ぐ
VOiCEとは
VOiCEは、現職で働く社員の声や評判を掲載している口コミサイトです。入社前に求職者が職場の雰囲気や働き方を理解する手助けとして活用できます。また、企業側も自社の制度や働く環境について、客観的に伝えるための参考情報として利用可能です。第二新卒の採用においては、入社前に正確な情報を提供することで、早期離職のリスクを減らすことにつながります。
VOiCEの特徴
(1)社員の経験や感想を知ることができる
VOiCEでは、現職社員が実際に経験した業務内容や日常の働き方に関する口コミが掲載されています。例えば、プロジェクトでの取り組み方やチーム内での協力の仕方など、具体的な業務体験を知ることができます。入社前にこうした情報を把握することで、職場のイメージをより具体的に持つことが可能です。
(2)職場の雰囲気や制度を理解できる
VOiCEでは、社員の体験を通して職場環境や評価制度、キャリアサポートの一例も確認できます。業務のやりがいや成長機会、コミュニケーションの取り方など、公式情報だけでは分かりにくい点を補足的に知ることができます。これにより、入社前の理解を深める参考として活用できます。
(3)企業の情報発信の補助として
VOiCEは、企業が自社の魅力や制度を客観的に伝える補助ツールとしても活用できます。社員の体験に基づく情報を整理することで、求職者が職場の特徴を理解しやすくなります。ただし、成果や待遇を保証する表現は避け「社員の声の一例」として提供することが重要です。
第二新卒採用での活用方法
(1)採用前の情報提供に活用
VOiCEの内容を採用説明会や求人ページで紹介する場合は「現職社員の声の一例」として掲載するのが良いでしょう。たとえば「この職場では〇〇の業務に携わった経験がある社員もいます」といった形で具体例を示すことで、入社前に職場の雰囲気や仕事内容を理解してもらいやすくなります。
(2)入社後フォローの参考情報として
VOiCEに集まる社員の声は、入社後のフォローや育成の改善にも活用できます。新人が感じやすい課題や不安を把握する材料として利用することで、早期離職のリスクを抑える取り組みを検討する際の参考になります。
まとめ:第二新卒の早期離職を防ぐために企業ができること
第二新卒は、社会人経験を持ちつつ柔軟性や学習意欲が高い層であり、企業にとって大きな戦力となる可能性があります。しかし、仕事内容や職場環境が本人の期待と合わなかった場合、早期離職につながるリスクがあることも事実です。
企業が第二新卒の早期離職を防ぐためには、採用段階から定着まで一貫した取り組みが求められます。採用段階では、仕事内容やキャリアパス、企業文化を具体的に伝え、入社前のギャップを減らすことが大切。入社後は、メンター制度やOJT、定期的な面談を通じてフォローを行い、働きやすい職場環境を整えることが有効です。
さらに、現職社員の声を集めた口コミサイト「VOiCE」を活用することで、入社前に職場の雰囲気や働き方を具体的に理解してもらえます。社員の体験に基づく情報は、第二新卒が入社後に感じやすい不安やギャップを減らす材料となり、定着率向上にもつながります。
これらの対策を組み合わせることで、第二新卒の早期離職を防ぎ、企業にとっても求職者にとってもより満足度の高い採用を実現できるでしょう。