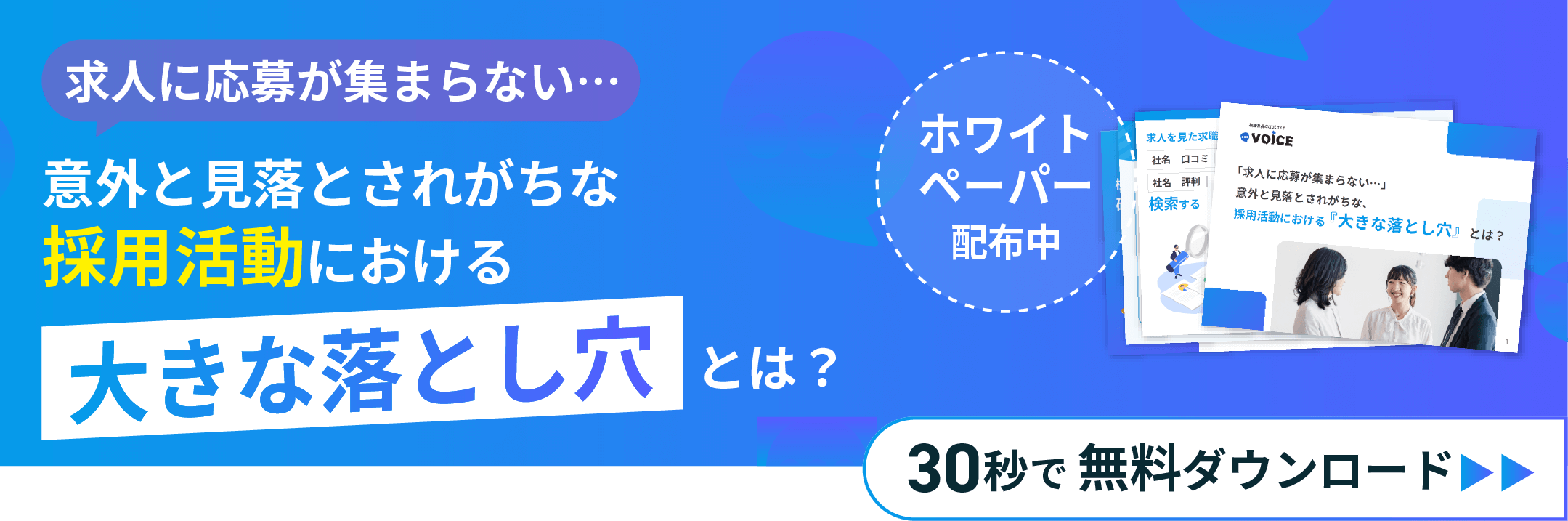薬剤師が早期離職してしまうのはなぜ?理由と定着率向上の採用施策
- 採用強化
- 採用課題
- 離職防止
2025.08.14
「せっかく薬剤師を採用したのに、半年も経たずに辞めてしまった……」
このような声を、薬局や病院、ドラッグストアなど薬剤師を雇う現場から耳にする機会が増えています。
人材不足の中でようやく採用できたと思ったら、短期間での離職。採用にかけた時間やコストが無駄になるだけでなく、現場の士気低下や再採用に追われる負担も大きな問題です。
薬剤師の離職理由は「職場に合わなかった」のひと言では片付けられず、背景には職場環境、ミスマッチな採用、価値観のすれ違いなど、いくつもの要因が複雑に絡んでいます。
本記事では、薬剤師が早期離職してしまう理由を整理しながら解説。
さらに、薬剤師の早期離職を防ぐ採用のポイントや社員のポジティブな声を活かした採用施策もご紹介します。
薬剤師が早期離職してしまう主な理由とは?
「薬剤師は資格職だから離職率が低いのでは?」と思われがちですが、実際には早期離職が多い職種の1つです。現場では「せっかく採用したのに、数ヶ月で辞めてしまった」という声も珍しくありません。企業や薬局側としては、手間とコストをかけて採用した人材が短期間で離職するのは大きな損失です。
では、なぜ薬剤師は早期離職してしまうのでしょうか?ここでは、薬剤師が短期間で離職する主な理由について解説します。
1. 業務内容と期待とのギャップ
薬剤師は調剤や服薬指導といった専門業務のイメージが強いですが、実際には在庫管理や事務処理、レジ業務、クレーム対応など多岐にわたる業務をこなす必要があります。
特にドラッグストアでは、OTC販売や接客業務に追われることも多く「思っていた仕事と違った」「もっと専門性を活かせると思っていた」とミスマッチを感じ、早期離職につながるケースが目立ちます。
2. 人間関係や職場の雰囲気
上司や同僚との人間関係での悩みや、少人数体制による閉塞感も薬剤師の離職理由として挙げられます。
薬局や病院では人間関係が固定されやすく、相性が悪い上司や先輩がいると、日々の業務がストレスになりやすいです。
また、業務の忙しさから新人の教育が後回しにされる環境も少なくありません。孤独感や孤立を感じた結果、短期間で職場を去ってしまう薬剤師も少なくないのです。
3. 労働環境の過酷さやワークライフバランスの崩壊
薬剤師不足の影響で、一人当たりの負担が非常に大きい職場もあります。
地方や夜間診療のある薬局の一部では、長時間労働やシフトの過酷さが問題になっていることも。
「体力的に続けられない」「プライベートの時間が取れない」といった理由から、やむを得ず退職するケースもあるのです。
4. キャリアの停滞や将来性への不安
薬剤師は専門職でありながら、キャリアパスが見えにくいと感じる人も多いです。
「このまま調剤だけを続けていくのか」「スキルアップできるのか」といった将来への不安があると、
よりキャリアの可能性を広げられる職場へと転職を考える傾向があります。

薬剤師の早期離職が企業にもたらす損失とは?
「早期離職は仕方ない」と片づけてしまうのは危険です。
薬剤師の早期離職は、企業や薬局にとって想像以上に大きな損失をもたらします。ここでは、具体的な影響について掘り下げて解説します。
1. 採用コストの損失
薬剤師の採用には、以下のような多くの時間と費用がかかっています。
- 求人媒体への掲載費用
- 人材紹介会社への紹介料
- 面接・書類選考などにかかる工数
- 入職後の研修・教育コスト
その薬剤師が半年以内に辞めてしまえば、かけた時間や費用が水の泡になってしまうのです。
採用が思うように進まないたびに、このコストを繰り返し負担しなければなりません。
2. 回収できない育成コスト
新しく入社した薬剤師が即戦力になるわけではありません。実際には、現場のOJTやフォローアップを通じて徐々に業務に慣れていくものです。
先輩スタッフが指導に時間を割くことで通常業務の効率も一時的に落ちます。
ようやく戦力になってきた頃に辞められてしまえば、教育にかけた時間や労力が十分に活かされないまま終わってしまうことになります。
また、スタッフの入れ替わりが頻繁だと、残されたスタッフの士気低下や疲弊にもつながりかねません。
3. 現場運営への悪影響
薬剤師は国家資格を有する専門職であり、一定人数の確保が法令で義務づけられている場合もあります。
急な離職が発生すると、以下のような問題が起こり得ます。
- 薬局や店舗の営業時間短縮
- 既存スタッフへの過度なシフト調整・残業増加
- 顧客対応の質の低下
人手不足が表面化すると、地域の患者や利用者からの信頼低下にもつながります。これは、長期的な経営リスクにもなりかねません。
4.組織イメージの悪化
短期間で辞める薬剤師が多い職場は「働きづらい職場なのでは?」というネガティブな印象を与えることがあります。
特に口コミサイトやSNSでの発信が盛んな現代では、悪い評判が広まりやすい傾向にあります。
すると、次の採用にも悪影響を及ぼし、求人応募が減る、優秀な人材が集まらないといった悪循環に陥ってしまいます。
薬剤師の早期離職は、単なる「人材が減った」という話では済まされません。経済的損失と組織運営の停滞、ブランドイメージの低下という複数のリスクを同時に抱えることになるのです。
長く活躍する薬剤師を採用するために見直すべきポイント
薬剤師の早期離職が頻発する背景には、採用時点でのミスマッチが深く関係しています。では、どうすれば長く活躍する薬剤師を採用できるのでしょうか?ポイントは「入社前からの相互理解の深さ」と「働き続けたいと思える職場づくり」です。
1. 価値観・働き方のマッチングがカギ
薬剤師の業務内容や職場環境は、企業によって大きく異なります。調剤中心の職場もあれば、在宅医療やOTC販売に力を入れているところもあるため「薬剤師」という職種名だけで画一的に採用するのは危険です。
また、応募者が求める働き方(例えば、ワークライフバランスを重視するのか、キャリアアップを志向しているのか)と企業側のニーズがズレていると、入社後に「思っていたのと違う」となり、短期間で離職する原因になります。
このズレを防ぐには、選考時から企業の価値観や将来の方向性を明確に伝え、応募者側の考えともすり合わせることが欠かせません。
2. 現場のリアルな声を届ける工夫を
会社の魅力を正しく伝えるには、給与や福利厚生といった表面的な条件だけでなく「人」「文化」「空気感」などの内面を伝える努力が必要です。特に薬剤師は、日々チームで働く機会も多いため、人間関係や現場の雰囲気が職場選びの重要な判断材料になります。
それには、社員のリアルな声を活用した採用情報の発信が有効です。たとえば、現場で働く薬剤師が実際に感じているやりがいや、会社のサポート体制などをインタビュー形式で伝えることで「この職場なら続けられそう」と感じてもらえる可能性が高まります。
3. 「辞めない人材」は辞めない環境でこそ育つ
採用の段階で“辞めにくい人”を見極めようとするよりも「辞めにくい環境」を整えることのほうが、定着率の向上につながります。
たとえば、
- 相談しやすい上司や先輩の存在
- 定期的なフォロー面談の実施
- 明確なキャリアパスの提示
- 柔軟な働き方への対応(時短勤務・希望休の取得など)
といった要素は、薬剤師の不安を和らげ、長く働くモチベーションを保つ基盤になります。
つまり「辞めない薬剤師を採用する」のではなく「辞めたくならない職場をつくる」。この考え方が、採用成功と定着の鍵になるのです。
薬剤師の定着率向上を支える VOiCE の活用法
薬剤師の早期離職を防ぐには、求職者との相互理解を深める採用活動が欠かせません。そのための一つの手段として、社員のリアルな声を発信できる口コミサービス「VOiCE」があります。
1. VOiCEとは? ─ 現職社員の“ポジティブな声”を届ける口コミサイト
VOiCEは、現職社員のポジティブな口コミを通じて、企業の“リアルな魅力”を求職者に届けるサービスです。
一般的な採用サイトや求人媒体では伝えきれない「働く人の価値観」や「日々の仕事への想い」「実際の職場の雰囲気」などを、等身大の声で表現できるのが特長です。
薬剤師をはじめとする専門職の採用では、職場の環境や人間関係などが重視されるため、VOiCEのような実際に働く社員によるリアルな口コミの発信は相性が良い手段といえます。
2. 共感・納得を生むことで、入社後のギャップを軽減
求職者が「この会社で働くイメージが持てる」と感じれば感じるほど、入社後のギャップは小さくなり、定着率の向上にもつながります。
VOiCEでは、以下のような具体的な声を通じて、職場の雰囲気や働き方の実態を伝えられます。
- 「現場の雰囲気がとても温かく、困ったときに相談しやすいです」
- 「ライフステージが変わっても働き続けられる制度があるのが安心でした」
- 「調剤だけでなく在宅や健康相談など、幅広い経験が積めるのが魅力です」
こうした社員の実体験は、企業が発信するメッセージよりも信頼性が高く、応募者の共感を得やすいコンテンツになります。
3. 価値観がマッチする薬剤師に刺さる情報を届ける
VOiCEで集めた社員の声を採用活動に活かして、企業にマッチする人材に響く内容を届けることも可能です。
たとえば、以下のようにターゲット層に合わせた社員のリアルな声をまとめて採用資料としても活用できます。
- ワークライフバランス重視:働き方の柔軟性、休日の取りやすさ、育児との両立事例
- キャリア志向型:教育制度、資格取得支援、社内キャリアパス
- 安定志向:離職率の低さ、定年まで働ける制度、長期雇用実績
このように、ただ企業の良さをアピールするのではなく「どのような価値観の人に合う職場か」を具体的に示すことが、採用後のミスマッチ防止と定着促進に効果的といえるでしょう。
まとめ:薬剤師の早期離職を防ぐには、採用の質を見直すことが鍵
薬剤師の早期離職に悩む企業にとって「長く活躍する薬剤師」を採用することは喫緊の課題です。
本記事では、その実現のために以下の観点が重要であることを解説してきました。
- 早期離職がもたらす損失は、採用費や育成コストだけでなく、職場の士気低下にもつながる
- 早期離職を防ぐにはミスマッチの要因を知り、採用プロセスを見直す必要がある
- 職場のリアルを伝える取り組みが、応募者との相互理解を深め、ミスマッチを防ぐ
- VOiCEのようなサービスを活用すれば、社員の声を通じて“マッチする人材”に届く採用活動が可能になる
単に求職者を集めるのではなく「自社に合う薬剤師」を惹きつけ、納得感のある入社につなげることが、結果として定着率の向上や採用効率の改善につながります。
早期離職に頭を抱えている採用責任者の方は、まず今の採用手法を見直し「薬剤師に選ばれる職場づくり」と「ミスマッチを減らす情報発信」に注力してみてはいかがでしょうか。