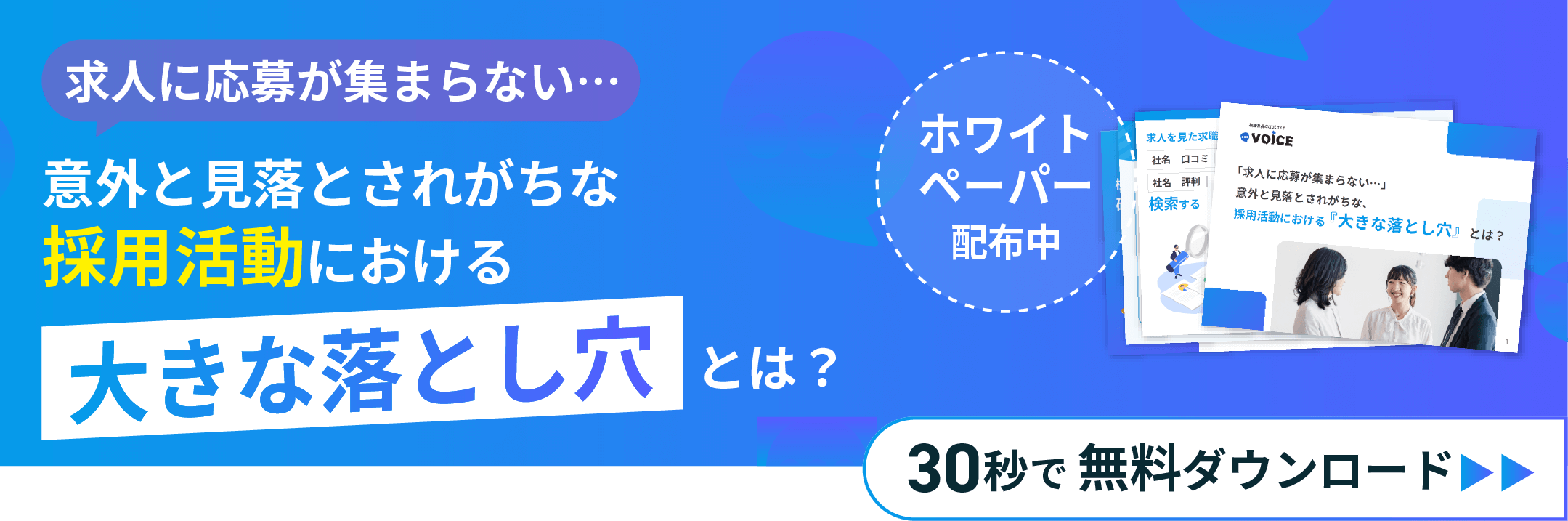リファラル採用がうまくいかない理由とは?成功に導くための根本的な改善策を解説
- 採用強化
- 採用活動
- 採用課題
2025.08.14
近年、人材の定着率向上や採用コスト削減を目的に「リファラル採用(社員紹介)」を導入する企業が増えています。求人媒体や人材紹介会社に頼らず、社員の紹介によって信頼性の高い候補者を採用できる点がメリットとして語られがちですが、実際には「うまく機能していない」「紹介が集まらない」といった声も少なくありません。
実際に「リファラル採用 うまくいかない」と検索している人事担当者や経営層の方は多く、制度設計や導入支援サービスを利用しても成果が出ないケースも散見されます。
なぜ、期待されていたリファラル採用が成果につながらないのでしょうか?
本記事ではその背景にある社員心理や職場環境の問題を紐解きながら、リファラル採用を成功させるために企業が取り組むべき根本的な改善策を解説します。
1. よくある悩み|リファラル採用がうまく進まない3つの理由
リファラル採用が期待通りに成果を出せない企業には、いくつかの共通した背景があります。ここでは、現場でよく見られる課題を3つに分けてご紹介します。
(1)社員が「安心して紹介できる」と感じられていない
リファラル採用が機能しない原因のひとつに「社員が自信を持って知人を紹介できない」という状況があります。
たとえば、次のような心理が働いているケースがあります。
「職場環境がまだ整っていないから、紹介するのは少し不安」
「もしうまくいかなかったら、自分と相手の関係に気まずさが残るかも」
「現場が忙しくて、人が増えることで負担が増えるかもしれない」
紹介とは、社員にとって大切な人との信頼関係を前提とした行動です。だからこそ「紹介しても安心」「自分の評価が下がらない」と感じられる職場環境や信頼感がなければ、自然な紹介は生まれにくいのです。
(2)インセンティブ制度だけに頼ってしまっている
リファラル採用を促進する目的で報酬制度を取り入れている企業は多くあります。しかし、金銭的なインセンティブだけでは、紹介の動機としては不十分になりがちです。
紹介には、相手に対する責任や自分の職場に対する信頼が必要です。単に報酬があるから紹介するというスタンスでは、継続的な成果を出すことは難しく「一度きりの紹介で終わってしまう」状況にもつながりかねません。
(3)紹介後のフォロー体制に不安がある
せっかく社員が紹介しても、その後の流れがスムーズでなければ紹介は続きません。
たとえば、
紹介した後の選考状況が見えづらい
入社後にサポート体制が不十分で、候補者が孤立してしまう
紹介者へのフィードバックがない
といったことがあると「紹介してよかった」という前向きな気持ちは生まれにくくなります。
社員が安心して紹介できるよう、紹介から選考、入社後のオンボーディングまで一貫したフォロー体制を整えておくことが、次の紹介にもつながる重要なポイントです。

2. 社員が紹介したくなる会社とは?成功事例に学ぶ企業の共通点
リファラル採用を成功させている企業には「紹介したくなる理由」が社員の中に自然と根付いています。ここでは、リファラルが活発に行われている企業に共通する特徴を紹介しながら、社員が前向きに“紹介”という行動を起こす背景について掘り下げていきます。
(1)職場の雰囲気や人間関係に自信がある
「うちの会社、いい人が多いから一緒に働きやすいよ」
このように自然と話せる会社では、リファラル採用がうまく回ります。
紹介は“この職場に大切な人を迎え入れたい”という気持ちが前提です。そのためには「人間関係が良好」「安心して働ける」と社員が日頃から感じていることが不可欠です。
一方で、ギスギスした人間関係や慢性的な業務過多のような状態では、制度が整っていても紹介はなかなか生まれません。
(2)紹介後のフォローや社内の受け入れ体制が万全
社員が安心して紹介できる企業は、紹介後の候補者に対するサポートが丁寧です。たとえば、
選考状況を紹介者にも適宜フィードバックする
内定後、配属部署と紹介者が連携してオンボーディングを行う
入社後の不安やミスマッチを減らすためのフォロー面談を実施する
など、紹介された人が安心して活躍できるよう、制度だけでなく“人”の動きが伴っています。
このような丁寧なフォローは紹介者にも安心感を与え「次も紹介しよう」というポジティブな循環を生み出します。
(3)ポジティブな社員の声が社内外に“見える化”されている
社員のリアルな声が、採用広報の中で活用されている企業は、リファラル採用が活発になりやすい傾向があります。
たとえば、
社員インタビュー記事や動画を採用サイトに掲載
SNSや社内報で「働く人のストーリー」を定期的に発信
紹介時に使える「社員の声付きの会社紹介資料」を整備
このような仕組みにより、紹介者が「この会社のどこが魅力なのか」を明確に伝えやすくなり、紹介の心理的ハードルが下がります。
社員の声を“見える化”することで、紹介のきっかけをつくる効果が期待できるといえるでしょう。
3. 「紹介される会社」になるために必要な組織づくりとは
リファラル採用の成功には、制度やツールの整備だけでなく「紹介されるにふさわしい会社」であることが重要です。ここでは、紹介される会社になるために企業が取り組むべき“組織づくりのポイント”を3つの観点から解説します。
(1)心理的安全性の高い職場をつくる
心理的安全性とは、社員が「自分の意見を安心して言える」「ミスや課題を素直に共有できる」と感じられる状態を指します。つまり、立場や経験に関係なく、誰もが安心して発言や提案ができる風通しの良い職場環境が整っていることが、心理的安全性が高い状態だといえます。
社員が誰かを紹介するには「この職場なら大切な人にも自信を持って勧められる」と思えることが重要です。そのためには、次のような日常的な取り組みが効果的です。
上司が部下の意見に真摯に耳を傾ける
会議で全員が発言できるように配慮する
ミスを責めるのではなく、前向きに改善策を共有する文化をつくる
紹介の裏側には、社員の「自分の職場に対する信頼感」があります。心理的安全性を高めることは、リファラル採用の土台を築く上で欠かせないステップです。
(2)会社の「価値観」や「ビジョン」を、共感できる形で発信する
社員が誰かを紹介する背景には「この会社で働く意味や意義に共感している」という気持ちがあります。言い換えれば、日々の仕事が単なるタスクの積み重ねになっていると、誰かを招き入れたいという感情は生まれにくいのです。
だからこそ、企業側は次のような発信を意識することが大切です。
経営層から社員へ、ミッション・ビジョン・バリューを定期的に伝える
社員がビジョンに基づいた取り組みをしている様子を社内で共有する
採用広報でも理念やカルチャーを言語化し、共感を呼ぶコンテンツを用意する
こうした取り組みを通じて「この会社で働くことに意味がある」「自分も会社の一部として貢献している」と社員自身が感じられるようになれば、自然とその価値を人に伝えたくなるものです。
(3)現場から経営層まで、“紹介の文化”を育てる
リファラル採用を一過性のキャンペーンではなく、企業文化として根づかせるには、社内全体の意識づけが必要です。紹介を「やらされるもの」ではなく「自然なコミュニケーションの一部」にしていくことが理想です。
そのために有効なアプローチは以下の通りです。
経営陣が率先して紹介の重要性を社内で語る
リファラルで入社した社員の活躍を紹介し、成功体験を可視化する
「紹介してくれてありがとう」と感謝の言葉を日常的に伝える
こうした一つ一つの積み重ねが「紹介しても大丈夫」「紹介すると会社も自分もうれしい」という空気をつくり、制度ではなく文化としてリファラルが定着します。
4. 【ソリューション提案】VOiCEで社員の“今ここにいる理由”を伝えよう
リファラル採用を成功に導くには、社員のリアルな声を収集し、それを採用活動に活かす視点が重要です。そのために活用できるサービスが、現職社員による口コミに特化したメディア『VOiCE(ボイス)』です。
VOiCEとは?
VOiCEは、現職社員によるポジティブな口コミに特化した企業紹介のメディアであり、いわゆる“現職社員に特化した口コミサイト”です。退職者のネガティブな声ではなく、今もその企業で活躍している社員の“今ここにいる理由”を発信することに重きを置いている点が特徴です。
VOiCEの主な特徴
1. 現職社員の声に中心を置き「今の会社選び」に寄与
一般的な口コミサイトでは退職した社員の意見や古い投稿が多く、新規応募者にとっては信頼性に欠ける場合があります。VOiCEでは、現職社員の声を集めることで「今働いている人が本当にどう感じているか」を伝える場を提供します。
2. ポジティブな声を中心に掲載し、企業の魅力を表現
口コミに基づくテキストマイニング機能を導入。企業の文化や働き方の魅力を、口コミから抽出されたキーワードをもとに可視化できます。これにより、求職者が企業の“らしさ”を理解しやすくなります。
3. 掲載企業は社内調査・アンケートの実施が前提
VOiCE掲載には、企業による現職社員対象のアンケート調査が必要です。つまり、社員の声を集め、内部の改善にも活用する姿勢のある企業のみが掲載される構造です。
リファラル採用におけるVOiCEの役割
リファラル採用を促進する上で、VOiCE活用には以下のようなメリットがあります。
社員の「自社の魅力」を紹介しやすくなる:信頼できるリアルな社員の声が、紹介時の資料や採用ページで使いやすくなります。
求職者の動機形成を促進:求職者は実際に働いている人の言葉を見て、会社理解が深まります。
内部改善のきっかけを得る:ポジネガ両面のフィードバックが見えることで、紹介しやすい職場づくりにつながります。
VOiCEを活用するには
まず、現職社員に向けたアンケート調査を実施し、ポジティブな声を収集します。
収集した声はVOiCEに掲載され、求職者向けに発信できるようになります。
加えて、社内用素材として紹介資料や採用広報コンテンツに活用することで、紹介者や求職者の信頼度を高めます。
社員の“今ここにいる理由”を可視化して、紹介を後押ししよう
リファラル採用がうまくいかない原因のひとつは、社員が「自分が働いている会社の魅力を、自信をもって伝えられない」ことにあります。VOiCEを活用することで、現職社員から発せられるリアルな声を“紹介しやすい形”で届けられ、紹介のきっかけづくりに貢献します。
もちろんこれはあくまでひとつの手段。VOiCEで集めたコンテンツを組織運営やコミュニケーションに活用し、“紹介される会社”への文化づくりに組み込んでいくことが重要です。
5. まとめ|リファラル採用を成功に導くために今、取り組むべきこと
リファラル採用は、信頼できる人材をコストを抑えて採用できる非常に効果的な手法です。しかし、その導入や運用がうまくいかないケースも少なくありません。
ここまで解説してきた通り、制度そのものに目を向ける前に大切なのは「紹介したくなる会社」であるかどうかを見つめ直すことです。
リファラル採用がうまくいかない原因は「紹介されにくい環境」にある
多くの企業が抱える課題は、社員が自社を「紹介したい」「勧めたい」と思えていないという点です。これは、制度設計や報酬インセンティブの有無とは関係なく、職場への信頼感や安心感、そして会社への共感がないと、自然な紹介は生まれません。
「紹介される会社」になるためのステップ
リファラル採用を根付かせるためには、次の3つの視点から職場づくりを見直す必要があります。
心理的安全性のある職場をつくる
社員が安心して意見や課題を話せる環境を整える。会社の価値観やビジョンを明確に発信する
「この会社で働く意味」が言語化されていることが紹介の動機を生む。紹介文化を根づかせるコミュニケーション
成功事例を共有し、紹介者にきちんと感謝の意を伝える文化をつくる。
社員のリアルな声を活用するツールの活用も効果的
VOiCEのように、現職社員によるポジティブな声を集めて発信できるサービスを活用することで、社員が「紹介しやすい」環境を整えることができます。
社員自身も自分の言葉が使われていることを知ると、会社への信頼感や愛着も高まり、リファラルの促進にもつながっていきます。
最後に
リファラル採用は、単なる採用手段ではなく「社員が自社をどう見ているか」という企業の“内面”を映し出す鏡のような存在です。
もし、いま制度を整えてもうまくいかないと感じているのであれば、それは制度の問題ではなく、“紹介したくなる会社になれていない”というサインかもしれません。
一朝一夕では変わらないからこそ、今から「社員の声に耳を傾けること」から始めてみてはいかがでしょうか。リファラル採用は、企業と社員の関係性をより良くするきっかけにもなるでしょう。