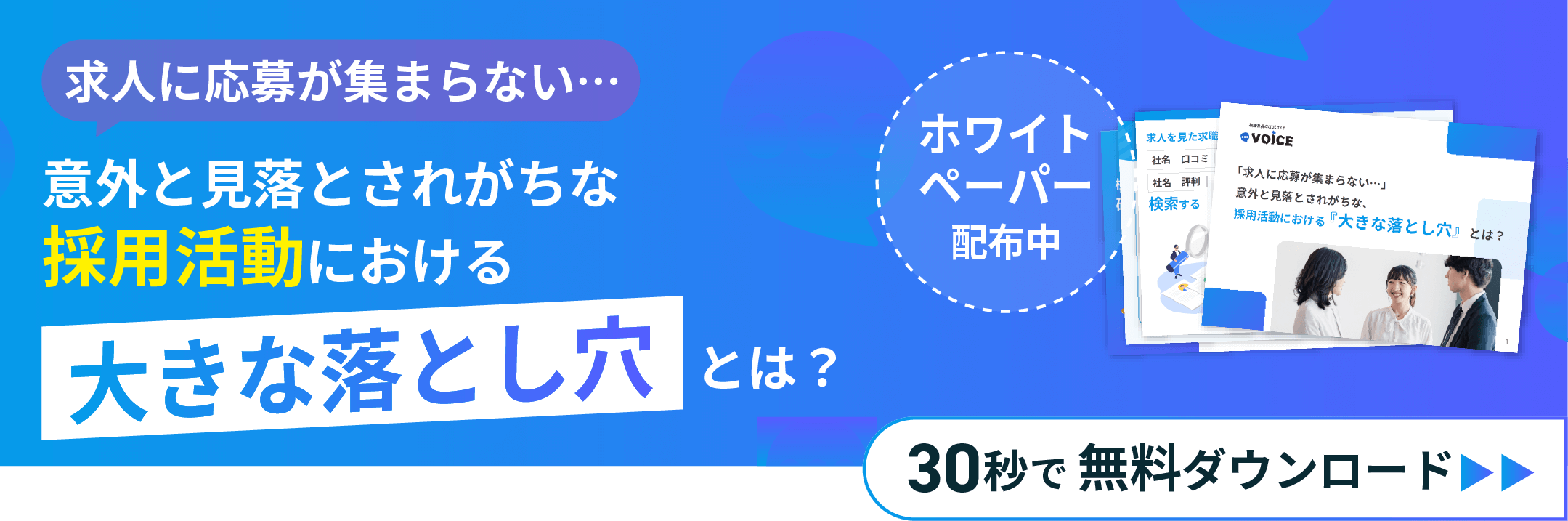レピュテーションリスクとは?今すぐ始める第一歩
- 会社の評判
- 採用活動
- 採用課題
2025.08.14
企業経営や人材採用において、近年急速に注目を集めている言葉があります。それが「レピュテーションリスク」です。
これは直訳すれば“評判リスク”。つまり、企業の社会的評価や信頼性が毀損されることで発生する経営的な不利益や採用活動への悪影響を指します。特にデジタル社会の現在においては、そのリスクはかつてないほど身近で、かつ拡散性が高く、見過ごすことのできない重要課題となっています。
たとえば、ある退職者がSNSや口コミサイトに残した1つの投稿。それが数ヶ月後、貴社の採用サイトを見ていた有望な応募者の目にとまったとしましょう。「あれ、この会社、なんか雰囲気悪そう……?」と感じたら、求職者の関心は冷め、応募の意欲は下がってしまいます。こうした“小さな評判”が、採用活動や社外の信用構築に与えるインパクトは、年々大きくなっているのです。
かつてはテレビCMや新聞広告など、自社発信の情報が主流でしたが、今や人々は「第三者からのリアルな声」こそを信頼します。とりわけ、転職を検討する層は、企業のWebサイト以上に、口コミサイトやSNSで「現場の声」を確認しているのが実態です。
そのような背景の中、レピュテーションリスクに正面から向き合い、戦略的に対処する姿勢は、もはや“あったほうが良い”ものではなく、“備えて当然”の経営課題となっています。
本記事では、経営者や採用責任者の皆様に向けて、この目に見えにくいリスクの本質と、今日から始められる取り組みについて、実践的な視点からお伝えします。
1. レピュテーションリスクが企業にもたらす主な3つの影響
レピュテーションリスクとは「評判が損なわれることで生じる経営上のリスク」ですが、その影響は実に多面的です。特に人材採用に関わる責任者や経営層にとっては、以下の主な3点が深刻な課題となり得ます。
① 採用活動における「見えない離脱」の増加
現在の求職者は、企業の採用ページだけでなく、転職系口コミサイトやSNSなど、あらゆる情報ソースを横断的にチェックしています。その中で「この会社、評価が低いな…」という印象を持たれた場合、応募すらされずに“水面下での離脱”が起きている可能性が高いのです。
これは、採用担当者の目には見えない現象であるため、対応が遅れがちです。しかし、実際には優秀な人材が「口コミでの評判」を理由に、エントリーを避けているという現実は、多くの企業で起きています。
② 既存社員のモチベーションと定着率への悪影響
レピュテーションリスクは、社外だけでなく社内にも波及します。ネット上でネガティブな声が拡散されると、社員の間でも「あの投稿、うちのことじゃないか?」と不安が広がり、組織全体の士気が下がってしまうこともあります。
また、将来的なキャリアを考える中で「この会社に居続けると、自分の市場価値が下がってしまうのでは」と感じた社員が、転職を考え始めるケースも少なくありません。つまり、評判の悪化は、離職リスクや内部崩壊の引き金にもなり得るのです。
③ 顧客・取引先との信頼関係の毀損
レピュテーションは、求職者や社員だけでなく、顧客や取引先との関係にも直結します。特にBtoB企業の場合、「評判の悪い会社とは関わりたくない」という心理が働き、入札や商談で不利になるケースもあります。
たとえばある発注担当者が、商談中に企業名を検索し、ネガティブな口コミを目にしたとします。すると「コンプライアンス意識が低いのでは?」「離職率が高いと、プロジェクト継続性が心配だ」といった懸念につながり、競合に乗り換えられてしまうことも。
つまり、レピュテーションリスクは、採用だけでなく売上・利益にも波及する、経営全体の根幹にかかわるリスクなのです。

2. 求職者にとって企業の“口コミ”は特に重要なポイント
レピュテーションリスクの影響を深く理解するためには、求職者の視点に立つことが不可欠です。従来のように、求人票や企業の公式サイトだけを頼りに就職活動を行う時代は、すでに終わりを迎えています。
今や、求職者が信頼している情報源のひとつが「口コミサイト」や「SNS上の評判」です。
転職者の8割以上が口コミサイトを確認しているという事実
実際、転職希望者のうち約8割以上が、応募前に企業の評判を口コミサイトなどで確認しているという調査結果もあります。これは、単なる興味ではなく、入社後のギャップを防ぐための「防衛策」として機能しているのです。

※参照元:株式会社インタツアー「22・23卒生対象 就活におけるクチコミの活用状況調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000058834.html)
※エン・ジャパン株式会社「『エン転職』ユーザーアンケート」(https://partners.en-japan.com/special/190313)
その際、求職者は以下のような観点で情報を見ています。
- 実際の残業時間や休日の取得状況
- 上司や経営層のマネジメントスタイル
- 社内の人間関係や雰囲気
- 離職率や退職理由の傾向
- 給与や昇進に対する満足度
これらは、求人票やオウンドメディアでは見えにくい“本音の情報”であり、求職者にとっては応募の意思決定に直結する材料です。
ポジティブな情報が少ないと、それだけでネガティブに見える
ここで重要なのが、口コミが「ネガティブなものばかり」なのがリスクではないという点です。むしろ、「肯定的な声が圧倒的に少ない」「ポジティブな内容が更新されていない」といった状態そのものが、求職者にとっては“警戒サイン”になります。
なぜなら、良い職場であれば、働いている社員の満足の声が自然と出るはずだという前提があるからです。そのため、肯定的な口コミが少ない=“ブラックかもしれない”と見なされてしまうリスクがあるのです。
求職者は「信頼できる社員の声」を求めている
さらに、求職者は「どのような情報が書かれているか」だけでなく、「誰の声なのか」という点も重視します。たとえば、現職社員が実際に体験したことをもとに書いたと思われる具体的なエピソードや、部署ごとのリアルな働き方に触れた口コミには、高い信頼感と共感が生まれやすくなります。
一方で、投稿者が分からないような匿名の否定的コメントが目立つと、「この内容は本当なのか?」「一部の意見に過ぎないのでは?」といった不信感を抱かせてしまいます。そうした印象が、他社との比較の中で企業イメージを下げる結果につながることも少なくありません。
つまり、求職者が求めているのは、「ネガティブかどうか」ではなく、「信頼できるリアルな声があるかどうか」。この点を意識することが、採用活動において非常に重要なのです。
3. まずは現職社員のリアルでポジティブな口コミを発掘する所から始める
レピュテーションに関する課題を本質的に解決するためには、「悪い評判を消す」よりも先に、「良い評判を育てる」発想が欠かせません。その第一歩が、社内に眠る“ポジティブなリアルの声”を見つけ出し、可視化する取り組みです。
悪い口コミを“埋める”のではなく、“上書き”する
口コミに関する課題というと、ネガティブな投稿を削除したいという声をよく聞きます。しかし実際には、それを直接的に取り除くことは容易ではなく、仮に削除できたとしても、その空白をどう埋めるのかという新たな課題が残ります。
むしろ、重要なのは「良い声」を積み重ねていくことで、ネガティブな印象そのものを薄め、“企業の本来の姿”を伝えていくこと。いわば、評判を上書きしていくアプローチです。
社員のリアルな声こそ、企業のブランディング資産
多くの企業では、社員が日々当たり前のように感じていることの中に、外部から見ると魅力的な価値が眠っています。
たとえば、
- 上司との距離が近く、何でも相談しやすい
- 子育てと仕事を両立しやすい制度が整っている
- チャレンジできる環境があり、自分で業務を広げていける
- 成長機会が豊富で、短期間でスキルアップできる
こうしたポジティブな要素は、社員にとっては「当たり前」になってしまっているケースが多く、自発的に外へ発信されることはほとんどありません。
しかし、求職者にとっては価値の高い情報であり、まさに「現場のリアル」が伝わる口コミです。
組織ぐるみで“発掘”する仕組みを
これらの声を拾い上げるためには、口コミの発信を社員任せにするのではなく、組織として仕組みを整えることが大切です。たとえば以下のような工夫が考えられます:
- 社内アンケートで満足ポイントを収集する
- 座談会形式での“本音”ヒアリングを行う
- 実際に働いている社員のコメントを集めて特設ページに掲載する
こうした活動を継続的に行うことで、社内のポジティブな声が蓄積され、外部に対する“真の企業イメージ”として育っていきます。
つまり、評判を守ること=社員のリアルな体験を、信頼できる形で伝えていくこと。そのための起点は、社内の声にもっと耳を傾けることにあります。
4. VOiCEの特徴と導入メリット
現職社員の“生の声”を可視化し、求職者に信頼される情報として届ける。それを可能にするのが、企業口コミサービス「VOiCE」です。
従来の匿名型口コミサイトでは難しかった「企業発の透明な発信」と「求職者目線での共感形成」を、VOiCEは両立させます。
VOiCEとは?
VOiCEは、実際に今働いている社員のリアルな体験をもとに、企業文化や働く環境を“中の人”の視点から表現する新しい口コミ発信サービスです。
ただ好印象なことを並べるのではなく、「その企業で働く理由」や「仕事のやりがい」「人間関係」など、具体的なストーリーを言葉にし、採用候補者の不安や疑念を軽減することを目的としています。
従来の口コミサイトでは、企業側にとって不利な内容が一方的に拡散されるケースも多く、採用活動にブレーキをかけてしまう場面がありました。VOiCEはその課題を踏まえ、“現職社員のポジティブな実体験”を軸に、企業の魅力を正しく伝える仕組みを提供します。
特徴①:働く人の言葉で、企業のリアルを伝える
VOiCEが収集・公開するのは、現場で実際に働く社員の声です。表面的なPRではなく、日々の業務やカルチャー、マネジメントスタイルなど、社員ならではの視点が詰まったコメントが中心。
これにより、求職者は求人票や会社説明会だけでは分からない「社内の空気感」を掴めて、ミスマッチ防止や応募意欲の向上にもつながります。
特徴②:印象形成のバランスを整える“カウンター情報”として機能
仮にネット上に一部否定的な情報が存在していたとしても、VOiCE上に掲載される前向きな社員の声が“印象の中和剤”として機能します。
一方的に悪い印象が強調される状況を避け、企業本来の魅力や取り組みが適切に伝わる土壌を整えられるのです。
レピュテーションに関する課題は、単にネガティブを排除するのではなく、「正しい印象をどうつくるか」に視点を置くべき――VOiCEはそのための有効な選択肢です。
特徴③:「企業目線」ではなく「社員目線」で語られるから、信頼される
求職者が敏感なのは「企業が自分たちに都合の良い情報だけを見せていないか?」という点です。その点でVOiCEの口コミは、社員によるリアルな語り口で構成されており、候補者からは“第三者の視点”として受け止められやすくなっています。
つまり「企業が発信している情報」ではなく「そこで働く人が話している情報」であることが、信頼の源泉となっているのです。
5. まとめ:企業の“今”を届けることが、採用の未来を変える
企業の評判は、もはや外部の評価に委ねるだけの時代ではありません。自らの組織に眠る“ポジティブな声”を見つけ出し、信頼性のあるかたちで発信することが、採用活動の成果を大きく左右します。
レピュテーションリスクを回避するためには、まず企業の実像を丁寧に伝える姿勢が求められます。VOiCEは、その第一歩を力強く支える仕組みです。
求職者にとっての“安心できる判断材料”を増やし、組織にフィットした人材との出会いを実現するために、今こそ「社員のリアル」を届けてみませんか?