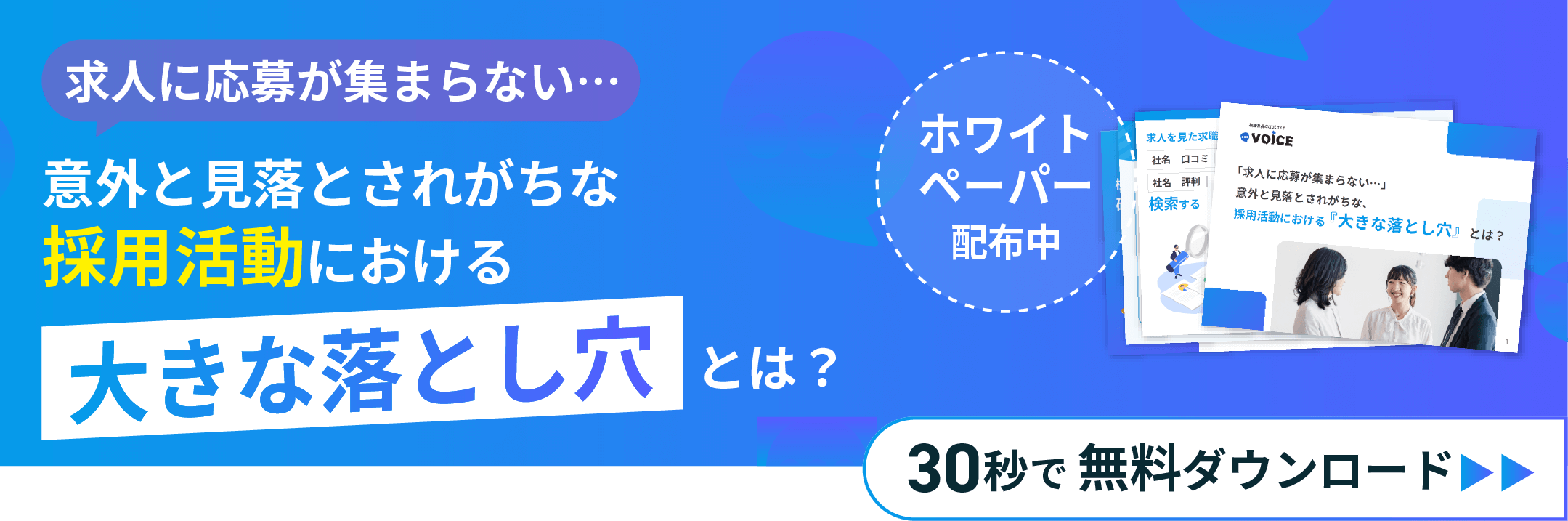薬剤師は飽和状態って本当?薬剤師の採用が難しい理由と企業が今できる対策とは
- 内定辞退
- 採用活動
- 採用課題
2025.11.04
「薬剤師は飽和状態」と耳にすることが増えました。
しかし現場では「薬剤師の採用が難しい」「応募が集まらない」と悩む声も多いでしょう。
求職者が増えているはずなのに、採用が思うように進まない──この矛盾の背景には、業界構造や働き方の変化など、さまざまな要因が関係していると考えられます。
他の業種と同様に、薬剤師も働く場所や働き方の選択肢が広がり、転職先に求める条件も多様化しています。
一方で、企業側の情報発信がまだ十分でないケースも多く、求職者との「マッチングのずれ」が生まれている傾向にあります。
本記事では「薬剤師採用が難しい」と感じている企業が直面している課題を整理し、採用を成功に導くための具体的な対策をご紹介します。
人材確保に悩む経営者や人事担当者の方にとって、次の一手を考えるヒントになれば幸いです。
薬剤師の採用が難しいといわれる背景
薬剤師は「余っている」のではなく「マッチングしていない」
ニュースやSNSでは「薬剤師は飽和状態」といわれることがあります。
しかし、実際の採用現場では「薬剤師の採用が難しい」と感じる企業が多いのが実情です。
一見すると矛盾しているように見えますが、これは「薬剤師が余っている」のではなく「企業と求職者がうまくマッチングしていない」ことが主な原因と考えられます。
厚生労働省のデータを見ても、薬剤師の有効求人倍率は依然として高い水準にあります(※1)。
しかし、薬剤師の人数は都道府県により異なるため、偏りが見られるのです(※2)。
(※1)出典:厚生労働省「職業別<中分類>常用計 有効求人・求職・求人倍率 (令和6年12月)」[PDF](https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/content/contents/002118678.pdf?utm_source=chatgpt.com)
(※2)出典:厚生労働省 薬剤師に関する基礎資料「都道府県(従業地)別の人口10万人対薬剤師数(H30)」[PDF](https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000647924.pdf?utm_source=chatgpt.com)
このように「全国的に見れば人材はいるが、自社に合う人材が見つからない」という状態が、薬剤師採用を難しくしていると考えられます。
求職者にとっても、自分に合う職場を見極める情報が不足している場合が多く、結果として“すれ違い”が起きているといえるでしょう。
採用市場の変化と薬剤師のキャリア志向の多様化
近年、薬剤師に限らずではありますが、求職者の働き方に対する考え方は大きく変化し始めています。
従来は「安定した職場で長く働く」ことを重視する傾向がありました。
しかし今は、ワークライフバランスを重視する人や、複数の職場でスキルを活かしたい人など、キャリアの価値観が多様化しているのです。
また、オンライン調剤や在宅医療の普及により、勤務形態そのものも変わりつつあります。
こうした変化の中で「正社員だけでなく、パートや業務委託など柔軟に働きたい」という希望を持つ薬剤師も増えているのです。
企業側がこのニーズに対応できていない場合、採用が難航するケースも少なくありません。
さらに、若手世代を中心に「働く環境」や「人間関係」を重視する傾向が強まっています。
給与や待遇よりも、職場の雰囲気や成長機会を重視する人が増え、企業が提供する情報が十分でないと応募をためらうこともあります。
求人票に記載された条件だけでは、職場の実際の様子を十分に伝えることは難しいのです。
薬剤師採用の競争が激化する現場
薬剤師は国家資格を持つ専門職です。
そのため、採用市場では比較的安定した需要が見込まれます。
一方で、医療機関やドラッグストア、調剤薬局、企業の研究部門など、活躍の場が幅広いため、採用競争は激しくなっている傾向にあります。
また、企業ごとの採用手法に差が生まれている点も見逃せません。
求人媒体や人材紹介会社を中心に採用活動を行う企業が多い中で、SNSや口コミを活用して情報発信を行う企業も増えています。
求職者が情報を比較しやすくなった一方で「情報発信力の差」が応募数の差となって表れるケースもあります。
つまり、薬剤師の採用が難しい背景には「人材不足」そのものよりも「求職者との接点の作り方」や「情報の伝え方」に課題があるのです。
採用活動の改善を進めていくためには、この点を見直す必要があるといえるでしょう。

薬剤師採用を難しくしている要因とは?
報酬や福利厚生だけでは採用が決まらない時代
薬剤師の採用が難しい背景には「待遇を良くすれば人が集まる」というこれまでの考え方が通用しにくくなっている現状があります。
給与や福利厚生を充実させても、応募が増えないケースも多く見られます。
その理由のひとつは、求職者が重視する価値観の変化です。
近年は「働きやすさ」「人間関係」「職場の雰囲気」など、職場環境のリアルな部分を重視する傾向が強まっています。
求人票で提示される条件だけでは、そうした情報を十分に伝えられないことが多いのです。
また、薬剤師は複数の選択肢を持つ専門職です。
他社の求人と比較した上で応募を決めるため、企業の魅力が具体的に伝わっていない場合、選ばれにくくなります。
条件面の競争に偏ると、結果的に採用コストが上がるだけでなく、定着率の低下にもつながるおそれがあります。
応募者が知りたい情報が届いていない
薬剤師の採用を難しくしているもうひとつの要因は「企業の情報発信不足」です。
公式サイトや求人媒体では、事業内容や募集条件は掲載されていますが「実際にどのような職場なのか」「どのような人が働いているのか」といった情報は伝わりにくい傾向にあります。
求職者が知りたいのは、数値や制度の説明だけではありません。
日々の仕事の雰囲気やチームの関係性、成長の実感など、“現場の声”も知りたいと考えている傾向が強まっているのです。
こうした情報が不足していると、求職者は「自分に合う職場なのか」が判断できず、応募を見送ることがあります。
さらに、採用活動における情報発信が他社と差別化されていない場合も注意が必要です。
求人票の内容が似通っていると、求職者はどの企業も同じように見えてしまいます。
採用市場においては「情報を出しているかどうか」だけでなく「どのような情報を、どのように伝えるか」が重要になっています。
薬剤師が自社に興味を持ち、安心して応募できるような発信ができていないと、いくら条件を整えても採用は進みにくいのです。
伝わる情報の差が採用の壁になっている
採用活動では、企業が発信している情報と、求職者が受け取る情報に差が生まれやすいといわれます。
企業側は「魅力を十分に伝えた」と思っても、求職者にはその内容が正確に伝わっていない場合があるのです。
特に薬剤師の場合、転職活動の際に限られた情報しか得られないケースが多く、職場の雰囲気やチーム構成などを事前に知る機会が少ないのが現状です。
こうした“情報の見えにくさ”が、採用を難しくしている一因と考えられます。
薬剤師採用を成功に導くための主な3つの視点
薬剤師の採用が難しい状況を打開するには、従来の「求人掲載」や「条件強化」だけでは限界がある場合も。
求職者との接点づくりや企業の見せ方を見直し、採用の質を高めることが重要です。
ここでは、薬剤師採用を成功させるための主な3つの視点をご紹介します。
① 「職場のリアル」を見せる採用ブランディング
薬剤師の採用で重要なのは「リアルな職場の姿を伝えること」です。
どれだけ待遇を整えても「実際にどのような人が働いているのか」「どのような雰囲気の職場なのか」が見えなければ、求職者は応募をためらうこともあります。
採用ブランディングの第一歩は、職場の日常や社員の声を発信することです。
例えば、現場で働く薬剤師のインタビューや、チームの取り組みを紹介するコンテンツを社内サイトやSNSで公開する方法があります。
実際の働き方を可視化することで、求職者との信頼関係を築きやすくなるのです。
また、社員の声を通じて「どのような価値観を大切にしている職場なのか」を発信することで、企業文化への共感を得られます。
結果的に、応募の段階でミスマッチを防ぎ、採用後の定着にもつながることが期待できます。
② 薬剤師が働きやすい制度を整える
薬剤師の採用を成功させるには、働きやすい環境づくりも欠かせません。
例えば、時短勤務や週休3日制など、柔軟な勤務体系を設けることで、家庭やライフスタイルとの両立を重視する人材にもアプローチできます。
また、キャリア支援やスキルアップの機会を設けることも効果的です。
薬剤師は専門職である一方、職種や業態によって求められる知識が異なります。
そのため「教育体制が整っている」「新しい分野にも挑戦できる」環境を整えることが、採用の強みになるでしょう。
現職社員の意見を取り入れ、制度を定期的に見直すことも重要です。
こうした取り組みが「働きたい」と思われる企業づくりにつながるのです。
③ 採用チャネルを最適化し情報発信を強化する
「薬剤師採用が難しい」と感じる企業の多くは、採用チャネルが限られていることがあります。
従来の求人媒体だけでなく、SNS・自社メディア・口コミなど、複数のルートで情報を発信することが重要です。
特に、現職社員による口コミや体験談は、求職者にとって信頼性の高い情報源のひとつです。
「企業の発信」よりも「社員のリアルな声」を重視する傾向が強まっており、これを採用広報に生かす企業が増えています。
また、求人情報をただ掲載するのではなく、職場の写真やエピソードを添えることで、企業の“温度感”を伝えられます。
それにより、求職者は「自分が働く姿」を具体的にイメージしやすくなり、応募へのハードルが下がります。
情報発信を継続的に行うことは、採用活動の“地力”を高める上でも重要です。
薬剤師にとって魅力的な情報を、タイミングよく、分かりやすく届けることが、採用成功の近道といえるでしょう。
社員の声を活かした採用ブランディングの実践│VOiCE紹介
リアルな社員の声が採用に効く理由
薬剤師の採用が難しいと感じる企業の多くは、求職者との信頼関係づくりに課題を抱えている場合があります。
その中で注目されているのが「現職で働く社員の声」を活用した採用ブランディングです。
求職者は、求人票や企業サイトの情報だけでなく、実際に働く人のリアルな感想を重視する傾向にあります。
「どのような職場なのか」「どのような上司や同僚がいるのか」といった情報があると、自分が働くイメージを持ちやすくなります。
こうした“生の声”があることで、企業の雰囲気や価値観が伝わり、応募の後押しにつながる場合があるのです。
また、リアルな声を通じて企業文化を知ることで、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
結果的に、採用の効率化だけでなく、定着率の向上にもつながる可能性があります。
薬剤師の採用難を感じる企業ほど、まずは自社の「内側の声」を活用した発信に目を向けることが大切です。
VOiCEで実現する透明性のある採用広報
採用活動において「信頼できる情報」をどう発信するかは、今後ますます重要になるでしょう。
そのひとつの手段として注目されているのが、社員の声を見える化するサービスです。
VOiCEは「現職で働く社員によるリアルな声」を集めた口コミサイトです。
企業の公式情報だけでなく、実際に働く社員の声を通して、職場の雰囲気や組織の特徴を伝えられます。
求職者にとって信頼性のある情報を提供できる可能性があるため、企業と求職者のミスマッチを防ぐ一助となります。
また、VOiCEを活用することで、企業は自社の採用ブランドを客観的に伝えられます。
「第三者の視点で語られるリアルな声」があることで、求職者からの信頼を得られる可能性が高まるのです。
薬剤師の採用活動においても、透明性を重視した情報発信は、他社との差別化に役立つでしょう。
まとめ:薬剤師の採用を難しくしないために今できること
薬剤師の採用が難しいとされる背景には、人材の不足だけでなく、求職者との情報ギャップもあります。
給与や待遇といった条件面の改善も大切ですが、求職者が安心して応募できる「情報の透明性」を高めることが、採用成功の鍵になります。
そのために有効なのが、実際に働く社員の声を活用した採用広報です。
働く人のリアルな声を伝えることで、企業の姿勢や価値観が自然に伝わり、求職者が職場をより深く理解する助けとなります。
結果として、応募の質の向上や入社後の定着率アップをサポートする一助になり得るのです。
VOiCEのような現職社員の声を可視化できるサービスを活用すれば、企業の取り組みをより信頼性のある形で発信できる可能性があります。
薬剤師の採用を「難しい」ままで終わらせないためには、まず自社の魅力を“内側から伝える”工夫を検討してみるのもよいでしょう。