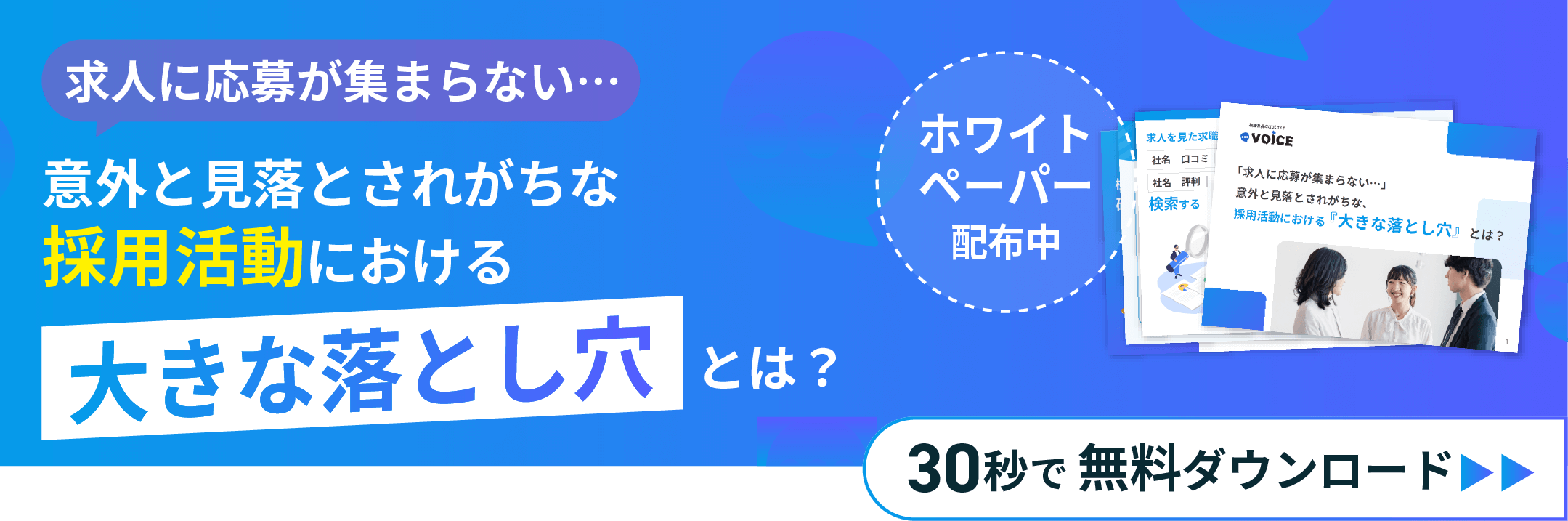2026年の“採用難時代”を生き抜くには?未来予測と今すぐ実践すべき戦略
- 内定辞退
- 採用活動
- 採用課題
2025.10.22
人手不足、応募数の減少、採用コストの上昇──。
こうした課題に直面し「採用が難しい」と感じる企業は増えています。
「以前と同じ方法では採用がうまくいかない」と感じている経営者や人事担当者も多いでしょう。
実際、2025年以降は業界を問わず“採用が難しい時代”に突入すると予測されています。
これは労働人口の減少だけでなく、働く人の価値観や情報収集の手段が大きく変化しているためです。
つまり、これまでのように求人サイトに掲載するだけでは、十分な応募を得ることが難しくなりつつあります。
2026年の採用市場はどのように変化するのでしょうか。
また、企業はこの「採用が難しい時代」をどう乗り越えるべきなのでしょうか。
この記事では、採用環境の未来予測をもとに、採用が難しいとされる背景を整理し、これからの時代に求められる採用戦略を具体的にご紹介します。
2026年の採用市場はどうなる?──採用が難しい時代は続くのか
1. 求職者の数がさらに減少する
総務省の統計によると、日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少を続けています。
※出典:総務省「生産年齢人口の減少」(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nd121110.html )
この流れは今後も止まらず、2026年には労働人口の減少がさらに加速する見通しです。
つまり、働く人の数そのものが減る中で、企業間の採用競争が激しくなるということです。
これまで以上に「人がいない」状態が当たり前になり、地方や中小企業では特に採用が難しい状況が広がると考えられます。
2. スキル構成の変化で求める人材が見つからない
2026年の採用市場では「数が減る」だけでなく「質のミスマッチ」も深刻化すると予測されています。
AI、データ分析、サステナビリティなどの新たなスキルが求められる一方で、そうした分野の即戦力人材はまだ限られています。
企業は、未経験者のポテンシャル採用や社内育成を含めた長期的な戦略を取らなければ、必要な人材を確保しにくくなるでしょう。
こうしたスキルのミスマッチが、採用を難しくする大きな要因になると考えられます。
3. 求職者の行動は「スピード」と「体験」重視へ
近年、求職者が複数の企業の選考を並行して進めるケースは一般的になっています。
2026年にはこの傾向がさらに強まり、応募から内定までのスピード感が採用成功の分かれ目になるでしょう。
また、求人票の内容だけでなく、面接時の対応やオンライン説明会など「候補者体験(CX)」全体が意思決定に大きく影響します。
「丁寧で誠実な対応を受けた企業を選ぶ」という傾向が強まり、プロセス設計の巧拙が“採用が難しいかどうか”を左右する時代に入ると考えられるでしょう。
4. 情報発信の中心がSNSと口コミサイトへ
2026年の採用活動では、企業発信の在り方が大きく変わると考えられます。
これまで主流だった求人サイトや転職エージェントに加え、SNSや口コミサイトを通じた「リアルな情報」が重視されるようになるでしょう。
求職者は、企業の公式メッセージよりも、実際に働く社員の声を信頼する傾向が強まっています。
こうした動きへの対応が後回しになっている企業は、どれだけ魅力的な制度を持っていても、その価値が伝わらず「採用が難しい」と感じることになりかねません。
5. 企業の“採用ブランディング格差”が広がる
採用が難しいとされる2026年においては、単に人を集める力ではなく「選ばれる力」が企業の明暗を分けます。
SNSでの発信や社員インタビュー、オウンドメディアの活用など、継続的に企業の魅力を発信してきた企業は、一定の応募を維持できる可能性があります。
一方で、発信が少ない企業や、情報が古いままの企業は、求職者からの信頼を得にくく、採用が難しい状況に陥るリスクがあります。

なぜ「採用が難しい時代」が続くのか——未来視点での分析
2026年の採用市場を取り巻く課題は、一時的な景気変動ではありません。
「採用が難しい」状況は、社会構造そのものの変化によって生まれた、長期的なトレンドといえます。
ここでは、その背景を4つの視点から整理します。
1. 人口の変化によって生じる「長期的な採用の難しさ」
まず避けて通れないのが、労働人口の減少です。
生産年齢人口が減少する一方で、引退する高齢層が増加し、労働需給のバランスが崩れつつあります。
今後は企業間だけでなく、業界を越えた人材の取り合いが進むと考えられます。
例えば、これまで安定して人材を確保できていた医療・介護、建設、運輸業でも、若年層の確保が難しくなりつつあるでしょう。
加えて、非正規雇用や副業・フリーランスの増加により「企業に所属して働く人」の割合も減少傾向にあります。
こうした社会的背景が、採用が難しい状況を長期化させているのです。
2. 働き方の価値観が変化し企業選びの基準が多様化
若手世代を中心に、仕事選びの基準は大きく変わりつつあります。
安定志向から“自己実現”や“柔軟な働き方”を重視する傾向が強まり「給与や福利厚生だけでは応募が集まらない」時代に変化しているのです。
さらに、テレワークや副業制度が広がったことで、求職者は地域や雇用形態に縛られず、より多くの選択肢から企業を比較できます。
その結果、従来の採用広報だけでは「選ばれる理由」を伝えにくくなっているのです。
求職者の関心は、企業理念や働く人の雰囲気、成長できる環境などの「体験的価値」に移っている傾向にあります。
この変化への対応が遅れがちな企業ほど、採用が難しいと感じやすくなるでしょう。
3. 企業の透明性が求められる時代に
かつては、企業が発信する情報が採用活動の中心にありました。
しかし今では、実際に働く社員の声や職場の雰囲気を、SNSや口コミでも知ることができます。
つまり、企業が一方的に発信する情報だけでは、信頼を得にくい時代になったのです。
特に若年層の就職活動では「口コミや評判を見てから応募する」という流れが一般化しています。
企業の公式発信と、実際の社員の声との間にギャップがある場合、“リアルな姿を見せていない企業”として求職者に選ばれにくくなることも。
これからの採用活動では、表面的なPRよりも、社員の声を通じて企業文化や価値観を正しく伝える取り組みが必要といえます。
採用が難しいと感じる企業ほど、まずこの「情報の透明性」を見直していくのが大切です。
4. 採用活動の主軸が“発信”から“信頼構築”へ
これまでの採用は「いかに多くの人に情報を届けるか」が中心でした。
しかし今後は、「いかに信頼を得るか」に重きが置かれるようになると考えられます。
求職者は企業のメッセージを“広告”としてではなく、“体験”として感じたいと考えている傾向にあります。
そのため、社員インタビューやSNS発信、口コミなど、リアルな声を通じた採用広報が重視されるのです。
企業が発信する情報が“信頼できるもの”と受け止められれば、応募数だけでなく、マッチ度の高い採用につながる場合があります。
反対に、情報発信が少なかったり、一方的だったりすると「どのような会社か分からない」という印象を与え、採用が難しい状況に陥るおそれがあるのです。
採用難を乗り越えるために今から実践できる4つの採用アプローチ
採用市場の競争が激しくなる中「新しい取り組みを始めたいが、何から着手すれば良いか分からない」という声も多く聞かれます。
ここでは、今からでも実践できる4つの採用アプローチをご紹介します。
1. 社員紹介(リファラル採用)の仕組みを整える
リファラル採用とは、社員が知人や友人を自社に紹介する採用手法です。
求職者にとっては「信頼できる人の推薦」が安心材料となり、企業にとっても「自社に合う人材」と出会いやすいというメリットがあります。
導入にあたっては、まず以下の3点を整えることが重要です。
- 紹介の流れを明確にし、誰でも使いやすい仕組みにする
- 紹介した社員を適切に評価・感謝する文化をつくる
- 採用担当者が積極的に社内へ発信し、参加を促す
近年では、専用のリファラル管理ツールを活用する企業も増えています。
小規模な組織でも取り入れやすく、社員のエンゲージメント向上にもつながるアプローチです。
2. SNS・動画を活用した採用広報
求職者の情報収集手段が多様化するなか、SNSを通じて企業のリアルな姿を発信する動きが広がっています。
特にInstagramやTikTok、YouTubeなどでは、社員インタビューやオフィス紹介、1日の業務の様子を短くまとめた動画が人気です。
ポイントは、「採用の宣伝」ではなく「どのような人が、どのような想いで働いているか」を伝えること。
制作コストをかけずとも、スマートフォンで撮影した動画や社員自身の投稿でも十分に効果が期待できます。
日常の雰囲気を自然に伝えることが、共感や応募動機につながるでしょう。
3. スカウト型サービスで「待たない採用」を進める
求人を出して応募を待つだけではなく、スカウト型の採用プラットフォームを活用し、自ら候補者にアプローチする採用も一般化しています。
特に若手や専門職では、スカウトメッセージの内容が応募意欲を左右するケースが多く「テンプレートではなく、個人に合わせたメッセージ設計」が成果の分かれ目となります。
導入時には以下を意識しましょう。
- スカウト対象者の人物像(ペルソナ)を具体的に描く
- スカウト文には「なぜ声をかけたのか」を明確に記載する
- 返信率を定期的に分析し、メッセージ内容を改善する
この手法は採用スピードの向上だけでなく、求職者との新しい接点づくりにもつながります。
4. 「社員の声」を活かしたオウンドメディア発信
採用サイトや企業ブログなど、自社メディアを活用した情報発信も有効です。
特に近年注目されているのが、現職社員のリアルな声をコンテンツ化する方法です。
社員インタビューや座談会記事、プロジェクト紹介などを通して、働く環境や社風を伝えることで、企業の信頼性や透明性を高めることができます。
重要なのは、過度に理想化せず「実際にどのような価値観を大切にしているか」を等身大で伝えること。
求職者が「この会社なら自分らしく働けそう」と感じるきっかけになります。
継続的に発信することで、採用活動だけでなくブランディングにも良い影響をもたらすでしょう。
採用環境の変化に対応するには、大きな投資やシステム導入が必要なわけではありません。
リファラル採用やSNS発信、スカウト運用、社員の声の活用といった身近なアプローチを積み重ねることが、結果として「選ばれる企業づくり」につながります。
採用を単なる募集活動ではなく、企業の魅力を発信する戦略として捉えることが、これからの時代に求められる採用のあり方です。
これからの採用は「信頼構築」が鍵——自社採用力を高める発信とは
前章ではさまざまな採用アプローチについてご紹介しました。
しかし、どのような手法を選んでも成果を左右するのは「自社の信頼性」です。
応募者が企業を選ぶ際、重視するのは給与や条件だけではありません。
「この会社は信頼できるか」「自分の価値観と合っているか」といった“見えない要素”を重視する傾向が年々高まっています。
つまり、今後の採用で鍵を握るのは、信頼を軸にした自社採用力の強化です。
自社採用力とは何か
自社採用力とは、求人広告やエージェントに頼らず、企業自身の発信や取り組みを通じて「応募したい」と思わせる力のことです。
これは一朝一夕で身につくものではなく、日常的な発信と誠実なコミュニケーションの積み重ねによって育まれます。
採用力が高い企業の共通点として、次のような特徴が挙げられます。
- 社員の声や働く環境が、社外にも自然に伝わっている
- 企業理念やビジョンが、具体的なエピソードで語られている
- SNSやオウンドメディアでの情報が定期的に更新されている
- 採用ページにリアルな情報が掲載され、誇張や演出が少ない
こうした取り組みを通して企業の“人格”が伝わり、結果的に応募の質と量が向上します。
採用活動は「発信活動」へ
これまでの採用は、求人票やエージェントに情報を掲載する「募集中心の活動」でした。
一方、これからは「自らの価値を伝え、共感を得る活動」へと変化しています。
SNSや採用サイト、インタビュー記事、動画など、発信の手段はさまざまですが、重要なのは「誰が」「どのような想いで」「どのような言葉で伝えるか」という点です。
特に効果的なのが、社員自身が語るストーリー発信です。
例えば、
- 新入社員が入社の決め手を語るインタビュー
- 管理職が大切にしているチームマネジメントの考え方
- 社員が日々の仕事のやりがいを紹介する動画
こうした“生の声”は、企業からのメッセージよりも強い説得力を持ちます。
求職者は自分と近い立場の人の発言を通して、企業の実像を感じ取りやすくなるのです。
「信頼」は一方向の発信では築けない
注意すべきは、発信が“宣伝”に偏ってしまうことです。
自社の魅力を伝えることは大切ですが、過剰な表現や演出は逆効果になる場合もあります。
例えば「社員全員が笑顔で働いている」「離職率ゼロ」といった過度な表現は、実際の印象と乖離が生じやすく、結果的に信頼を損なうリスクがあります。
重要なのは、「ありのままを丁寧に伝える」姿勢です。
また、発信は一方通行ではなく、双方向のコミュニケーションであることも意識しましょう。
SNSでのコメント対応や、採用イベントでの質疑応答などを通じて、「話せる会社」「対話できる会社」という印象を積み重ねることが、信頼構築の第一歩となります。
自社採用力を高める“発信の習慣化”
信頼を生む発信を続けるには、担当者1人に任せるのではなく、組織全体で「採用広報文化」をつくることが大切です。
- 月に1本、社員の声を紹介する記事を更新する
- SNSで週に1回、社内イベントや仕事風景を投稿する
- 採用チームと現場リーダーが定期的にテーマを話し合う
こうした“小さな継続”が、長期的に見れば大きな採用資産となります。
採用力とは、短期的な成果ではなく、「誠実な情報発信を積み重ねられる企業文化」そのものなのです。
信頼される採用活動を支える——「VOiCE」という選択肢
前章でお伝えした通り、これからの採用活動では「信頼の構築」が何よりも重要になります。
その信頼を支えるためのひとつの方法として注目されているのが、社員の声を活かした情報発信です。
社員一人一人が語る「働くリアル」は、企業の公式メッセージ以上に、求職者にとって価値のある情報になります。
とはいえ、「どのように収集・発信すればよいか分からない」「自社で取り組む時間がない」と悩む企業も多いでしょう。
そこで活用できるのが、現職社員によるリアルな声を集めた口コミサイト『VOiCE』です。
VOiCEとは
VOiCEは、実際に企業で働く社員が、自身の経験をもとに職場の魅力や環境について発信できる口コミサイトです。
一般的な口コミサイトとは異なり、現職社員の声を中心とした“現在進行形の情報”を掲載している点が特徴です。
求職者は、VOiCE上で企業のリアルな雰囲気や働き方、社員の価値観などを知ることができます。
一方、企業側は「自社で働く人たちの言葉」を通して、透明性のある採用広報を行うことが可能になります。
VOiCEが選ばれている理由
VOiCEの特長は、単なる口コミサイトではなく、“信頼を可視化する場”として機能している点にあります。
1. 現職社員の声を重視
匿名の投稿や退職者の体験談ではなく、現職社員が自らの体験をもとに語る仕組みを採用しています。
そのため、投稿内容には信頼性があり、求職者にとっても参考になる情報として活用されています。
2. 企業と社員の双方にメリット
企業はVOiCEを通して、社員の声を整理・発信しやすくなります。
また、社員が自らの言葉で職場を語ることで「自分の声が会社の魅力づくりに貢献している」という意識が生まれ、エンゲージメント向上にもつながります。
3. 採用広報の信頼性を高める
VOiCEを活用することで、企業の採用ページや求人情報とあわせて、第三者視点に近い“社員の声”を提示できます。
誇張や演出ではなく、実際の働く人の言葉が中心になるため、求職者とのギャップを減らすことができます。
まとめ:採用の未来は「信頼発信」の積み重ねにある
2026年以降の採用市場では、条件面の競争だけでは勝ち残れません。
求職者が重視するのは「この会社の人たちと働きたい」と思える信頼と共感です。
その信頼をつくる第一歩が、社員のリアルな声を伝える発信です。
VOiCEは「信頼を届ける採用」をサポートする手段のひとつとして、導入する企業も増えています。
今後の採用活動を見据える上で「信頼をどう築くか」を中心に据えた戦略を考えることが、採用難時代を生き抜くヒントになるでしょう。