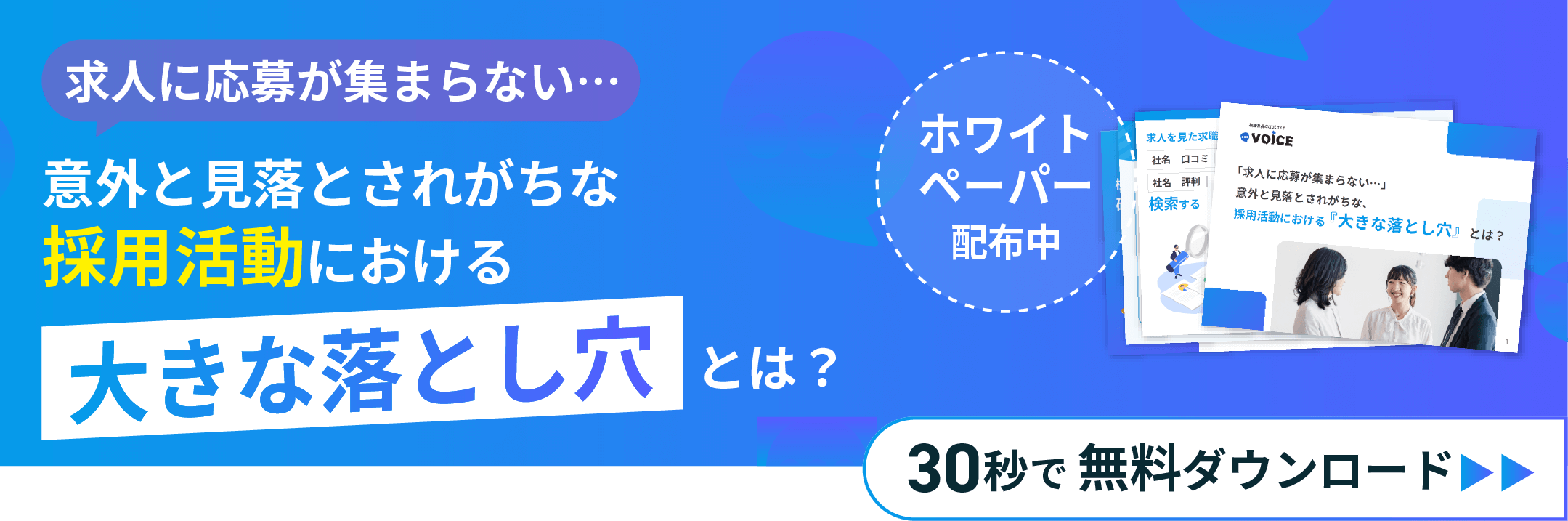新卒の離職率は「採用前」に決まる?リアルな情報発信が離職防止に効く理由
- 採用ミスマッチ
- 採用課題
- 離職防止
2025.10.22
新卒社員の離職率は、長年にわたり多くの企業にとって悩みの種となっています。
厚生労働省のデータによると、新卒社員の約3割が3年以内に離職していることがわかります(※1)。
この数字は業種や規模を問わず、高止まりが続いている状況です。
離職の理由として多く挙げられるのが「入社前に抱いていた期待とのギャップ」です。
仕事内容だけでなく、社風や人間関係、成長機会など、数字やデータでは表せない部分の誤認が影響しているケースも少なくありません。
一見、入社後の教育やマネジメントの問題に見えますが、実は「採用段階」に原因が潜んでいることもあります。
採用前にどのような情報を届けるかによって、入社後の定着率が変わる可能性もあります。
この記事では、新卒の離職率を左右する採用前の情報発信の重要性と、リアルな情報を届ける手段のひとつである「VOiCE」の活用についてご紹介します。
第1章:新卒の離職率はなぜ高止まりしているのか
数字で見る新卒離職率の現状
厚生労働省が公表した新規学卒就職者の離職状況データによると、大学卒の新卒社員の3年以内離職率はおよそ35%。短大卒では約45%、高卒では約38%となっています(※1)。
この傾向は過去10年以上にわたり、多少の増減はありつつも大きくは変化していません(※2)。
つまり、多くの企業が「新卒の定着」という課題を長期的に抱えている状況がうかがえます。
(※1)出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html )
(※2)出典:厚生労働省「学歴別就職後3年以内離職率の推移」
(https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001318971.pdf )
離職率が下がらない背景
離職率が高止まりしている背景には、いくつかの要因があると考えられます。
ここでは、いくつかある要因の中で代表的な3つをご紹介します。
1. 採用段階でのミスマッチ
求人情報や採用サイトでは、企業の魅力を伝えることに重点が置かれがちです。
しかし、現場の実態や社風といった数値化できない情報が伝わりきらないことで、入社後に「思っていたのと違う」と感じるケースがあります。
2. キャリアの展望が不透明
新卒社員は将来の成長イメージを重視する傾向にあります。
しかし、具体的なキャリアパスや評価制度が十分に伝わっていないと、不安を抱きやすくなり、離職につながる場合があるのです。
3. 働き方や価値観の変化
最近の新卒層は「安定よりもやりがい」「長時間よりもワークライフバランス」を重視する傾向があります。
こうした考えと企業側の価値観がすれ違うことで、早期離職につながることもあります。
企業と求職者の間にある情報の差
採用活動において、企業と求職者では持っている情報に差があります。この差が新卒の離職率に影響を及ぼしていると考えられるのです。
企業は職場環境や人間関係の実情を把握していますが、外から企業を見ている求職者はそれを知ることができません。
結果として、入社後に初めて現実を知り、理想とのギャップに戸惑うケースもあります。
採用広報では「どう見せるか」だけでなく「どこまで正確に伝えるか」が求められる時代になっています。
情報の透明性が信頼を生み、結果的に新卒離職率の低下につながる可能性があります。

第2章:新卒の離職理由に潜む“情報ギャップ”
新卒の離職率が高止まりしている背景には、入社前と入社後の情報ギャップがあります。
この「ギャップ」とは、求職者が想像していた職場の姿と、実際の環境や働き方の間にあるズレのことです。
入社前の期待と現実のズレ
多くの新卒社員が離職を考えるきっかけとして挙げるのが「思っていた仕事と違った」という声です。
この“期待と現実のズレ”は、仕事内容そのものよりも、働く環境や人間関係、社風といった目に見えにくい部分で生じることが多いといわれています。
例えば、
- 「風通しのよい職場」という表現を目にして入社したものの、実際には上司との距離が遠く、意見を言いづらい雰囲気だった──。
- 「若手が活躍できる」と聞いていたのに、実際は裁量が限られていた。
こうした小さなギャップの積み重ねが、早期離職の引き金になることもあります。
採用の現場では、企業イメージを良く見せるためにポジティブな情報が中心になりがちです。
しかし、求職者が知りたいのは“良い面だけではなく、リアルな姿”です。
その差を埋めることが、新卒離職率を下げる第一歩といえます。
見えにくい「職場のリアル」が離職を招く
新卒採用では、学生が職場を直接体験する機会が限られています。
会社説明会や採用サイトで得られる情報も限られているため、実際の業務や社風を十分に理解できないまま入社を決めるケースも見られます。
また、企業が発信する情報はどうしても「企業側の視点」になりがちです。
社内文化や上司との関係、日常の雰囲気など、求職者が働く上で重要なポイントが見えにくいまま採用が進むと、入社後に“思っていた職場と違う”と感じやすくなります。
特に近年の若手世代は、企業選びにおいて「自分に合うかどうか」を重視する傾向があります。
そのため、仕事内容の説明だけでなく、職場のリアルな空気感や人間関係まで伝えることが大切です。
採用広報が陥りやすい“理想像の発信”
採用広報では、企業の魅力をアピールすることが目的のひとつです。
ただし「自社の理想像」を前面に出しすぎると、求職者の期待を過度に高めてしまうことがあります。
例えば、実際にはチームワークを重視する文化があるのに「個人の成果を評価する会社」と打ち出すと、入社後に価値観のズレが生まれます。
このような誤認が続くと、新卒の早期離職率の上昇につながるおそれがあります。
採用広報の目的は「応募を集めること」ではなく、「自社に合う人材に出会うこと」です。
そのためには、企業の強みだけでなく、働く上での難しさや課題も、できる範囲で誠実に伝える姿勢が求められます。
情報ギャップを減らす採用コミュニケーションへ
新卒離職率を下げるためには、採用段階でどれだけ“リアルな情報”を届けられるかが鍵になります。
企業側の発信だけでなく、現場で働く社員の声や日常の様子など、一次情報を求職者に届ける工夫が必要です。
「働く人のリアル」を伝えることは、企業の透明性を高めるだけでなく、応募者の信頼にもつながります。
結果として、入社後のミスマッチを防ぎ、長く働き続けてもらえる職場づくりへとつながる可能性があります。
第3章:離職率改善において「リアルな社員の声」が果たす役割
「リアルな声」が信頼を生む理由
新卒の離職率を下げるためには、採用活動における“信頼関係の構築”が欠かせません。
応募者が企業に対して信頼を感じる瞬間は「自分が働く姿をリアルに想像できたとき」です。
この想像を支えるのが、現場で働く社員の“リアルな声”です。
人事担当者の言葉だけでは伝わりにくい職場の雰囲気や文化も、社員自身の語りを通じてなら自然に伝わります。
「どのような人が働いているのか」「どのような価値観を持っているのか」といった定性的な情報が可視化されることで、応募者は企業に対する理解を深めやすくなります。
また、複数の社員の声が掲載されていれば、個人の主観に偏らず、より客観的な印象を与えられます。
こうした透明性のある情報発信は、応募者の不安をやわらげ、入社前の期待値を適切に調整する効果が期待できます。
入社後の“ギャップ”を減らすための第一歩
新卒者が入社後に感じるギャップは、離職理由の一因となることも多いです。
しかしその多くは、採用段階で“伝わっていなかった情報”に起因しています。
例えば、先輩社員の1日のスケジュールや、実際のプロジェクトの流れ、チームでのコミュニケーションの様子など。
これらは求人票や説明会だけでは伝えきれない部分です。
社員インタビューや口コミを通じて、こうした情報を事前に知ることができれば、求職者は入社後の働き方を具体的にイメージしやすくなります。
結果として「思っていたのと違う」という理由による早期離職の防止につながる可能性があります。
特に、新卒採用においては“リアルな社員の声”がミスマッチを防ぐ有効な手段のひとつといえるでしょう。
採用広報における“ストーリーテリング”の力
リアルな社員の声を活かした採用広報は、単なる情報提供だけにとどまりません。
それは「社員一人一人のストーリーを通して企業の魅力を伝える」という役割も果たします。
例えば、入社3年目の若手社員がどのように成長してきたのか。
仕事で悩んだ経験や乗り越えたエピソードを共有することで、求職者は自分の将来像を重ねやすくなります。
この“共感”が生まれることで、企業は単なる「働く場所」ではなく「自分の価値を発揮できる場所」として認識されやすくなる可能性があります。
こうした感情的なつながりは、採用後の定着やエンゲージメントにも良い影響を与えることが期待されます。
「発信者」を社員に変えることで見えてくるもの
近年は、企業公式アカウントや採用サイトに加え、社員自らが登場する発信が注目されています。
社員の言葉には、広報メッセージにはないリアリティがあります。
「どのような先輩がいるのか」「仕事のやりがいをどう感じているのか」といった内容を、実際の社員が語ることで、企業文化の温度感まで伝わります。
特に新卒層にとっては、同世代や少し年上の先輩の声が強い共感を呼ぶことがあります。
こうした“社員が語る採用広報”は、応募者との心理的距離を縮める効果があり、結果として新卒離職率の改善にもつながると考えられます。
信頼は「リアル」から生まれる
採用活動で発信する情報の中でも、特に信頼されやすいのは“リアルな体験談”です。
企業の公式発信だけでなく、社員の声を組み合わせることで、より立体的に職場の姿を伝えられます。
こうした発信は「良いことばかりを並べる」ものではなく、誠実にありのままを伝える姿勢こそが求職者の信頼を生みます。
その信頼が、結果的に入社後の満足度や定着率の向上につながっていくのです。
第4章:VOiCEで実現する“リアルな採用広報”
VOiCEとは
VOiCEは、現職で働く社員のリアルな声や口コミを集めたプラットフォームです。
企業が発信する採用メッセージだけでなく、実際に働く社員が感じている職場の魅力や課題を、求職者が知ることができます。
従来の採用広報は、企業側の視点で「どう見せるか」を中心に設計されてきました。
しかし、VOiCEは「働く人の視点」から企業を伝えることを重視しています。
そのため、企業が発信する情報だけでは伝わりにくい“現場のリアル”を、求職者に直接届けることが可能です。
VOiCEが提供する価値:透明性と信頼の可視化
新卒採用において、求職者が特に不安に感じるのは「入社後の自分を想像できないこと」です。
VOiCEでは、実際の社員が投稿したコメントやエピソードを通じて、職場の雰囲気・人間関係・成長機会など、数字では表せないリアルな情報を伝えられます。
例えば、ある部署での働き方やチームの雰囲気、上司との関係性など、採用サイトだけでは見えにくい情報を共有することで、応募者は自分との相性を具体的に判断する参考にできます。
結果として、採用前に生じる情報ギャップを小さくし、新卒離職率の改善につながる可能性があるのです。
また、VOiCEに掲載されるコメントは、社内アンケートで集めた「現職社員の声」です。
匿名性を保ちつつも信頼性のある仕組みにより、リアルな声の発信が行われています。
これにより、企業と求職者の間に「正直で開かれた関係性」を築くことに役立ちます。
採用広報の新しい形へ
これまでの採用広報は、企業が一方的に情報を発信する形が主流でした。
しかし今後は「社員と企業がともに語る採用広報」が重要になっていきます。
VOiCEは、そのサポートとなる口コミサイトです。
働く人の言葉が企業の魅力を自然に伝え、求職者との共感を生み出します。
こうしたリアルなコミュニケーションを積み重ねることで、結果的に新卒離職率を下げる効果が期待できるのです。
VOiCEでミスマッチのない採用へ
「どのような会社で、どのような人と働くのか」。
この問いに、リアルな答えを届けられるかどうかが、採用活動における参考になります。
VOiCEは、社員の声を通して企業の姿を可視化し、応募者に“働く前のリアル”を伝えるための手段のひとつです。
採用の透明性を高め、求職者との信頼を築くことが、結果的に離職率改善の近道となる可能性があります。
まとめ:離職率改善の鍵は「採用前の情報発信」にある
新卒の離職率を下げるために重要なのは、入社後のフォローよりも「採用前の情報の伝え方」です。
採用活動で企業の強みだけでなく、リアルな日常や社員の声を発信することで、求職者とのミスマッチを軽減できる可能性があります。
VOiCEは、そのための実践的な手段のひとつとして活用できます。
企業と求職者の間にある情報の壁をなくし、“お互いを正しく理解した上での採用”の一助となるでしょう。